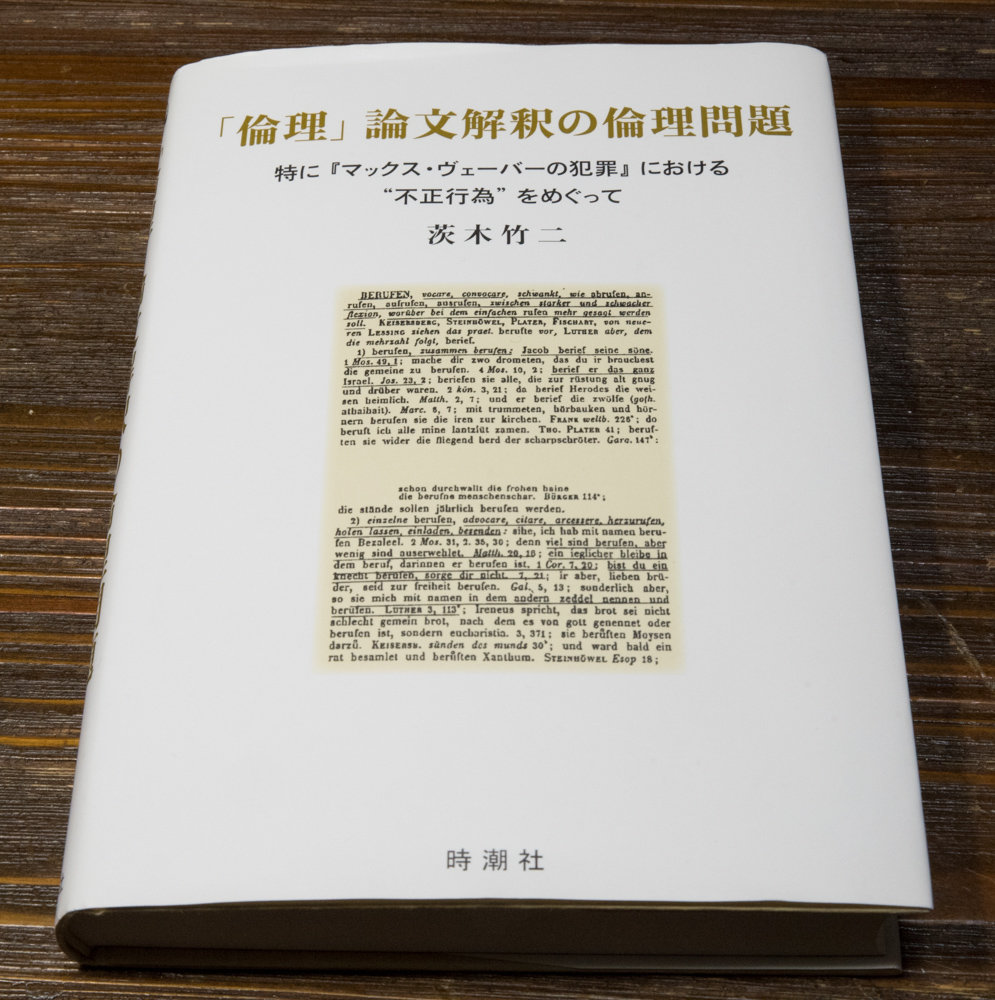 茨木竹二の「「倫理」論文解釈の倫理問題」を読了。
茨木竹二の「「倫理」論文解釈の倫理問題」を読了。
副題が「特に『マックス・ヴェーバーの犯罪』における”不正行為”をめぐって」になっていることから分かるように、羽入辰郎の「マックス・ヴェーバーの犯罪」についての批判がメインですが、それだけではありません。
筆者は、いわゆる「羽入-折原論争」とそれに関連した「日本マックス・ウェーバー論争」の議論について、論争が尻すぼみに終わったと考えており、それを「総括」するつもりでこの本に書いてある諸論文を書いたようです。
まず、「日本マックス・ウェーバー論争」への執筆者の一人として、何故「論争」が止まったかについて言及しておきます。基本的には「論争」と前後して出版された羽入辰郎の「学問とは何か―『マックス・ヴェーバーの犯罪』その後」という反論本が、学問として許される範囲の叙述を大きく超えた、非常に奇妙なデマゴギーの固まりであることが明らかな本であり、おそらくはこれを読んだ多くの人が、「もはやこの人は学者とは言えない」という感じを抱き、これ以上同氏の批判を続けることは学問としてまったく無意味と判断したであろうことが挙げられます。これは別に論争に参加したメンバーに直接確認した訳ではありませんが、おそらく大きくは外れていないと思います。
そういう状況にこの茨木氏の本が登場する訳ですが、同氏の論考は北海道大学の橋本努氏が開設した「羽入-折原論争」のHPの最後期に一度だけ、単なる「書誌情報」として紹介されていました。それは氏の在職する大学の研究紀要であり、一般には入手困難でまたインターネットで公開もされていなかったため、私は中身を見ていません。そうした氏が、何故今頃になって、「証文の出し遅れ」のような論考を発表したのかが、私は理解に苦しみます。氏は論争の総括が必要だと思った、と書いていますが、私が今回の論考を通読した限り、「総括」と呼べるようなまとめ的な内容はまったくありません。それ所か、私の論考を含む「先行する批判」に対しても、ほとんどといっていいほど言及がありません。(折原浩氏の論考・著作は除く。)
たとえば、この本では、ウェーバーのBerufという語の解釈について、グリムのドイツ語辞書での語義の言及がされます。しかし、ウェーバーがグリムのドイツ語辞書を参照しているのではないかという指摘は、既に私の論考の注釈に記載してあります。これに対して「終章」というまとめの中で矢野善郎氏が、ドイツででのマックス・ウェーバー全集の編集の際に、このグリム版辞典への参照の可能性などは、是非とも取り込まれるべき、と評価してくれています。以下、原文を引用します。
(引用開始)
グリムのドイツ語大辞典(CD-ROM版)で、”Beruf”と”Ruf”を調べてみた。このドイツ語大辞典が最終的に完成したのは、本文中に記述した通り1961年のことであるが、”Beruf”の項は1853年にJ. Grimm、”Ruf”の項は1891年にM. Heyneにより編集されており、ヴェーバーが倫理論文を書く前の編集である。ヴェーバーがグリム大辞典(の当時出版されていた分冊)を参照したかどうかは倫理論文中には記載されていないが、OEDの前身のNEDをあれだけ参照しているヴェーバーがグリム大辞典を参照しなかったということは想定しにくい。
“Beruf”の項では、2つの語義が書かれている。1つめはラテン語のfamaにあたる、「名声・評判」という意味である。2番目の語義が、ラテン語のvocatioに相当し(ドイツ語ではさらに新たな意味が付与された)、いわゆる「天職」である。ここでグリム大辞典は、この意味での語源の一つを、”bleibe in gottes wort und übe dich drinnen und beharre in deinem beruf. Sir. 11, 21; vertraue du gott und bleibe in deinem beruf. 11, 23” 、つまりヴェーバーと一致して「ベン・シラの書(集会の書)」としている。
これに対し、”Ruf”の項では、「過渡的な用法」として、「(内面的な使命としての)職業」を挙げている。また、「外面的な意味での職業」、つまり召命的な意味を含まない職業の意味ではほとんど用いられたことがなかったと説明されている。さらにはルター自身の用例が挙げられている:” und ist zu wissen, das dis wörtlin, ruff, hie (1 Cor. 7, 20) nicht heisze den stand, darinnen jemand beruffen wird, wie man sagt, der ehestand ist dein ruff, der priesterstand ist dein ruff. LUTHER 2, 314a” このルターの章句がどのような文脈で使われたものなのか、残念ながらまだ突き止められていない。しかしながら、ルター自身が、コリントI 7.20のこの部分を、今日のほぼすべての学術的聖書が採用する「状態」(Stand)の意味ではない、と明言しているのは非常に興味深い。
コリントI 7.20の翻訳にあたって、ルターは羽入が指摘したように、生前の翻訳においては、”ruff”または”Ruf”を使用し、”Beruf”とはしていない。このことの理由は、ヴェーバーが倫理論文で述べているように、古いドイツ語訳の訳語を尊重しただけなのかどうかはわからない。しかしながら、グリム大辞典にあるように、”Ruf”(”ruff”)は過渡的に使用され、最終的には”Beruf”に収斂している。この場合、ルターがコリントI 7.20を一貫してたとえば”Stand”とし、ルターの死後、ルターのあずかり知らないところでそれが”Beruf”に改訂されたのなら、確かにヴェーバーの議論は成立しない。しかしながら、”Ruf ”(”ruff”)にせよ、”Beruf”にせよ、元々は動詞であるrufen、berufenからの派生語であり、そのどちらにも今日のような「世俗的職業」という意味はまったく含まれていなかったのである。「神の召し」という意味に、世俗的職業という意味を含有させる可能性がある章句は、新約聖書全体では、このコリントI 7.20以外はありえないであろう。(コンコルダンスの「召す」の項目を参照。)その意味で、コリントI 7.20が「架橋句」であると解釈される。
このコリントI 7.20で橋渡しされた「召し」と「世俗的職業」という意味が、ベン・シラにおいて、翻訳者のある意味「意訳」によって、通常ならArbeitやGeschäftと訳されるべきものがBerufと訳され、ここに「翻訳者による新たな語義創造」は完成するとヴェーバーは述べている。この「ベン・シラの書(集会の書)」は、旧約聖書外典に含まれ、いわば「処世訓」的な性格のものである。ルターは、外典を含む聖書の全体をすべて同格にはけっして扱っていない。正典に含まれる「ヨハネ黙示録」や「ヤコブの手紙」を自分の教義とは違うからという理由で排除しようとしたのは有名である。その意味で、ベン・シラにおいて比較的「自由な」翻訳が行われたとしても、決して不思議ではない。
また、この「ベン・シラの書」の翻訳者がルターかメランヒトンなどの他の人間か、という議論も些末にすぎよう。ヴェーバーは「翻訳者の精神」の翻訳者を複数形にしており、「ルター」と書いてあっても、それは「ルターが中心になっていた聖書の翻訳グループ」と解釈すべきであろう。
なお、この問題について、改めて整理して詳論する機会もあるかもしれないが、当論考においては、脚注にとどめておくことにしたい。
(引用終了)
私はここで、グリムの辞典に出てくる用例で、「ルター自身が、コリントI 7.20のこの部分を、今日のほぼすべての学術的聖書が採用する「状態」(Stand)の意味ではない、と明言している」という、ある意味非常に重要な指摘をしています。これについては、どのような文脈でいつ言われたのかを調べることが、ルターがどのようにこの部分を「状態」から「職業」に解釈替えしたのかということを明らかにすることになります。残念ながら、その後ルター全集を個人で買うことも、図書館で調べることも私は出来ていません。(インターネット上に全文がなく、検索で発見することも出来ていません。)折角またウェーバ-のグリム辞典への参照を指摘するのであれば、こうした点についても調べて欲しかったです。少なくとも「総括」という言葉を使うのであれば。
羽入批判として見た場合、その多くの部分が羽入の文献の引用の仕方についてであり、羽入が著作権法や文科省から出ているガイドラインで規定されている引用のルールを無視し、かなり恣意的な引用操作が行われていることを明らかにしています。このこと自体は重要な指摘で、羽入批判として十分な価値があることを認めるのは何らやぶさかではありません。しかしながら、羽入以外に中野敏男氏への批判としても使われているこの引用のルールですが、何か「引用ルールパリサイ人」のような、あまりにも窮屈なルールの主張のように思えることも事実です。私見ですが、著作権法が定める引用の制限は、ある意味自由な学問の発展にとってはそれを阻害するものでもあり、あまりにも厳格なルールの主唱は、今後論文を書いていく若手研究者にとっての足枷になるのではないかと懸念せざるを得ません。もちろん恣意的な引用操作は言語道断ですが、少なくとも文献表で該当文献が別途確認可能である限りにおいては、「パリサイ人」的なルール化は私は望ましくないと思います。
そのことと関連しますが、中野敏男氏への批判として、”Gewiss…, Aber”(なるほど…だが、だがしかし…)の解釈を巡っての、実に長大な批判が展開されます。まず批判の最大の根拠は、”Gewiss”と”Aber”の登場位置が離れすぎているということですが、この点はごもっとも、と思いつつも、ウェーバーの場合、最初に書いた文章に付け足していってどんどん増えていって、最初は近接していた2つの語が、最終的には遠く離れてしまった、という可能性も否定できません。実際に「経済と社会」の解読を、中野氏と一緒に行った経験がありますが、そういうケースは常に考慮していたと記憶しています。それもあって、きわめて長大な(正直な所くどいとしか言いようがない)説明にもかかわらず、私は中野敏男氏の解釈がまったくの誤りだという風には思えません。茨木氏は”:”をd.h.の代わりだとしますが、それ自体は間違いではないにせよ、GewissやAberの後にいきなり”:”が来るのはある意味異常な用法であり、遠く離れていてもその2つを関連付けて読もうとするのがまったくの間違いだと断定する気にはなれません。
後、情報として良かったのは、シュルフター教授が羽入の「ルター聖書はBerufではなくruff」という指摘を、あっさり否定して片付けているということがわかったことです。私は2004年9月20日にハイデルベルク大学を訪問してそこでシュルフター教授に面会し、羽入事件について報告しています。その時のシュルフター教授からの回答として「もうすぐ詳細な注釈付きのウェーバー全集が出るので、そこでそうしたことも論じられる」というお言葉をいただきましたが、それがきちんと実現していることがわかって嬉しく思いました。
更に、些末な指摘ではありますが、氏が引用について、””を「証明引用」、「」を「参照引用」として使い分けているのに、かなり面喰いました。本文についてはあらかじめ「凡例」で解説してあるので良しとしても、それがタイトル(副題)にまで説明なしで使われているのはどうかと思いました。また、Idealtypusの日本語訳について、「理想型」と「理念型」という2種類の訳語を混在させているのも理解に苦しみました。おそらく氏の別の論考に詳述されているのかもしれませんが、この論考だけを読む読者には何のことかわかりません。また「非難/批難」のような意味不明な表記ゆれや、「意外」を「以外」とする誤変換の放置(P.340)、私から言わせれば「老人語」である「如上の」という表現の過剰な使用、など日本語理解で苦労することが多くありました。ご自身で書いておられるように論旨が錯綜した上に冗長で、もう1回読みたくない文章と言わざるを得ません。
それからグリム辞典の「ベン・シラ」の引用の章句番号が間違っているのではないかということで、「ママ!」のような実に「耳目聳動的」な表現が用いられています。羽入がOEDを間違っていると断定したのと同じ匂いを感じざるを得ません。私はむしろ、聖書の章節分けが1551年のエチエンヌのギリシア語テキストから始まったもので、ルター聖書はルター自身による最後の校正は1545年なので、この時には章節番号自体が存在していない、ということを指摘させていただきます。またベン・シラという「旧約聖書続篇」であることも考慮すると、むしろルター死後のルター聖書に章節番号が付けられた時に、何かのミスか混乱で今日のものとは違う番号がついてしまったことも考えられ、単純に辞書の誤りとするには即断が過ぎると思います。
最後に、羽入書の悪影響で、社会学会でここ数年ウェーバーに関する研究発表をする若手がいなくなったということが指摘されていますが、私に言わせれば羽入ごときの指摘でびびってしまうような者はそもそもウェーバーについて研究することなど不可能だと思います。ある意味丁度いいフィルターなのではないでしょうか。
