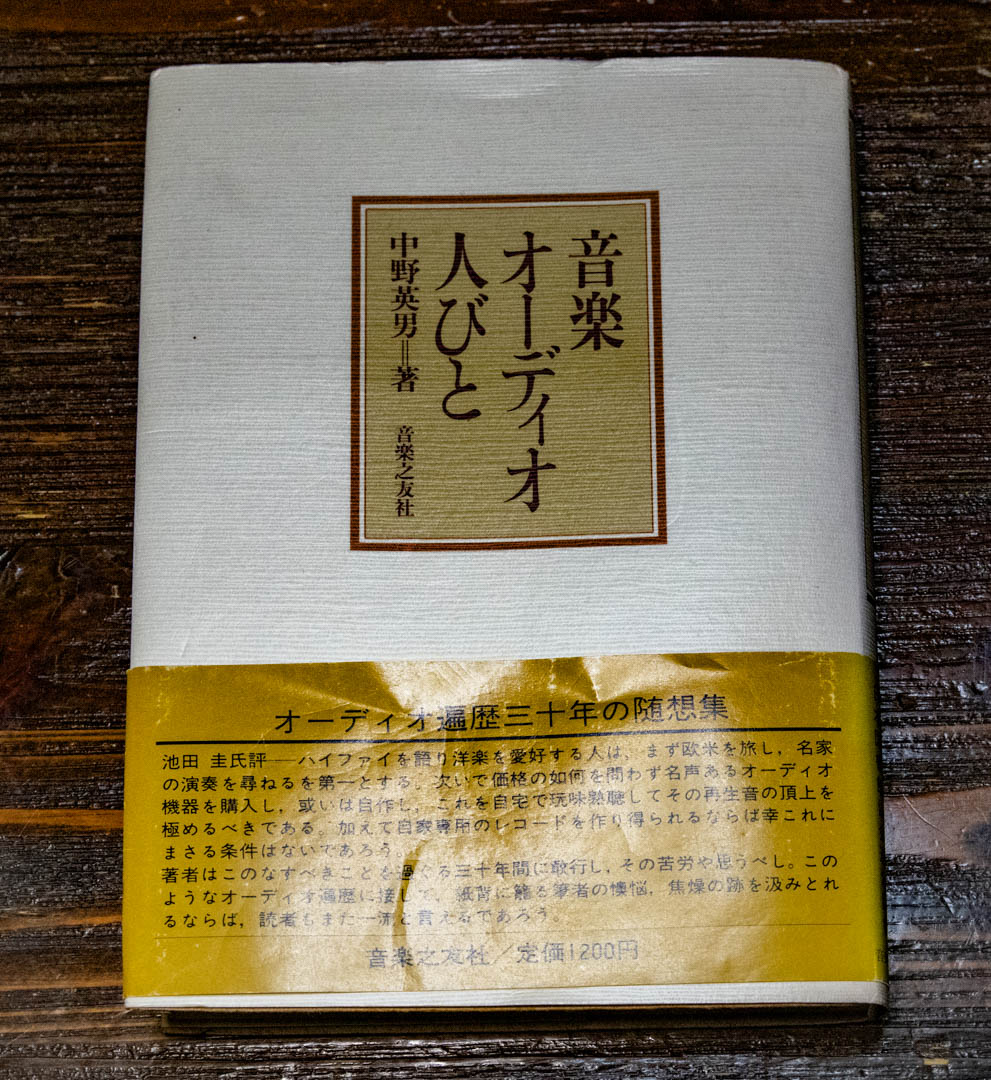立花隆氏が亡くなられたそうですがお悔やみを申し上げます。私は氏をジャーナリストとしては優れた業績を挙げたと評価しますが、「知の巨人」などとはまるで思いません。「知の巨人」という呼び方に値するような、どんな学問的業績を氏は残されたのでしょうか。氏の著作リストを見る限り、どこにもそんなものはありそうにありません。要するに出版社が本を売るためのキャッチコピーに過ぎないと思います。
以下は、私が2004年に氏の本に対してAmazonでレビューしたものですが、この本などは本当にひどい内容でした。かなりネガティブなレビューにも関わらず、64人も「役に立った」としています。私と同様立花隆氏の「学問的」業績には眉唾な人が多いのだと思います。
「ぼくが読んだ面白い本・ダメな本 そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術」
5つ星のうち2.0
ファーストフードとしての読書
2004年4月28日に日本でレビュー済み
立花隆氏が、なぜあのような内容のない見当外れの書評やエッセイをばらまくのか、その秘密がわかる本である。要は氏は書籍をファーストフードとしてひたすら大量に「消費」し続けているだけである。その結果、栄養は偏ってどうでもよい些末な知識のゴミだけがグロテスクに肥大化し、本質を見通すべき眼力は磨かれることなく、むしろ日々失われていく、といった惨憺たる状況に陥っている。であるのに本人には自覚症状がなく、却ってそれを声高に自賛するという倒錯に陥っている、そういう本です。私は途中で読むのをやめてゴミ箱に捨てました。
64人のお客様がこれが役に立ったと考えています