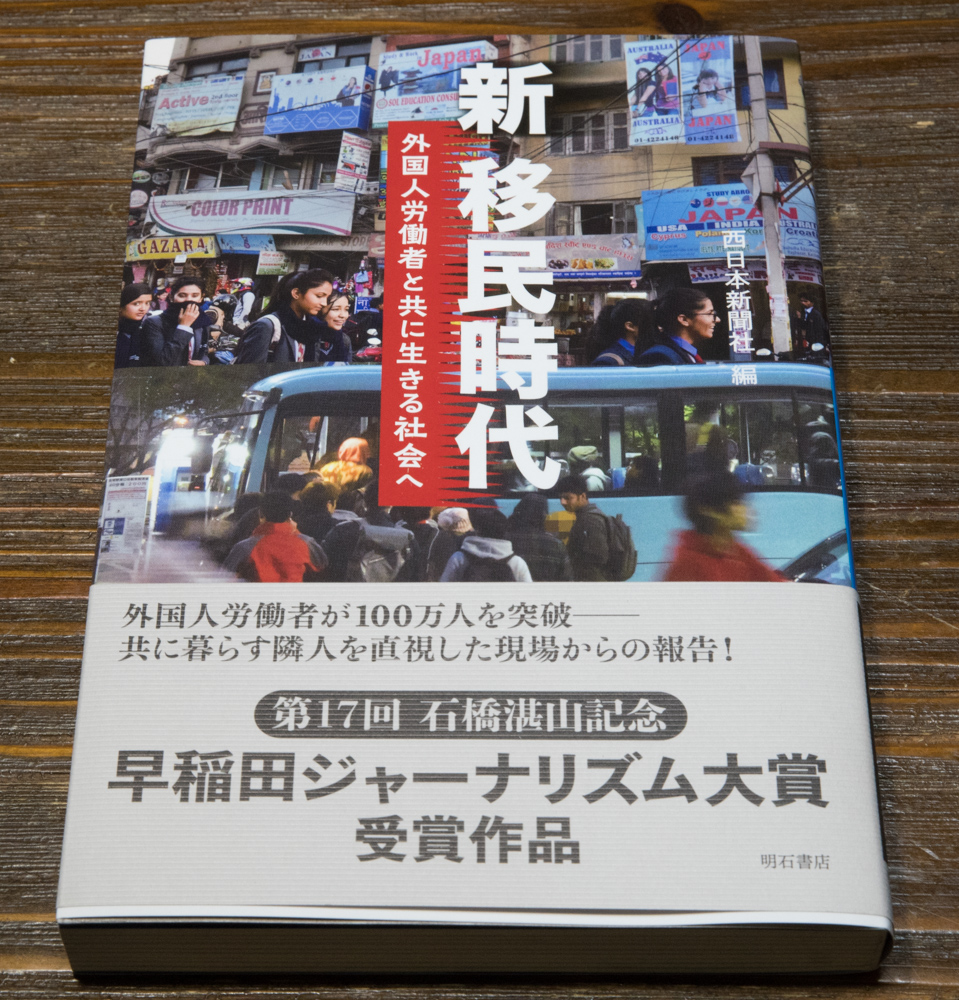 西日本新聞社 編「新 移民時代 外国人労働者と共に生きる社会へ」を読了。移民問題について、3冊目でやっと良書に出会いました。この本の内容は西日本新聞という福岡の地方新聞に連載されたものです。まずは何より取材に手間を惜しまず、時にはネパールやタイにまで出かけて関係者に取材してまとめた労作です。最近マスコミがフェイクニュースを垂れ流すものとして批判されますが、こういう地道ないい仕事を、全国新聞ではなく地方新聞がやっていることに救いを感じました。福岡という場所、九州という場所は、よく考えれば昔から海外の文化の取り入れで日本の最前線にあった所だと思います。またある意味「よそ者」に寛容な土地柄で、私も小学6年の時に山口県から福岡県に引っ越した経験がありますから、余計にそう思います。
西日本新聞社 編「新 移民時代 外国人労働者と共に生きる社会へ」を読了。移民問題について、3冊目でやっと良書に出会いました。この本の内容は西日本新聞という福岡の地方新聞に連載されたものです。まずは何より取材に手間を惜しまず、時にはネパールやタイにまで出かけて関係者に取材してまとめた労作です。最近マスコミがフェイクニュースを垂れ流すものとして批判されますが、こういう地道ないい仕事を、全国新聞ではなく地方新聞がやっていることに救いを感じました。福岡という場所、九州という場所は、よく考えれば昔から海外の文化の取り入れで日本の最前線にあった所だと思います。またある意味「よそ者」に寛容な土地柄で、私も小学6年の時に山口県から福岡県に引っ越した経験がありますから、余計にそう思います。
内容については、この本で暴かれているのは、日本の政策の建前と本音の使い分けのひどさ。表では移民政策を否定しておいて、裏では留学生や研修生の名前で外国人の安い労働力を搾取する構図というのが見えて憤りを感じざるを得ません。ネパールから来た留学生が、ほとんど睡眠時間を取らずにいくつもバイトを掛け持ちし、結局精神を病んだり、失踪したりという悲劇が語られています。「女工哀史」は明治時代だけの話ではありません。また色々と識者に話を聴いている中でひどかったのが、連合の副事務長の安永とか言うの。自分達の既得権益が侵される心配ばかりして、人口減というある意味日本の危機を無視してはっきりいって何も考えていません。その逆に、自民党の石破茂氏については、意外なことに移民推進派であり、「移民庁」という官庁を作ってはどうかと提言しています。ちょっと見直しました。
この問題については、更に色々調べていきたいと思います。
カテゴリー: Book
毛受敏浩の「自治体がひらく日本の移民政策 人口減少時代の多文化共生への挑戦」
 毛受敏浩の「自治体がひらく日本の移民政策 人口減少時代の多文化共生への挑戦」を読了。かなり飛ばし読み。この本は「外国人労働者受け入れを問う」よりはましな内容と思いますが、正直な所、「多文化共生」といういわばきれい事を強調し過ぎと思います。どのような事にもポジティブな面とネガティブな面がありますが、この本はポジティブな事を中心にかかれており、ネガティブな懸念みたいなことに対しては、きわめて通り一遍の説明しか与えられていません。たとえば「移民が増えれば犯罪が増えるのではないか」という懸念に対しては、近年の外国人による犯罪が減少しているから問題ない、といったレベルで片付けられてしまいます。しかし、本格的に移民を受け入れ、外国人の永住者が今の10倍になった時に、果たしてその説明で、反対者を説得できるかというと、きわめて疑問です。
毛受敏浩の「自治体がひらく日本の移民政策 人口減少時代の多文化共生への挑戦」を読了。かなり飛ばし読み。この本は「外国人労働者受け入れを問う」よりはましな内容と思いますが、正直な所、「多文化共生」といういわばきれい事を強調し過ぎと思います。どのような事にもポジティブな面とネガティブな面がありますが、この本はポジティブな事を中心にかかれており、ネガティブな懸念みたいなことに対しては、きわめて通り一遍の説明しか与えられていません。たとえば「移民が増えれば犯罪が増えるのではないか」という懸念に対しては、近年の外国人による犯罪が減少しているから問題ない、といったレベルで片付けられてしまいます。しかし、本格的に移民を受け入れ、外国人の永住者が今の10倍になった時に、果たしてその説明で、反対者を説得できるかというと、きわめて疑問です。
ただ、この本で良かったのは、国の移民政策の立案がほとんどされていない一方で、都市部よりもいち早く深刻な人口減少に直面している地方都市のいくつかが、外国人受け入れを真剣に検討し始めているというのがわかったことです。例として沖縄県や浜松市、あるいは北海道のいくつかの都市が挙げられます。
しかし、二冊読んでも相変わらず私が知りたいことを十分に知ることは出来ませんでした。
宮島喬、鈴木江理子の「外国人労働者受け入れを問う」
 宮島喬、鈴木江理子の「外国人労働者受け入れを問う」を読了。人口が減少していく日本の対策としては、移民の積極的な受け入れを考えるべきで、それに向けての予想される諸問題をオープンに議論していく必要があると思いますが、残念ながら今の政治家にそういう気概のある人は見当たりません。ちょっとこの問題を自分で考えようと思って、2冊買った本の1冊がこの本。残念ながら本自体薄いですが、中身も薄かったです。大体「移民の是非を問う」ではなく、何故「外国人労働者受け入れを問う」なのか。タイトルからは、これまで日本政府が進めてきた、表ドアは閉じておいて、都合の良い時だけ期間を限定して外国人を労働者として使う、という発想しか見えてきません。私は日本のあらゆる産業がガラパゴス化している今、外国から人を受け入れ、日本文化の多様化を図る「第二の開国」が必要と思います。
宮島喬、鈴木江理子の「外国人労働者受け入れを問う」を読了。人口が減少していく日本の対策としては、移民の積極的な受け入れを考えるべきで、それに向けての予想される諸問題をオープンに議論していく必要があると思いますが、残念ながら今の政治家にそういう気概のある人は見当たりません。ちょっとこの問題を自分で考えようと思って、2冊買った本の1冊がこの本。残念ながら本自体薄いですが、中身も薄かったです。大体「移民の是非を問う」ではなく、何故「外国人労働者受け入れを問う」なのか。タイトルからは、これまで日本政府が進めてきた、表ドアは閉じておいて、都合の良い時だけ期間を限定して外国人を労働者として使う、という発想しか見えてきません。私は日本のあらゆる産業がガラパゴス化している今、外国から人を受け入れ、日本文化の多様化を図る「第二の開国」が必要と思います。
ロバート・L・フォワードの「竜の卵」
 ロバート・L・フォワードの「竜の卵」を読了。ハードSFとして、お友達のKさんのお勧めによるもの。感謝。前半ちょっとかったるい部分はありましたが、通して読んでみるとなかなかの作品と思いました。まず、表面の温度が8000℃、そして重力が地球の370億倍という、中性子星(パルサー)上に生物が発生しているという設定がすごいです。解説によると先行作品としてハル・クレメントの「重力の使命」があり、また1970年代に、パルサー上の生物の可能性は科学者の間で指摘されていたそうですが、しかしそれを実際に書くのはかなりの難度だと思います。フォワードはそれを見事にやり遂げています。また、いわゆる異星人とのファーストコンタクト物なのですが、パルサー上の生物であるチラーが人間より100万倍の時間感覚で生きているという設定が秀逸です。このために、コンタクト当初は遅れていたチラーが人間側が与えた情報を元に、人間時間でほんの数日の内にあっという間に人間を追い越してしまいます。ただ、マイナーな欠陥を指摘すると、たとえばチラーの姿形に関する描写が曖昧で、今一つ文章だけでその姿を具体的に思い浮かべることがうまくできなかったことです。もっともナメクジみたいなものかという予想は大体あたっていましたけど。「デューン」もそうだったですけど、本文だけで語りきれないで、巻末のおまけで解説するというのは、どうも私にはフェアではないように思えます。また、イエスキリストを思わせるような予言者が登場して、民衆に殺害されますが、このお話は全体の中では取って付けたような印象を受けます。そうは言っても、1960年代初めに生まれた私は、子供の頃色んなアニメとか漫画で(当時は平井和正、辻真先、豊田有恒、眉村卓、そして筒井康隆に至るまでの若いSF作家が黎明期のSF設定のアニメに台本を提供していました)、「科学技術の進歩による明るい先進的な未来」というのを刷り込まれているせいか、こうしたちゃんとしたSFを読むとちょっと安心します。
ロバート・L・フォワードの「竜の卵」を読了。ハードSFとして、お友達のKさんのお勧めによるもの。感謝。前半ちょっとかったるい部分はありましたが、通して読んでみるとなかなかの作品と思いました。まず、表面の温度が8000℃、そして重力が地球の370億倍という、中性子星(パルサー)上に生物が発生しているという設定がすごいです。解説によると先行作品としてハル・クレメントの「重力の使命」があり、また1970年代に、パルサー上の生物の可能性は科学者の間で指摘されていたそうですが、しかしそれを実際に書くのはかなりの難度だと思います。フォワードはそれを見事にやり遂げています。また、いわゆる異星人とのファーストコンタクト物なのですが、パルサー上の生物であるチラーが人間より100万倍の時間感覚で生きているという設定が秀逸です。このために、コンタクト当初は遅れていたチラーが人間側が与えた情報を元に、人間時間でほんの数日の内にあっという間に人間を追い越してしまいます。ただ、マイナーな欠陥を指摘すると、たとえばチラーの姿形に関する描写が曖昧で、今一つ文章だけでその姿を具体的に思い浮かべることがうまくできなかったことです。もっともナメクジみたいなものかという予想は大体あたっていましたけど。「デューン」もそうだったですけど、本文だけで語りきれないで、巻末のおまけで解説するというのは、どうも私にはフェアではないように思えます。また、イエスキリストを思わせるような予言者が登場して、民衆に殺害されますが、このお話は全体の中では取って付けたような印象を受けます。そうは言っても、1960年代初めに生まれた私は、子供の頃色んなアニメとか漫画で(当時は平井和正、辻真先、豊田有恒、眉村卓、そして筒井康隆に至るまでの若いSF作家が黎明期のSF設定のアニメに台本を提供していました)、「科学技術の進歩による明るい先進的な未来」というのを刷り込まれているせいか、こうしたちゃんとしたSFを読むとちょっと安心します。
ディケンズの「クリスマス・キャロル」
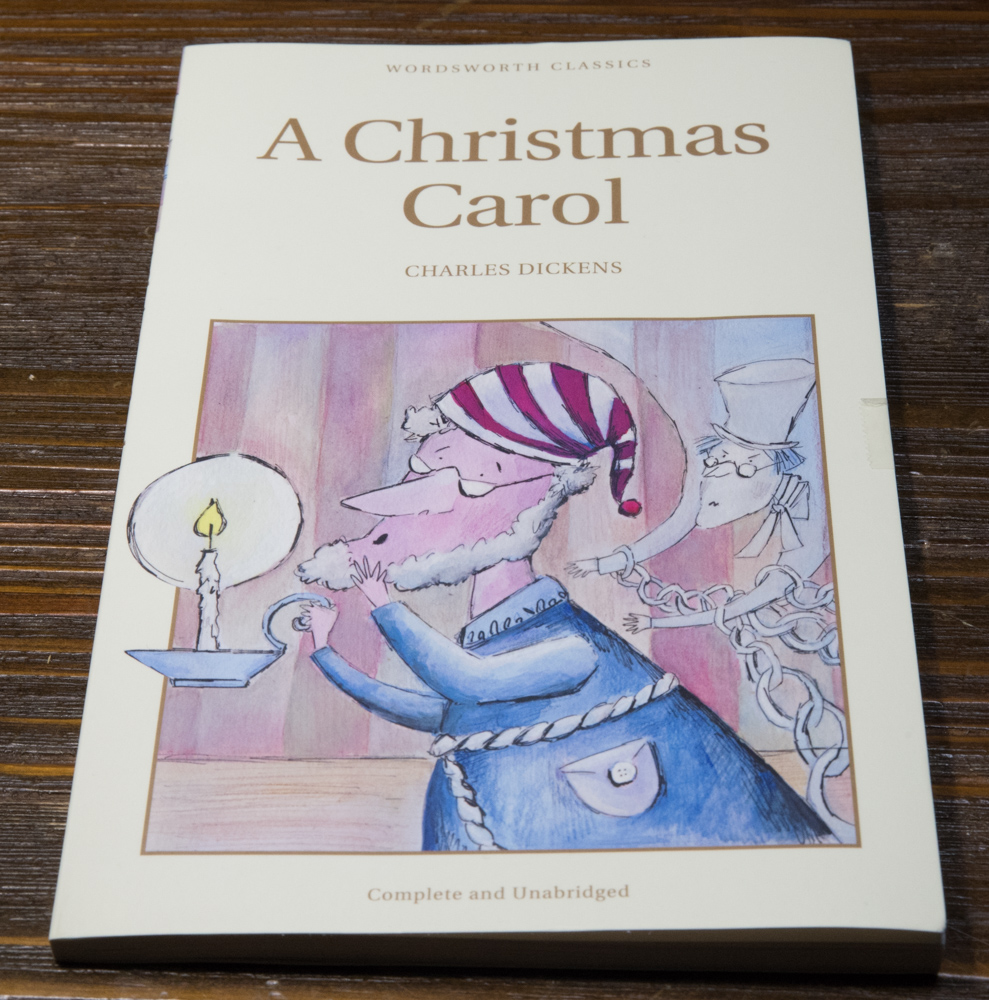 ディケンズの「クリスマス・キャロル」を「英語で」読了。このお話のラジオドラマ(英語)を、高校の時英語の授業で使って、懐かしかったので改めて英語で読んでみたものです。よく知られた小説で、ストーリーも分かっているし、そんなに難しくないだろう、と思っていましたが、実際には知らない単語だらけで、結構苦労しました。それでもストーリーは分かっているので知らない単語を一つ一つ辞書で引いたりはせずに読み進めました。この小説が書かれたのは1843年で、日本で言えば天保年間の最後の年です。さすがにこれだけ昔の本だと今の英語とはそもそも語彙自体が違うように思います。後読んでいて感じたのは、結構韻を踏むような文章も出てくることでした。
ディケンズの「クリスマス・キャロル」を「英語で」読了。このお話のラジオドラマ(英語)を、高校の時英語の授業で使って、懐かしかったので改めて英語で読んでみたものです。よく知られた小説で、ストーリーも分かっているし、そんなに難しくないだろう、と思っていましたが、実際には知らない単語だらけで、結構苦労しました。それでもストーリーは分かっているので知らない単語を一つ一つ辞書で引いたりはせずに読み進めました。この小説が書かれたのは1843年で、日本で言えば天保年間の最後の年です。さすがにこれだけ昔の本だと今の英語とはそもそも語彙自体が違うように思います。後読んでいて感じたのは、結構韻を踏むような文章も出てくることでした。
この物語に出てくる、ボブ・クラチットの末の息子で、足の不自由なTiny Tim(これも韻を踏んでます)が、私は好きで、スクルージ爺さんが改心して、ボブの一家を助けてTiny Timを死の運命から救い、Tiny Timの第2の父のような存在になる、というお話が好きです。
Erin Meyerの”The culture map”
 Erin Meyerの”The culture map”を読了。(日本語訳は、「異文化理解力」)
Erin Meyerの”The culture map”を読了。(日本語訳は、「異文化理解力」)
エリン・メイヤーは、フランスとシンガポールに拠点を置くビジネススクールであるINSEAD客員教授です。この本を知ったきっかけは、English Journalにエリン・メイヤーのインタビュー記事が載っていたことです。そのインタビューで、メイヤーが日本の企業について、日本はこの上ない階層社会だけど、決定プロセスは合議とコンセンサスに基づくもの(つまり稟議システムのこと)、そこで決定されたものはDecision(Big-D)でなまじ皆で時間をかけて決めたため、一度決まるとフレキシブルに変更することが難しい。一方でアメリカはフラットな平等主義の社会だけど、企業の決定プロセスはトップダウンで上から降ってくる。しかしそこで決まったものはdecision(small-D)で一度決めても状況が変わればすぐ変更される。といった内容に興味を覚えてこの本を買ってみたものです。
メイヤーは色々な国のビジネス文化を評価・比較するために8つのスケールを持ち出します。
1.コミュニケーションのやり方-簡単で直接的なコミュニケーションを良しとするか、高度な文脈を持った含蓄のある(けどわかりにくい)コミュニケーションが一般的であるか。
2.人の評価方法-ネガティブな評価をダイレクトに伝えるか、遠回しに伝えるか。
3.説得の仕方-原理原則で相手を説得するか(演繹的)、具体的な事実・意見を先に行って説得するか(帰納的)。
4.リーダシップのあり方-平等主義的なリーダーシップか階層的・権威的なリーダーシップか。
5.企業での決定方法-全員のコンセンサスを重視するか、トップダウンでの決定か。
6.人への信頼-あくまでビジネスライクか、個人としての付き合いをビジネスでも重視するか。
7.意見が違う時-対立的か、それとも全体の和を重視するか。
8.時間感覚-きちんとスケジュール化してそれに従うか、成り行きに任せてフレキシブルに対応するか。
日本については、
(1)この上ない程、高度な文脈を持ったコミュニケーション(空気を読む、忖度)
(2)ネガティブな評価はオブラートにくるんで直接的な非難の表現をほとんど使わない
(3)具体的な事実・意見を重視した説得プロセス、原理原則から論じない
(4)かなりの部分階層的で平等主義ではない
(5)コンセンサスを世界でもっとも重んじる
(6)仕事に割切った人間関係というより個人での関係をかなり重視する
(7)ともかく対立を忌み嫌うことでは最右翼
(8)かなり時間に几帳面で正確
となっています。
この本を批判するとすれば、(1)この8つの尺度を持ち出すのが適当であるかどうか(2)その尺度に従った各国の評価がどの程度当てはまっていて、またその国全体に一般化してOKかどうか、という点で可能と思います。私の意見では(1)についてはこの8つはかなりいい線を行っていて、実際にビジネスを行っていく上で非常に重要な尺度が良く集められていると思います。(2)については、個別の会社ではそれぞれ文化が違いますし、過度な一般化は危険なようにも思いますが、ある程度は参考になる評価だと思います。細かく見ると、8.の時間感覚で、ドイツの方が日本より時間にシビアで正確となっているのはまったく納得できませんが。(ドイツに行ってドイツの鉄道の運行時間の適当さにはうんざりしましたから。)また、日本の「コンセンサスを重んじる」ってのは、ちょっと稟議制だけを見た表面的な見方のようにも思います。
ともかく、中にちりばめられた具体的な文化の違いによるビジネス上のトラブルがとても面白く参考になります。たとえば欧州の人とアジアの人を集めたチームで、最初懸念された「欧州人対アジア人」ではなく、実は「中国人対日本人」の対立が一番問題になったとか。(8つの尺度で比較すると、中国と日本は実は同じアジアの国でありながらかなり違います。)国際的なビジネスに携わる人にとっては、ある意味必読の本と思います。
なお、オリジナルの英語版で読みましたが、辞書を引かなければならないのは1ページ辺り1~2回のレベルであり、Newsweekの記事なんかに比べるとはるかに読みやすいです。
豊田有恒の「『宇宙戦艦ヤマト』の真実 ---いかに誕生し、進化したか」
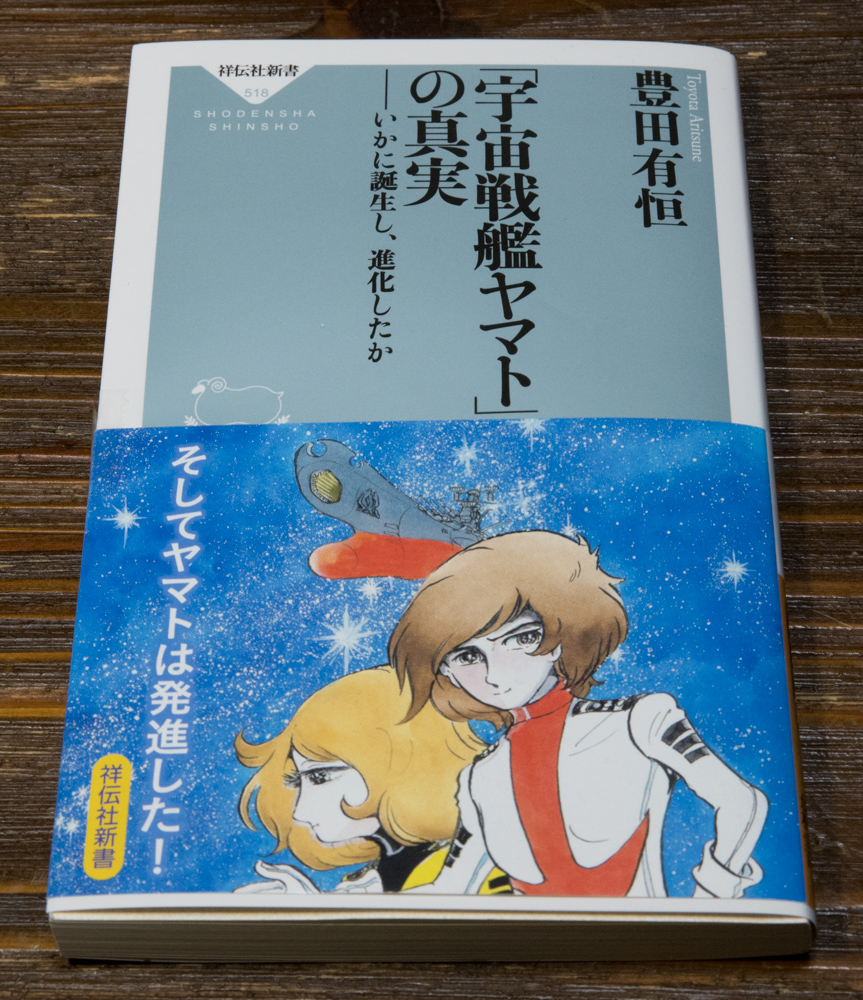 豊田有恒の「『宇宙戦艦ヤマト』の真実 ---いかに誕生し、進化したか」を読了。豊田が「宇宙戦艦ヤマト」についてある大新聞からインタビューを受けたけど、その大新聞が内容をねじ曲げ、無理矢理に「ヤマトではガミラスに敗北寸前の地球が太平洋戦争での日本の姿に重ねられている」という勝手な解釈で記事を書かれたことに憤激して、「宇宙戦艦ヤマト」の誕生の背景を当時者として改めて語っているものです。(その大新聞の名前は書いてありませんが、誰が読んでも朝日新聞だろうと推測がつきます。)個人的には、前半の日本のアニメの創生期の話が興味深くて、エイトマンが生まれる背景などが楽しく読めました。「ヤマト」については、西崎義展との関わりが必然的に多くなります。豊田は西崎がいなかったらヤマトは出来ていなかったとその功績を認めながら、しかし西崎にはクリエイターとしての才能はなく、その一方で多くのクリエイターをただみたいな安いお金でこき使ったとして強く非難しています。なんと松本零士にさえ、ろくなお金を払っていなかったようです。これは西崎一人の罪というより、日本で多く見られる「知的作業にお金を払わない」という悪しき慣習と深くつながっていると思います。豊田によれば、作品が一律に「コンテンツ」と呼ばれるようになってから、この傾向がさらにひどくなったとしています。
豊田有恒の「『宇宙戦艦ヤマト』の真実 ---いかに誕生し、進化したか」を読了。豊田が「宇宙戦艦ヤマト」についてある大新聞からインタビューを受けたけど、その大新聞が内容をねじ曲げ、無理矢理に「ヤマトではガミラスに敗北寸前の地球が太平洋戦争での日本の姿に重ねられている」という勝手な解釈で記事を書かれたことに憤激して、「宇宙戦艦ヤマト」の誕生の背景を当時者として改めて語っているものです。(その大新聞の名前は書いてありませんが、誰が読んでも朝日新聞だろうと推測がつきます。)個人的には、前半の日本のアニメの創生期の話が興味深くて、エイトマンが生まれる背景などが楽しく読めました。「ヤマト」については、西崎義展との関わりが必然的に多くなります。豊田は西崎がいなかったらヤマトは出来ていなかったとその功績を認めながら、しかし西崎にはクリエイターとしての才能はなく、その一方で多くのクリエイターをただみたいな安いお金でこき使ったとして強く非難しています。なんと松本零士にさえ、ろくなお金を払っていなかったようです。これは西崎一人の罪というより、日本で多く見られる「知的作業にお金を払わない」という悪しき慣習と深くつながっていると思います。豊田によれば、作品が一律に「コンテンツ」と呼ばれるようになってから、この傾向がさらにひどくなったとしています。
豊田のヤマトの最初の設定で面白いのは、イスカンダルにコスモクリーナーを取りに行くというのの元ネタは何と西遊記だということです。さすがにそれは気がついていませんでした。(西遊記をベースにしたアニメには、同じく松本零士原作の「SF西遊記スタージンガー」があります。)また、初期の設定はかなりダークでハードなもので、その設定が2010年のキムタク主演の実写版で一部使われていました。
英語学習雑誌2誌の比較-CNN English ExpressとEnglish Journal
 2018年3月で、購読歴丸4年になる2つの英語雑誌の比較。「CNN English Express」と「English Journal」。この2つはたぶんライバル誌となりますが、内容はかなり違います。価格はCNNの方が税込み1,240円、EJの方が1,512円でEJの方が高いです。
2018年3月で、購読歴丸4年になる2つの英語雑誌の比較。「CNN English Express」と「English Journal」。この2つはたぶんライバル誌となりますが、内容はかなり違います。価格はCNNの方が税込み1,240円、EJの方が1,512円でEJの方が高いです。
1.CNN English Express
朝日出版社から出ているもの。名前の通り、CNNのニュースが満載でそれが主要コンテンツです。それも短いニュース(10本+2本くらい)、ちょっとまとまったニュース(4本くらい)、ニュースショー(アンダーソン・クーパー360°)とバラエティーに富んでいます。ただ、雑誌に掲載されるのは大体1~2ヵ月前のニュースで時間差があります。ニュースの元もアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアと色々でそれぞれの国のアナウンサーがしゃべっており(2回読まれて最初がオリジナル、2回目がアメリカ人かカナダ人になりますから、発音を比較する上でも有益)、TOEICでのリスニングがこの4ヵ国ですから、TOEICリスニング対策として有益です。また、長いニュース1本について、通常のスピードと1.5倍速のスピードがあり、これも聴き取り強化に有益です。ニュース以外に、インタビュー記事がありますが、これは月に2本ぐらいでEJに比べるとちょっとだけ劣ります。その他連載が何本かありますが、一回連載が始まるとかなり長く続き、今やっている科学評論家のクリストファー・ロイドの記事は2018年1月号でもう34回目です。添付されているCDの収録時間は毎回きちんと65分ぐらいで安定しています。これはEJに比べるとしっかりしていて学習計画が立てやすいです。
2.English Jounal
英語教材で定評があるアルクから出ているもの。この雑誌の売りはなんといってもインタビュー記事で、毎月3本くらい。それもその中には毎月かなりの有名人が含まれており、たとえば2018年1月号ではレディー・ガガが登場します。過去にはジョン・レノンの昔のインタビューとか、ブラッド・ピットなんかも登場しました。大体新しい映画が封切られるとその主演男優・女優が登場することが多いので、洋画好きの人にはいいと思います。(まあそのせいで価格がCNNより高いのでしょうが。)芸能人以外にも、学者系が結構登場し、なかなか面白いことをしゃべっていることがあります。最近著作を読んだエリン・メイヤーはこのEJのインタビューで初めて知りました。インタビュー以外の連載記事としては、アメリカの作家ケイ・へザリのエッセイ(これはなかなかいいです)とか、クイック・チャットという日本に在住している外国人同士の雑談(普通)、またミステリー・スピーカーという正体が隠されたキャラクターがしゃべってその正体を当てるクイズ(これはその正体が最近はスモッグだとか駐車場だとかダムのような訳の分からない物が多くなってイマイチ)があります。この雑誌の問題点は、それ以外の特集記事のばらつきが極めて激しいことです。その特集記事の長さによって、毎月のCDの収録時間がかなり大幅にぶれ、短い時は50分程度、長いときは80分とCDの収録時間の限界に近いものもあり、毎月の学習計画を大幅に狂わせてくれて、非常にやりにくいです。また、最近始まった「英語でヨガ」というのも意味不明の企画で、出てくる単語はinhale(息を吸う)、exhale(息を吐く)みたいなのの繰り返しで、英語の教材としてはあまり価値がありません。(私はいつも聴かないで飛ばしています。)全体的に編集方針がはっきりしていなくてあっちへ行ったりこっちへ行ったりしています。
もし、どちらか1冊だけというのであれば、価格的にも安いCNN English Expressの方をお勧めします。もちろん経済的に余裕があるなら両方を購読する方が、英語のバラエティーという意味では広がります。
ただもちろんこの2つの雑誌だけで十分という事ではなく、例えば”panting”(荒い息をしている状態)という単語はドラマを見ていれば良く出てきますが(セリフではなく英語の字幕の説明で)、この2つの雑誌で登場したのを一度も聞いたことがありません。英語のレベルが上がる程、色々な英語にチャレンジし、媒体を拡げた方がいいと思います。
山室恭子の「歴史小説の懐」
 山室恭子の「歴史小説の懐」を読了。この人は白井喬二のちくま文庫版の「富士に立つ影」の第6巻「帰来篇」で見事な解説を書いていた人で、他に大衆小説に関する評論は無いかとAmazonで検索してみて見つけたものです。この方、本業は日本の中世専門の歴史学者です。その本業の影響もあって、時代小説をまるで歴史資料みたいに扱っていて、各小説のまず詳細なストーリー内の年表を作って、色んな矛盾を発見しています。その矛盾の最たるものが「大菩薩峠」です。この小説が1867年の秋で時間が進まなくなるのは知っていましたが、それが実は全体の1/4しか進んでいない第5巻でもうその時に達してしまうのだということは、この本で初めて知りました。また大菩薩峠で主人公の机龍之助と関わる女性が「お浜」(白浜)、「お銀」(白銀)、「お雪ちゃん」とすべて「白」を基調にしている、つまり色が欠けている、それだけではなく実は「大菩薩峠」は「何かが欠如している」ことを特徴とする、という指摘は実に鋭いと思います。
山室恭子の「歴史小説の懐」を読了。この人は白井喬二のちくま文庫版の「富士に立つ影」の第6巻「帰来篇」で見事な解説を書いていた人で、他に大衆小説に関する評論は無いかとAmazonで検索してみて見つけたものです。この方、本業は日本の中世専門の歴史学者です。その本業の影響もあって、時代小説をまるで歴史資料みたいに扱っていて、各小説のまず詳細なストーリー内の年表を作って、色んな矛盾を発見しています。その矛盾の最たるものが「大菩薩峠」です。この小説が1867年の秋で時間が進まなくなるのは知っていましたが、それが実は全体の1/4しか進んでいない第5巻でもうその時に達してしまうのだということは、この本で初めて知りました。また大菩薩峠で主人公の机龍之助と関わる女性が「お浜」(白浜)、「お銀」(白銀)、「お雪ちゃん」とすべて「白」を基調にしている、つまり色が欠けている、それだけではなく実は「大菩薩峠」は「何かが欠如している」ことを特徴とする、という指摘は実に鋭いと思います。
それはいいんですが、後半の方になるとかなり脱線気味で、平岩弓枝の「御宿かわせみ」の「かわせみ」の宿が実はパラレルワールドで2軒存在するのだとか、池波正太郎の「鬼平犯科帳」で平蔵に可愛がられた野良犬が突如姿を消した後、「御宿かわせみ」に別の名前の犬として登場する、などという説は、かなり妄想が入っていて、表面的な辻褄を合わせるために、学者が珍説をひねり出すという感じを受けました。
そうはいっても、なかなか面白い指摘をたくさん含む本で、時代小説ファンにはお勧めします。
イリーナ・メジューエワの「ピアノの名曲 聴きどころ 弾きどころ」
 イリーナ・メジューエワの「ピアノの名曲 聴きどころ 弾きどころ」を読了。メジューエワと対談した人が聴き取ってまとめたものです。素晴らしい本で、全てのクラシック音楽を愛する人、またピアノを弾く人にお勧めします。メジューエワはその演奏を聴くと、感受性と知性がかなりの高いレベルで融合した人、という印象を受けるのですが、その印象はこの本によって更に強固になりました。こういう本が出ると、大抵の音楽評論家の本は不要になるのではないかと思います。ピアニストが曲を取り上げるにあたってここまで深く色々なことを考えているということが新鮮で感動的です。取り上げられている作曲家は、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ショパン、リスト、ドビュッシー、そしてラヴェルです。バッハの「ゴールドベルク変奏曲」の中に「数」へのこだわりがあるとか、ベートーヴェンのピアノ・ソナタは弦楽四重奏曲の様式で書かれているとか、シューベルトこそ本当の古典派であるとか、ともかく目から鱗が落ちるような指摘に満ちています。また、メジューエワのお勧めの演奏(本人以外の)が載っているもなかなか楽しく、シュナーベルとかコルトーが多く登場します。個人的には、シューマンのクライスレリアーナとラヴェルの「夜のガスパール」についてはアルゲリッチを外して欲しくないのですが、ライバル意識があるのか(?)一度も登場しません。一方で私が好きなアファナシエフは何度か登場します。しかし、この本を読んで、いわゆる「ロシア・ピアニズム」というものが、ネイガウスやソフロニツキーが亡くなってかなりの時間が経った今でも、このメジューエワの中にしっかり生きているだなと思いました。
イリーナ・メジューエワの「ピアノの名曲 聴きどころ 弾きどころ」を読了。メジューエワと対談した人が聴き取ってまとめたものです。素晴らしい本で、全てのクラシック音楽を愛する人、またピアノを弾く人にお勧めします。メジューエワはその演奏を聴くと、感受性と知性がかなりの高いレベルで融合した人、という印象を受けるのですが、その印象はこの本によって更に強固になりました。こういう本が出ると、大抵の音楽評論家の本は不要になるのではないかと思います。ピアニストが曲を取り上げるにあたってここまで深く色々なことを考えているということが新鮮で感動的です。取り上げられている作曲家は、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ショパン、リスト、ドビュッシー、そしてラヴェルです。バッハの「ゴールドベルク変奏曲」の中に「数」へのこだわりがあるとか、ベートーヴェンのピアノ・ソナタは弦楽四重奏曲の様式で書かれているとか、シューベルトこそ本当の古典派であるとか、ともかく目から鱗が落ちるような指摘に満ちています。また、メジューエワのお勧めの演奏(本人以外の)が載っているもなかなか楽しく、シュナーベルとかコルトーが多く登場します。個人的には、シューマンのクライスレリアーナとラヴェルの「夜のガスパール」についてはアルゲリッチを外して欲しくないのですが、ライバル意識があるのか(?)一度も登場しません。一方で私が好きなアファナシエフは何度か登場します。しかし、この本を読んで、いわゆる「ロシア・ピアニズム」というものが、ネイガウスやソフロニツキーが亡くなってかなりの時間が経った今でも、このメジューエワの中にしっかり生きているだなと思いました。
