 藤原正彦の「国家と教養」を読みました。藤原正彦の本については、大体読まなくても内容を想像出来るので魅力を感じないのですが、この本については大衆小説の価値を強調しているという点に興味をもって読んでみました。しかしその点に関しては確かに立川文庫(たつかわぶんこ)などが出てきますが、中里介山も白井喬二も出てきません。もしこの筆者が「大菩薩峠」も「富士に立つ影」も読んだことないのであれば、そういう人に大衆小説がどうの、と言って欲しくないです。
藤原正彦の「国家と教養」を読みました。藤原正彦の本については、大体読まなくても内容を想像出来るので魅力を感じないのですが、この本については大衆小説の価値を強調しているという点に興味をもって読んでみました。しかしその点に関しては確かに立川文庫(たつかわぶんこ)などが出てきますが、中里介山も白井喬二も出てきません。もしこの筆者が「大菩薩峠」も「富士に立つ影」も読んだことないのであれば、そういう人に大衆小説がどうの、と言って欲しくないです。
私は「教養」学部「教養」学科という、ご丁寧に「教養」が2つも付く学科の出身なんで、「教養」の意義については、筆者に同意します。そういう意味で総論賛成ですが、各論ではいくつか異議があります。
一点目。マックス・ヴェーバーが「職業としての政治」で述べた内容がヒトラーの台頭につながったという主張。これはモムゼンという人が最初にそういう論旨でヴェーバーを批判して有名になったものですが、今ではヴェーバー学者でこの批判に賛同する人はほとんどいません。たとえて言えば、トランプみたいな大統領が出てきて無茶苦茶やっていますが、そのことについて大統領制というものを考えた人が責任を問われるべきでしょうか?それと同じだと思います。
二点目。イギリス人がバランス感覚に長けていて、EUからの離脱はその現れだという主張。まったくの噴飯ものと思います。私に言わせれば52:48の僅差でこのような大事なことが決まってしまうという事自体が、イギリス人が生み出した民主主義の欠陥だと思っています。多くの人が離脱に投票したことについて反省していて、今もう一度国民投票をやりなおせば残留派が6割くらいになると言われています。それを考えても離脱については多くの人が移民に対する嫌悪感などから衝動的な判断を行った結果であり、バランス感覚の現れだなどとはとても思えません。
批判ではありませんが、教養というより雑多な知識を得ることのメリットを私なりに挙げれば、それは「引き出し」を多く持つということで、何か新しいことを考え出したりするのは引き出しは多ければ多い程有利です。もう一つは今の学問の世界は細分化が行きすぎており、もう一度例えば社会科学だったら、法学・経済学・社会学などを統合した考え方が必要で(マックス・ヴェーバーなどはそれら全てをやっていました)、その基礎として教養が重要であるということです。
カテゴリー: Max Weber
折原浩先生の「東大闘争総括 戦後責任 ヴェーバー研究 現場実践」
 折原浩先生の「東大闘争総括 戦後責任 ヴェーバー研究 現場実践」を読了。(折原先生から戴いたもの。)シノドスというWeb雑誌での、北海道大学の橋本努氏の10項目に渡るインタビューが元になっています。折原先生のヴェーバー研究については、他にも色々書いたことがあるので、ここでは東大闘争総括に限定します。東大闘争が何だったのかということに関しては、曖昧な知識しか持っていませんでした。しかしこの本でかなりクリアーになり、全学連全体の70年安保反対という純政治的な闘争というより、医学部と文学部における不当な学生処分を巡る大学の自治に関する闘争、というのが本質のようです。この内医学部の処分に関しては、医学部出身の青医連が当時のインターン制度(今の就職予備活動のインターンとは違い、国家試験に合格した医者が一年間無給で特定の病院で研修を行う仕組み)に対する改革を呼びかけたのに対し、医学部当局がそれに関する立法化を盾に取って、運動に関わっていた医学部学生14人の大量処分を行ったというのがきっかけのようです。
折原浩先生の「東大闘争総括 戦後責任 ヴェーバー研究 現場実践」を読了。(折原先生から戴いたもの。)シノドスというWeb雑誌での、北海道大学の橋本努氏の10項目に渡るインタビューが元になっています。折原先生のヴェーバー研究については、他にも色々書いたことがあるので、ここでは東大闘争総括に限定します。東大闘争が何だったのかということに関しては、曖昧な知識しか持っていませんでした。しかしこの本でかなりクリアーになり、全学連全体の70年安保反対という純政治的な闘争というより、医学部と文学部における不当な学生処分を巡る大学の自治に関する闘争、というのが本質のようです。この内医学部の処分に関しては、医学部出身の青医連が当時のインターン制度(今の就職予備活動のインターンとは違い、国家試験に合格した医者が一年間無給で特定の病院で研修を行う仕組み)に対する改革を呼びかけたのに対し、医学部当局がそれに関する立法化を盾に取って、運動に関わっていた医学部学生14人の大量処分を行ったというのがきっかけのようです。
これに対し文学部処分の方は、学生と教授会の団交の場で、ある学生がある教授のネクタイを引っ張って暴言を浴びせたということを理由にして、その学生への処分が行われたものです。折原先生はこの文学部処分の方に深く関わり、社会科学的な事実分析を行い、この学生がある教授に手を出したのは、その教授が先にその学生に対し何かをやったからではないのか、という仮説を立てます。その仮説はあくまで仮説で100%検証されたものではありませんでしたが、状況的には明証性の高いものでした。色々とあって最終的には当時者二人の話し合いが実現し、事実はその教授がまずその学生を話し合いの行われた部屋から引きずり出そうとし、それに対してその学生が「何をするんだ」と反応した、ということになります。しかし文学部の処分はこの教授の先手を実は把握しておきながらその事実を伏せ、学生が一方的に悪いとして処分を強行したものでした。しかも、自分達が都合が悪くなり、学生達の騒ぎを抑えきれないと判断し、大学の自治を放棄した機動隊の導入という暴挙に出ます。
東大紛争と言うと、例の安田講堂のイメージで、学生側が全面的に敗退した、というイメージが強いのですが、実際は医学部処分も文学部処分もどちらも学生側の方が正しいことが判明し、両方の処分が撤回されています。
折原先生は学生の裁判の特別弁護人を引き受けて、大学側の虚偽と学問の府でありながら、まったく学問的ではない対応を繰り返した大学側を鋭く批判していきます。
今年は安田講堂事件から50年だそうで、再度あの「政治の季節」の意味を考え直すのにはいい機会だと思います。
マックス・ヴェーバーの「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」

 マックス・ヴェーバーの「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」を読了。松井秀親訳で、河出書房の「世界の大思想」の「ウェーバー宗教・社会論集」に収録されているもの。これも難解で二度読むことになりましたが、それでも内容を十分に理解することは現在の私の時間の使い方の中ではほぼ無理でした。この論考でも私が言う所の「ヴェーバー的倒錯」は発生するのであり、私はシュタムラーの「唯物史観による経済と法-社会哲学的一研究」を第一版も第二版もまるで読んでいません。ヴェーバーがこの論考でシュタムラーを激しく批判しているからといって、シュタムラーをロッシャーとクニースと同列扱いにするのは問題かと思います。少なくともシュタムラーの書籍は、それまでマルクスの一連の書籍をきちんと論じることが出来なかったブルジョア科学者の中で、初めてそれを行い、少なくともマルクス主義者の中にも修正主義者を生むくらいのインパクトを生んでいます。この論考は1907年に発表されたもので、ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の書かれた後です。ヴェーバーの「プロ倫」を読んで誰もが気付くことが、これは唯物論に対する強力な反証である、ということです。すなわち、全てが経済という土台に影響を受けた上で存在する、と主張する唯物論に対し、典型的な上部構造である宗教が逆に「資本主義」という「経済そのもの」が強く影響を受けている、という主張なのですから。シュタムラーもそういう意味では、唯物論に反論した先駆者の一人です。しかし、ほぼ同じような立ち位置にいながら、ヴェーバーはシュタムラーが唯物論で経済を全ての他の要素に先んじる基本要素としたのに対し、シュタムラーは今度は唯心論的に宗教その他を基本要素に置き換えただけで、なるほど唯物論を批判しているものの、その方法論は唯物論とまるで同じではないか、という批判を加えます。また、ヴェーバーは自身の「価値自由」的立場から、シュタムラーがSein(存在、あるもの)とSollen(当為、~すべきもの)の区別を混同していることを批判します。しかし、おそらくシュタムラーは「理想的な法体系」というものを信じているのであって、そこからすべての論理が出てくるのであって、それを批判するのは単なるヴェーバーとの立場の違いのように思います。それから、ヴェーバーのこの論考での主張は、かなりの部分が「経済と社会」の「法社会学」の冒頭での主張と重なっているように思います。すなわち、「ロッシャーとクニース」とこの論考は、批判そのものよりも、ヴェーバーが自身の理解社会学の方法論を確立していく上での踏み台として使われているように思います。
マックス・ヴェーバーの「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」を読了。松井秀親訳で、河出書房の「世界の大思想」の「ウェーバー宗教・社会論集」に収録されているもの。これも難解で二度読むことになりましたが、それでも内容を十分に理解することは現在の私の時間の使い方の中ではほぼ無理でした。この論考でも私が言う所の「ヴェーバー的倒錯」は発生するのであり、私はシュタムラーの「唯物史観による経済と法-社会哲学的一研究」を第一版も第二版もまるで読んでいません。ヴェーバーがこの論考でシュタムラーを激しく批判しているからといって、シュタムラーをロッシャーとクニースと同列扱いにするのは問題かと思います。少なくともシュタムラーの書籍は、それまでマルクスの一連の書籍をきちんと論じることが出来なかったブルジョア科学者の中で、初めてそれを行い、少なくともマルクス主義者の中にも修正主義者を生むくらいのインパクトを生んでいます。この論考は1907年に発表されたもので、ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の書かれた後です。ヴェーバーの「プロ倫」を読んで誰もが気付くことが、これは唯物論に対する強力な反証である、ということです。すなわち、全てが経済という土台に影響を受けた上で存在する、と主張する唯物論に対し、典型的な上部構造である宗教が逆に「資本主義」という「経済そのもの」が強く影響を受けている、という主張なのですから。シュタムラーもそういう意味では、唯物論に反論した先駆者の一人です。しかし、ほぼ同じような立ち位置にいながら、ヴェーバーはシュタムラーが唯物論で経済を全ての他の要素に先んじる基本要素としたのに対し、シュタムラーは今度は唯心論的に宗教その他を基本要素に置き換えただけで、なるほど唯物論を批判しているものの、その方法論は唯物論とまるで同じではないか、という批判を加えます。また、ヴェーバーは自身の「価値自由」的立場から、シュタムラーがSein(存在、あるもの)とSollen(当為、~すべきもの)の区別を混同していることを批判します。しかし、おそらくシュタムラーは「理想的な法体系」というものを信じているのであって、そこからすべての論理が出てくるのであって、それを批判するのは単なるヴェーバーとの立場の違いのように思います。それから、ヴェーバーのこの論考での主張は、かなりの部分が「経済と社会」の「法社会学」の冒頭での主張と重なっているように思います。すなわち、「ロッシャーとクニース」とこの論考は、批判そのものよりも、ヴェーバーが自身の理解社会学の方法論を確立していく上での踏み台として使われているように思います。
マックス・ヴェーバーの「ロッシャーとクニース」(松井秀親訳)
 マックス・ヴェーバーの「ロッシャーとクニース」(松井秀親訳)を読了しました。ヴェーバーの本は大体において難解で有名ですが、この本は特にそうで、一回読んだだけではさっぱり頭に入らず、二回目に注釈を飛ばしてなおかつマーカーで線を引きながら読んでようやく少しだけ理解できた感じです。私には「ヴェーバー的倒錯」と呼んでいる現象があって、それは何かというと、たとえば「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」であれば、本来であれば「プロテスタンティズムの倫理」について多少は知識がある人が読むべきと思いますが、大抵の日本人はヴェーバーの著作によってプロテスタンティズムを知る、ということになります。「古代ユダヤ教」なんかに至ってはさらにそうで、クリスチャンでない限り、旧約聖書の世界に精通している人は日本にはそうはいません。「儒教と道教」ぐらいなら、日本人であれば多少はヴェーバーよりも理解しているかも知れませんが、それだって実は怪しいのではないかと思います。(「老荘思想」は知っていても、道教の実際を良く知っている人がどれだけ日本にいるでしょうか。)
マックス・ヴェーバーの「ロッシャーとクニース」(松井秀親訳)を読了しました。ヴェーバーの本は大体において難解で有名ですが、この本は特にそうで、一回読んだだけではさっぱり頭に入らず、二回目に注釈を飛ばしてなおかつマーカーで線を引きながら読んでようやく少しだけ理解できた感じです。私には「ヴェーバー的倒錯」と呼んでいる現象があって、それは何かというと、たとえば「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」であれば、本来であれば「プロテスタンティズムの倫理」について多少は知識がある人が読むべきと思いますが、大抵の日本人はヴェーバーの著作によってプロテスタンティズムを知る、ということになります。「古代ユダヤ教」なんかに至ってはさらにそうで、クリスチャンでない限り、旧約聖書の世界に精通している人は日本にはそうはいません。「儒教と道教」ぐらいなら、日本人であれば多少はヴェーバーよりも理解しているかも知れませんが、それだって実は怪しいのではないかと思います。(「老荘思想」は知っていても、道教の実際を良く知っている人がどれだけ日本にいるでしょうか。)
この「ロッシャーとクニース」もまさにそうで、ヴェーバーは「ドイツ歴史学派の子」として、その親にあたる二人の学者を批判して自分の拠って立つ学問的基礎を固めようとしている訳ですが、この「ドイツ歴史学派」というのが、今日の日本ではほとんど知られていないと思います。この歴史学派は、経済学での「合理的な人間」(自分の利潤を最大限にしようとして行動する人間)の考えや、法学における「自然法思想」に対する批判として起こり、そういう普遍性の追究よりも、歴史的な経緯というものを重んじる学派です。それはドイツ自身がプロイセンによって国民国家としてやっと統一された「遅れてきた国民国家」としての立場主張と考えられます。その創始者はフリードリヒ・リスト(1789-1846)で、国民国家を最高のものとし、ヘーゲル的な発展段階説を唱えます。その後に来るのがブルーノ・ヒルデブラント(1812-1878)、ヴィルヘルム・ゲオルク・フリードリヒ・ロッシャー (1817-1894)やカール・グスタフ・アドルフ・クニース(1821-1898)になり、ヴェーバーがこの本で批判の対象にしているものです。
マックス・ヴェーバーの生涯はご承知の通り、1864年-1920年ですから、ロッシャーは47歳、クニースは43歳年上で、ヴェーバーから見ればいわば父親から祖父の世代になります。
そこでこの二人の批判ですが、ロッシャーに対する批判は比較的理解しやすいです。もっとも私はロッシャーの著作は一切読んだことがないので、片手落ちではありますが、ヴェーバーは、ロッシャーが「因果性」と「法則性」をごちゃごちゃにしていて、というか最初から「民族共同体の発展の図式」のような素朴な「信仰」がバックにあり、つまる所は宗教的な信仰へと行き着きます。19世紀に宗教から科学が分離をし始めますが、ロッシャーの段階ではそれはまだ混ざり合ったものであり、科学的な歴史の解明としては問題が多いことをヴェーバーは批判しています。
これに対して、クニースへの批判は非常に錯綜しており、分かりづらいです。私はクニースの著作もまったく読んでいませんが、ヴェーバーによればそれ自体がかなり晦渋なもののようです。しかもヴェーバーはクニース批判に入る前にそれと関連あるものとして、まずは実験心理学のヴィルヘルム・ブント(1832-1920)の方法論を批判し、さらには同じく心理学のヒューゴー・ミュンスターベルク(1863-1916)をも批判します。ヴェーバーが自分の社会学を心理学とははっきりと区別していることは例えば「理解社会学のカテゴリー」にも出てきますが、ここではかなり詳細に立場の違いが論じられます。
さらには続けてゲオルグ・ジンメル(1858-1918)の説も取り上げられます。ヴェーバーが歴史における現象の「意味」を客観的に「理解」することを、主観的な動機の解明(心理学的なアプローチ)からきちんと区別したことをジンメルの功績として挙げ、ヴェーバーの立場がそれに近いことを示しています。
ここで一言言っておかなければならないのは、私は保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」への書評の中で、保城がヴェーバーの理解社会学を「解釈学」として表現することに異を唱え、「ウェ-バーの方法論のテキストの中に「解釈学」という言葉が出てくるのを私は記憶していません。」と書きました。しかし、この私の書いていることは間違いで、この「ロッシャーとクニース」の中には、「解釈」や「解釈学」という言葉は何度か登場します。しかしヴェーバーは、「解釈学」が扱う「解釈」の問題は、彼がこの著作で問題にしている認識論的な問題とはまったく別のことを扱っているので、シュライエルマッハーやベックの研究は考慮しないとはっきり言っています。またディルタイの論説についてもその先入観ともいうべき部分を批判しています。私はこの「ロッシャーとクニース」によって、再度ヴェーバーの「理解社会学」は(いわゆるシュライエルマッハーやディルタイからハイデガーにつながる)「解釈学」とは理解されるべきでないことを再度確認できたと思います。
そういう風に延々と回り道をして、第三論文でようやくクニース批判にたどりつきますが、しかしこの論文は未完であり、途中で終わってしまっています。結局クニースの考え方は人間は統一された有機体であり、さらにその考え方を国民国家にも適用し、国家もそのような有機体として理解されるべきと考えているとヴェーバーは批判します。その「統一的有機体」というものが定義も歴史的な解明もされず所与のものとされて最初から前提とされている所にヴェーバーはクニースの学問の非科学性を見ています。
といったような私の理解がどこまで読めているのかはまったく自信がありませんが、ヴェーバーが精神疾患からの回復過程でかつ「プロテスタンティズムの倫理と資本主義」を書く前にこの方法論的考察を行ったという所が非常に興味深く感じます。
磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」
 磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」を読みました。
磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」を読みました。
筆者は日本人は勤勉と一般的に言われているけど、元々江戸時代などではそうではなかったという仮説を立て、どこで勤勉へとギアが切り替わったかを突き止めようとします。
私は個人的には「今の」日本人がそれほど勤勉とは思っていないので、スタートからすれ違いがありますが、それを抜いても、この筆者の論は仮説の提示に終わって、検証やより突っ込んだ説明というのがきわめて不足しているように思います。
たとえば、第4章で「浄土真宗と「勤労のエートス」」というのがあって、一部の浄土真宗の在野の僧侶が勤勉を説き、それを聞いた信徒が勤勉な生活を送ったとし、要するにマックス・ヴェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で述べたカルヴィニズムの役割を浄土真宗に求めます。しかし、この論理はきわめて杜撰といわざるを得ません。
(1)一部の浄土真宗の僧侶が「勤勉」を説いていたとしても、それが浄土真宗全体に言えることなのか。たまたまその僧侶が「勤勉」を強調しただけに過ぎないのではないのか。
(2)もし浄土真宗にその信徒に勤勉を誘発する力があるとするならば、それは真宗のどのような教義から派生するのか。
筆者は浄土真宗は念仏によって誰でも極楽に行けるから、働く場所がどこであっても気にせず、他国に移されても勤勉に働いた、としていますが、この説明はきわめて変です。念仏で救われることが決まるなら、むしろ信徒としては生活をある形にはめないで自由に生きる、という方向に行くことも十分考えられるからです。
(3)マックス・ヴェーバーは「プロ倫」で「勤勉」だけを説明したのではなく、「勤勉を含む生活全体の合理化」を説明したのであって、単なる「勤勉」の思想だけでは、資本主義を生み出すものとしてはきわめて不十分です。また、この生活の合理化は、「合理的な資本家」を生み出す基盤にもなりますが、真宗での「勤勉」は単に農民として仕事に精を出す、というレベルのものに過ぎません。
この筆者は吉田松陰にまで浄土真宗の影響を拡大しますが、私に言わせれば西日本で一番多い宗派が浄土真宗というだけで、松陰が浄土真宗の影響を受けているとはとても思えません。浄土真宗に限らず、江戸時代の仏教は檀家制度の元でいわゆる「葬式仏教」に堕しており、とても人々に何かのエートスを与えるようなものではなかったと思います。
以上のように、ある意味こじつけみたいな仮説が多すぎて私はこの本についてはまったく感心しませんでした。
保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」
 保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」を読みました。「歴史をどう学問的に扱うか」「社会科学にとって理論とは何か、そしてその検証方法は」ということに関心があって、マイヤーとヴェーバーの「歴史とは科学か」に続けて読みました。結論としてこの本は最近の情報をよく整理してあり、それなりに筆者なりの新しい試みも行っており、まあまあ評価出来るものでした。しかし、以下の点で疑問が残ったり、また異論があります。
保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」を読みました。「歴史をどう学問的に扱うか」「社会科学にとって理論とは何か、そしてその検証方法は」ということに関心があって、マイヤーとヴェーバーの「歴史とは科学か」に続けて読みました。結論としてこの本は最近の情報をよく整理してあり、それなりに筆者なりの新しい試みも行っており、まあまあ評価出来るものでした。しかし、以下の点で疑問が残ったり、また異論があります。
(1)「中範囲の理論」の「中」範囲とは何か?
この筆者はマートンの用語を借りて、扱う問題・時間・空間に限定を加えた「中範囲の」理論というものを提唱します。しかし、「中範囲」があるなら「大範囲の理論」「小範囲の理論」とは何なのか、今一つ明らかではありません。この本に述べられているものは、私に言わせれば「小範囲の理論」に過ぎないと思います。というか個人的には社会科学においては、結局どんな時代や社会にも適合するような「大理論」は存在せず、全ての理論化の試みは「小理論」に過ぎないのではないかという思いを強く持っています。
(2)歴史学と社会科学の結合
歴史学者は社会科学の学者に対し、自分達が苦労して調べたことを好き勝手に援用し、自分で事実を調べもしないで勝手な理論化を行っていると非難し、社会科学者は歴史学者が近視眼的過ぎて、森を見ないで木だけを見ていると非難します。これはマイヤーとヴェーバーの時代からそうで、今も同じ状況が続いているみたいです。これに対し筆者は(1)の「中範囲理論」で扱う問題・時間・空間に限定を加えることで、その限られた時空間に対しては歴史学者として事実の収集を行い、その上で社会科学的な分析を加えることを提案して、実際に実践もしているようです。しかし、歴史の流れというものを無視して、ある限定された時空間だけを切り出して分析するということ自体が、既に歴史学の立場からすると相容れないもののように思います。また、ヴェーバーの時代は、社会科学の各分野は現在のように細分化されておらず、経済学は法学部の中で扱われていましたし、また社会学もその中から産まれて来ました。そして、ヴェーバーの時代には各分野の学者はかなりの部分垣根を越えて意見を戦わせていたように思います。ヴェーバーとマイヤーが論争しているのもそのいい例だと思います。さらにはハイデルベルクのヴェーバーの家で、ヤスパースやトレルチなど分野の違う学者が文化的サークルを作って交流していたことも周知の事実です。それに対し、今のアカデミズムでの一番の問題点と私が思うのは、各人が自分の極めて狭い専門分野だけに関心を限定し(しかもしばしば研究テーマの選択がある意味非常に恣意的かつ時には奇妙でさえあって)、他の広い分野の人間と積極的に意見交換をしなくなっていることだと思います。私に言わせれば、歴史学者と社会科学者を一人で兼ねなくても、お互いにお互いの素材を利用して活発な議論や相互批判を行って、少しでも真実に近づけばいいのだと思います。
(3)マックス・ヴェーバーと「解釈学」
この筆者は、ヴェーバーのいわゆる「理解社会学」を解釈学と呼んでいます。この言い方はヴェーバーの学問を理解する上でも、また「解釈学」という言葉の使い方でも間違っていると思います。ヴェーバーの方法論は「理解社会学のカテゴリー」が一番良くまとまっているかと思いますが、人間の行為の意味を社会における集団形成の推進力の元としてのゲマインシャフト行為、ゲゼルシャフト行為といった形で定式化して、社会の動きのダイナミクスを捉えようとするものだと、私は思っています。ウェ-バーの方法論のテキストの中に「解釈学」という言葉が出てくるのを私は記憶していません。また「解釈学」の方も、本来の意味は聖書などの「テキスト」をどのような意味に解釈するかの学問であり、また哲学の世界ではハイデガーが自分の「存在と時間」のことを解釈学と呼んでいますが、ヴェーバー的な社会学においての人間の行為の意味を「解釈する」ための学問、と捉えている人はまずいないと思います。
そういう訳で参考にはなりましたが、特に(3)の点でこの人は元々社会学専攻(現在は国際関係論専攻)でありながら、ヴェーバーもきちんと読んでいないのではないかと思いました。
マイヤーの「歴史の理論と方法」とヴェーバーの「文化科学の論理学の領域における批判的研究」
 エドワルト・マイヤーとマックス・ヴェーバーの「歴史は科学か」(森岡弘通訳、みすず書房)を読みました。エドワルト・マイヤーの「歴史の理論と方法」とヴェーバーの「文化科学の論理学の領域における批判的研究」の両方を収録しているものです。マイヤーは20世紀初めにおいての有名な歴史家で、その「古代史」は、古代ギリシアがその当時の現代西洋に対して最大の影響を及ぼしているとして、その形成の過程を解き明かした書として高く評価されています。19世紀に実証的な自然科学が発達し、従来は科学としては見られていなかった歴史の記述も「歴史学」を名乗るであれば、その拠って立つ学問的な方法論は何なのかが厳しく問われるようになり、それにマイヤーが応えたのが、「歴史の理論と方法」です。マイヤーは冒頭で「歴史は何ら体系的な学問ではない」とまず断り、その当時のヘーゲル的な発展段階的な史観や唯物史観で歴史をある意味単純化して理解しようとするやり方に異を唱えました。その点に関してはマイヤーもヴェーバーも同じ立ち位置にあります。しかし、ではどういう方法論的立場でマイヤーは歴史の素材を扱うのかという問いに対しては、マイヤーはかなり舌足らずでまた自分が実際にその著作で実践している内容をかなり性急に定式化してしまいます。それは歴史において全てが重要なのではなく、その後の時代に対して「影響を及ぼした」ものこそが重要で、それによる因果連関の解明が歴史学の課題だとします。こうしたマイヤーの論理展開はかなり不用意であり、当然のことながらヴェーバーから自己矛盾的な記述として詳細に突っ込まれています。
エドワルト・マイヤーとマックス・ヴェーバーの「歴史は科学か」(森岡弘通訳、みすず書房)を読みました。エドワルト・マイヤーの「歴史の理論と方法」とヴェーバーの「文化科学の論理学の領域における批判的研究」の両方を収録しているものです。マイヤーは20世紀初めにおいての有名な歴史家で、その「古代史」は、古代ギリシアがその当時の現代西洋に対して最大の影響を及ぼしているとして、その形成の過程を解き明かした書として高く評価されています。19世紀に実証的な自然科学が発達し、従来は科学としては見られていなかった歴史の記述も「歴史学」を名乗るであれば、その拠って立つ学問的な方法論は何なのかが厳しく問われるようになり、それにマイヤーが応えたのが、「歴史の理論と方法」です。マイヤーは冒頭で「歴史は何ら体系的な学問ではない」とまず断り、その当時のヘーゲル的な発展段階的な史観や唯物史観で歴史をある意味単純化して理解しようとするやり方に異を唱えました。その点に関してはマイヤーもヴェーバーも同じ立ち位置にあります。しかし、ではどういう方法論的立場でマイヤーは歴史の素材を扱うのかという問いに対しては、マイヤーはかなり舌足らずでまた自分が実際にその著作で実践している内容をかなり性急に定式化してしまいます。それは歴史において全てが重要なのではなく、その後の時代に対して「影響を及ぼした」ものこそが重要で、それによる因果連関の解明が歴史学の課題だとします。こうしたマイヤーの論理展開はかなり不用意であり、当然のことながらヴェーバーから自己矛盾的な記述として詳細に突っ込まれています。
ヴェーバーの指摘はごもっともと思いつつも、その指摘内容はある意味社会科学的な歴史の取り扱いのように思え、如何にして歴史の無限の多様性を科学的に取り扱うのか、という点に関しては必ずしもヴェーバーは完全な解答は出していないと思います。もちろん後の「経済と社会」における理念型と決疑論を使った歴史記述は一つの答だとは思います。しかしそれはそれとして別のやり方があるのではないかという思いは禁じ得ません。この解答を求めて、更に2冊の本を読むことになりました。
理念型とフラット・キャラクター
今、フランスの歴史家のイヴァン・ジャブロンカが書いた「歴史は現代文学である」を読んでいます。この本は歴史を科学的に扱おうとして19世紀以降歴史と文学が切り離された物を、もう一度結びつけようとする試みでなかなか興味深いです。
それでちょっと思いついたのですが、社会学で「理念型」(ドイツ語でIdealtypus)という方法論みたいなのがあります。歴史の現象を解釈する上で、観念的に作り出された一種の純粋型のことです。昔は「理想型」と訳されていましたが、「理想」というと価値判断が伴っているようですし、また「売春宿」のIdealtypusもあり得るということで、ニュートラルな「理念型」という訳に落ち着いています。
で思ったのが、この「理念型」の元は、文学における「フラット・キャラクター」(平面的キャラクター)じゃないのかということです。この「フラット・キャラクター」はE.M.フォースターの造語で、対照にされるのは「ラウンド・キャラクター」(立体的キャラクター)です。フラット・キャラクターは、フォースターはディケンズの小説の登場人物はほとんどそうだとしていますが、ある類型的な性格や社会的地位をもっていて常に読者が期待するような行動をする人のことです。(ラウンド・キャラクターはそれとは違い、性格などが次第に変化して深まっていくようなタイプのキャラクターです。)例えば「クリスマス・キャロル」の(改心する前の)スクルージ爺さん、「ディヴィッド・コパフィールド」の悪役のユライア・ヒープ(ロックバンドのユーライア・ヒープはこの名前を借りたものです)なんかが、まさしくフラット・キャラクターです。
マックス・ヴェーバーは有名な「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の中で、「資本主義の精神」を読者にわかってもらうための「理念型」としてベンジャミン・フランクリンを使います。しかし、それは実在のフランクリンというより、キュルンベルガーという作家の書いた「アメリカにうんざりした男」という詩人レーナウのアメリカ体験を元にした小説に登場する「カリカチュア化したフランクリン」であり、まさしくフラット・キャラクターそのものです。
もちろん、「理念型」は人間だけに使うものではないのですが、少なくとも小説におけるフラット・キャラクターの使用の方が社会科学よりはるかに先なんではないかと。
マックス・ヴェーバーの「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」(富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳)
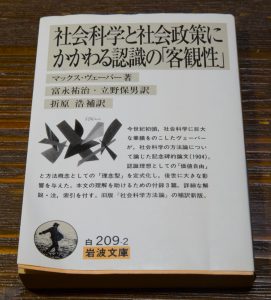 マックス・ヴェーバーの「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」(富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳)を読了しました。元々富永祐治・立野保男訳で「社会科学方法論」という書名で岩波文庫で出ていたもので、この論文の初の日本語訳だったものです。実は日本語訳については他に4種類くらい出ていて、たとえば「中世合名会社史」や「ローマ農業史」が未だに日本語訳が一つも出ていないのと著しい対照を成しています。折原先生は元々岩波書店から「新訳」を頼まれたそうですが、最初の翻訳を参照しながら、どこが新しくなったのか分からないような「新訳」が多数出る状況に疑問を抱かれ、実際には訳文の全面的な見直しをされたにも関わらず敢えて「補訳」と称されています。更には雑誌「アルヒーフ」に載った「移行予告」「告別の辞」「緒言」も一緒に掲載し、その上折原先生による丁寧な解説が付いているという、この論文の日本語訳の決定版です。
マックス・ヴェーバーの「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」(富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳)を読了しました。元々富永祐治・立野保男訳で「社会科学方法論」という書名で岩波文庫で出ていたもので、この論文の初の日本語訳だったものです。実は日本語訳については他に4種類くらい出ていて、たとえば「中世合名会社史」や「ローマ農業史」が未だに日本語訳が一つも出ていないのと著しい対照を成しています。折原先生は元々岩波書店から「新訳」を頼まれたそうですが、最初の翻訳を参照しながら、どこが新しくなったのか分からないような「新訳」が多数出る状況に疑問を抱かれ、実際には訳文の全面的な見直しをされたにも関わらず敢えて「補訳」と称されています。更には雑誌「アルヒーフ」に載った「移行予告」「告別の辞」「緒言」も一緒に掲載し、その上折原先生による丁寧な解説が付いているという、この論文の日本語訳の決定版です。
この論文をこのタイミングで読み直しているのは、今「経済と社会」の旧稿部を読んでいる訳ですが、そこで「決疑論(カズイスティーク)」について考えた際に、決疑論でまず行われる歴史の諸事例の類型化というのはまさに「理念型」なのであり、ヴェーバーが「理念型」にどのような意味を込めているのかを再度確認したくなったからです。結局の所ヴェーバーの学問は(というよりちゃんとした社会科学は)歴史事象を分析してある理念型を作り、それを元に理論を組立て、その結果更に考えが発展したら一旦設定した理念型を壊してまた新しいものを作り、ということを延々と繰り返していくものなのだ、と理解しました。
話は少しずれますが、ヴェーバー的方法論というのは、私にとって学問だけの問題ではなく、たとえばビジネスにおいても非常に役に立っています。ビジネスにおける様々な問題も社会科学の設定する問題とかなり近いものがあり、例えば自然科学の天文学のように、月食の日時を正確に予測する、といった精度で理論を組み立てることが不可能な事象が多数存在します。そういった場合に、(ビジネス上の)価値判断とは切り離した上で、自分なりに理念型を構成し、曖昧模糊とした先行きを少しでも正確に予測する、ということの方法論として十分に役立っています。なのでヴェーバーの学問は私にとって、閉じた象牙の塔だけのものでは決してない訳です。
マックス・ヴェーバーの「社会学の基礎概念」(阿閉吉男、内藤莞爾訳)
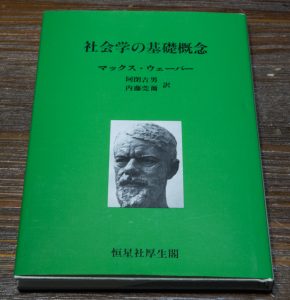 マックス・ヴェーバーの「社会学の基礎概念」(阿閉吉男、内藤莞爾訳)を読了。今、折原浩先生の仮説に基づく順番で「経済と社会」の旧稿を読み直している最中ですが、その前にこれもやっぱりきちんと読んでおかないといけないかと思い読んだものです。私が学生の時は清水幾太郎訳が岩波文庫で出ていましたが、この日本語訳がかなり問題が多いものだと聞いていましたので、今日まで読む機会がありませんでした。この阿閉・内藤訳は丁度私が卒業した年の翌年に出ています。
マックス・ヴェーバーの「社会学の基礎概念」(阿閉吉男、内藤莞爾訳)を読了。今、折原浩先生の仮説に基づく順番で「経済と社会」の旧稿を読み直している最中ですが、その前にこれもやっぱりきちんと読んでおかないといけないかと思い読んだものです。私が学生の時は清水幾太郎訳が岩波文庫で出ていましたが、この日本語訳がかなり問題が多いものだと聞いていましたので、今日まで読む機会がありませんでした。この阿閉・内藤訳は丁度私が卒業した年の翌年に出ています。
この「社会学の基礎概念」は、以前の「経済と社会」(ヨハネス・ヴィンケルマン編集による二部構成のもの)では、トップに置かれており、あたかもこれが「経済と社会」全体でのヴェーバーの方法論を示す論文だと理解されてきました。しかし、第二部のいわゆる「旧稿」については、この論文ではなく、1913年にLogos誌に発表された「理解社会学のカテゴリー」に準拠して読まなければならない、というのが折原浩先生の主張の内のもっとも重要な部分です。
それでは何故マックス・ヴェーバー自身が一度既に書いているカテゴリー論を新たに書き直す必要があったのか、という疑問が出てきます。それについては、ヴェーバーが1919年からミュンヘン大学で学生相手に「理解社会学のカテゴリー」に基づく講義を行った時の経験が影響していると言われています。「カテゴリー」論文では、ヴェーバーはゲマインシャフトとゲゼルシャフトという用語を、テンニースが最初にしたように「共同社会」と「利益社会」という対立概念ではなく、ゲマインシャフトの方がゲゼルシャフトをも包括する広い概念で、ある条件が整った特殊な場合のみがゲゼルシャフトであると定義していました。(正確に言うと、ゲマインシャフトとゲマインシャフトを直接定義したのではなく、ゲマインシャフト行為、ゲゼルシャフト行為という、人間の行為の種類の定義ですが。)ところが、このヴェーバーの定義がミュンヘン大学の学生にとってはテンニースの概念とごちゃごちゃになって極めて理解しづらいものだったと言われています。そのために、方法論論文をより一般向けにわかりやすく書き換えると同時に用語法も大幅に変更したのがこの「社会学の基礎概念」論文になります。そこではゲマインシャフトとゲゼルシャフトの定義がテンニースのものにかなり接近します。さらにゲマインシャフト行為、ゲゼルシャフト行為と言ったドイツ語そのものに起源を持つ特殊な用語法が消えて、その代わりにラテン語のsocietas(人の集まり、社会、組合といった意味)に起源を持つ、sozial-という形容詞を使ったsoziales Handeln(社会的行為)というかなり一般的な用語が使われるようになっています。
それと並んで重要なのは、「理解社会学のカテゴリー」ではかなり重要な概念として定義されていた「諒解」という概念(ゲマインシャフト行為の中で、例えば法律などによって目的合理的に協定された秩序を欠いているにもかかわらず、ある個人が理解していることを他の個人も理解しているであろうと予測しているのが「諒解」で例として貨幣の市場だとか言語共同体が挙げられています。)が、この「基礎概念」ではまったく消え去ってしまうことです。この理由は今の所私には理解できていません。しかし、例えば「法社会学」の冒頭部などを読めば、この「諒解」概念を理解することなしには、ヴェーバーの言わんとすることを理解するのはきわめて困難です。その意味で、この「社会学的の基礎概念」は「間違った頭」とされます。
