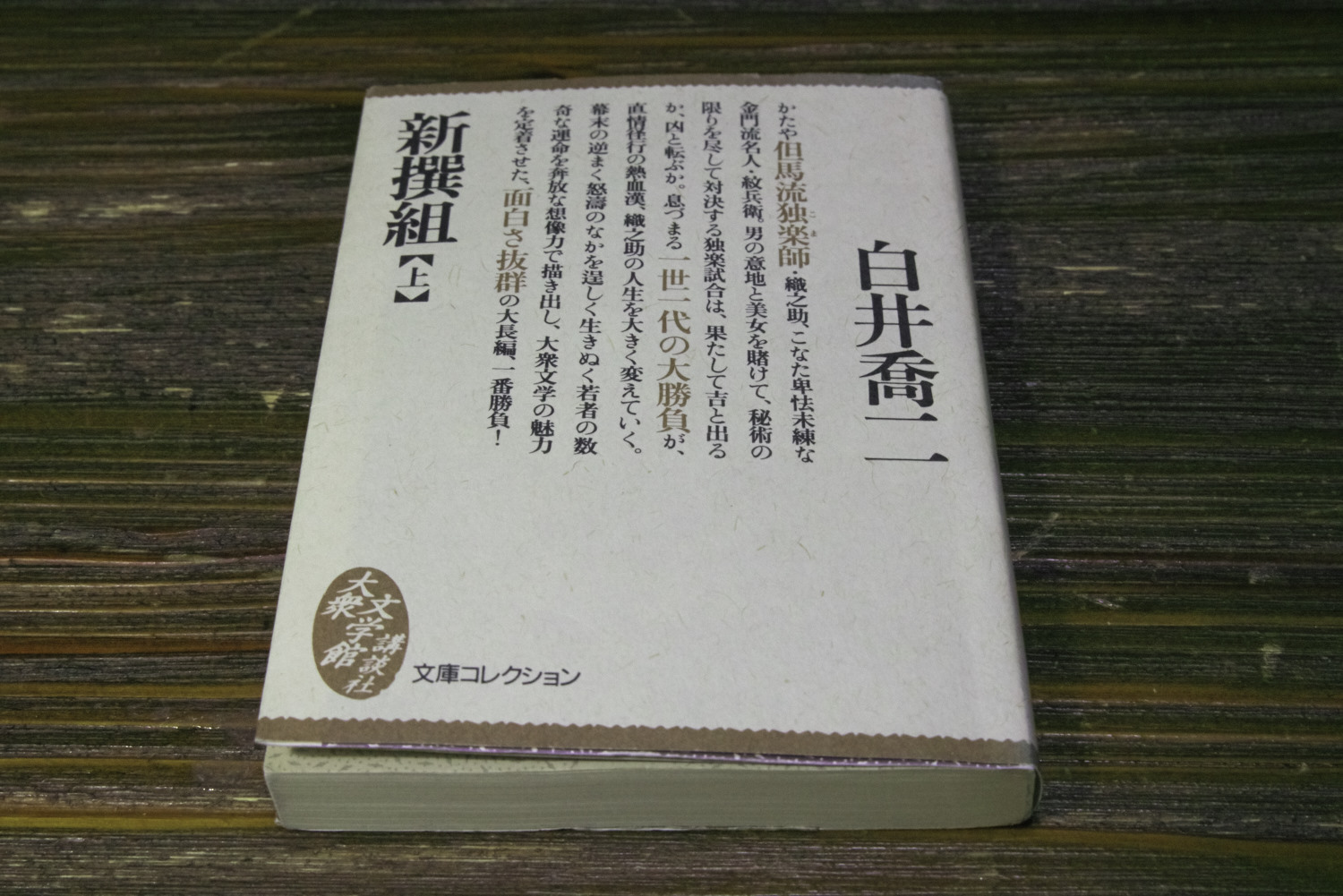 白井喬二の「新撰組」[下]を読了。
白井喬二の「新撰組」[下]を読了。
タイトルの「新撰組」は下巻の半分くらい、全体の3/4を経過したところでやっと登場します。それで池田屋事件とかも出てくるのですが、新撰組はあくまで背景に過ぎません。メインは、但馬流の織之助、金門流の紋兵衛、そして京都の伏見流の潤吉、この3人の独楽勝負を巡るお話しに、勤王の志士の妹であるお香代がからみます。織之助は、最初紋兵衛と戦い、その後潤吉と戦います。そして最後にお香代をどちらが妻にするかをかけて、潤吉と再度、肉独楽という占い独楽で決着をつけようとします。とにかくはらはらどきどき、織之助の人生も波乱万丈で読んでいて非常に楽しいです。ポケモンgoもいいけど、やっぱり本もいいです。
カテゴリー: Book
白井喬二の「新撰組」[上]
伊藤祐靖の「国のために死ねるか 自衛隊『特殊部隊』創設者の思想と行動」
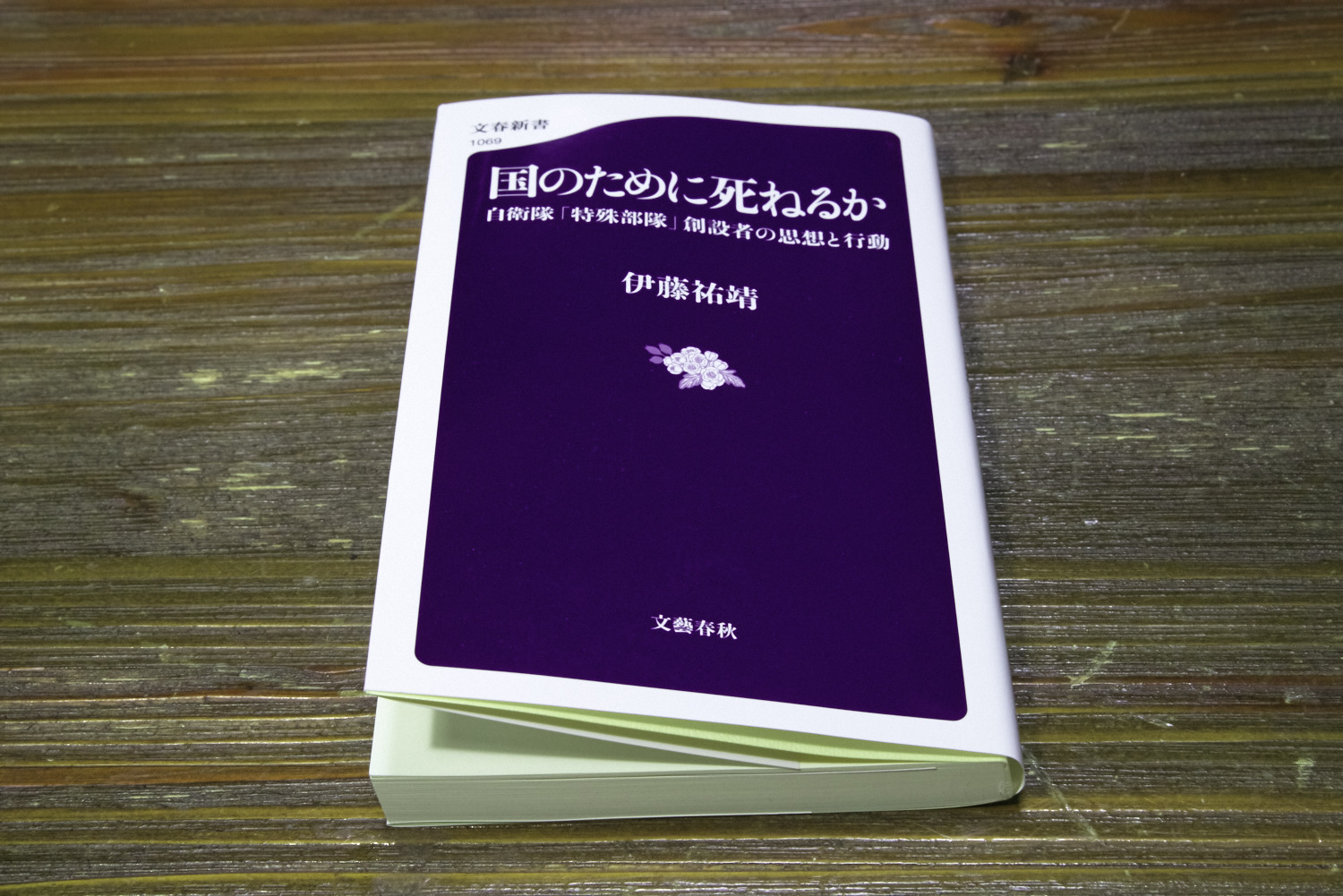 伊藤祐靖の「国のために死ねるか 自衛隊『特殊部隊』創設者の思想と行動」を読了。たぶん片山杜秀の右翼に関する本を買ったので、そのつながりでAmazonがおすすめで出してきたもの。強烈なタイトルに惹かれて購入。
伊藤祐靖の「国のために死ねるか 自衛隊『特殊部隊』創設者の思想と行動」を読了。たぶん片山杜秀の右翼に関する本を買ったので、そのつながりでAmazonがおすすめで出してきたもの。強烈なタイトルに惹かれて購入。
筆者は、海上自衛隊で、イージス艦「みょうこう」の航海長在任時に、北朝鮮の工作母船と遭遇し、その船を威嚇銃撃しながら追撃し、一度は停船させましたが、結局取り逃がすという能登半島沖不審船事件に遭遇しています。この時、工作母船の船内を調査することが必要でしたが、この時点ではその任務にふさわしい技能を持ったものは自衛隊にはいませんでした。これをきっかけに自衛隊初の特殊部隊である海上自衛隊の「特別警備隊」の創設に関わります。その後、特殊部隊について自衛隊の幹部と考え方が合わず退官、フィリピンのミンダナオ島に移り、そこでもさらに特殊部隊としての技能を磨いて、現在は各国警察や軍隊への指導を行っている人です。
まず、この人のお父さんがある意味異常な人で、陸軍中野学校の出身で、戦前に蒋介石殺害の命令を受け、終戦時にもその命令が解除されなかったという理由で、戦後も新たな指令に備えて、毎日射撃訓練を続け、それは1975年に蒋介石が死ぬまで続いたというそういう人です。
そういう父親を持つ人が海上自衛隊の特殊部隊の創設に深く関わるのですが、意外だったのが、アメリカの特殊部隊がある意味世界最弱で、まったく参考にならず、日本独自の特殊部隊を考案したということです。
そういう特殊部隊創設時のエピソードよりももっと興味深いのが、ミンダナオ島に移ってからの体験で、ラレインというおそらく反政府ゲリラ出身の20過ぎの女性で、この女性の「殺し」についての根性がすごいです。筆者にとって射撃は的に当てることですが、このラレインにとっては、相手の顔を吹っ飛ばすことです。また筆者とこのラレインが水中で格闘戦をやった時に、筆者はラレインの肩にまたがって、自分は水面から顔を出し、ラレインは水中に押し込められて呼吸ができないという姿勢になったのですが、ラレインはふりほどけないことがわかると、筆者を水の中に引きずり込んで、そちらも呼吸ができないようにし、結局我慢比べに勝って、不利な闘いを打開します。
そのラレインが、戦争中の日本の沈没船から、大正天皇が関東大震災の時に出した詔勅の額を引き上げてきて、筆者に訳してもらいます。それを聞いた感想が、大正天皇はエンペラーではなく、部族長だということです。何故なら命じるのではなく、ただ「こいねがう」ことしかしていないからです。
筆者の「思想」は正直な所、私には受け入れがたい部分が多いのですが、強烈な本ではありました。
小林信彦の「イーストサイド・ワルツ」
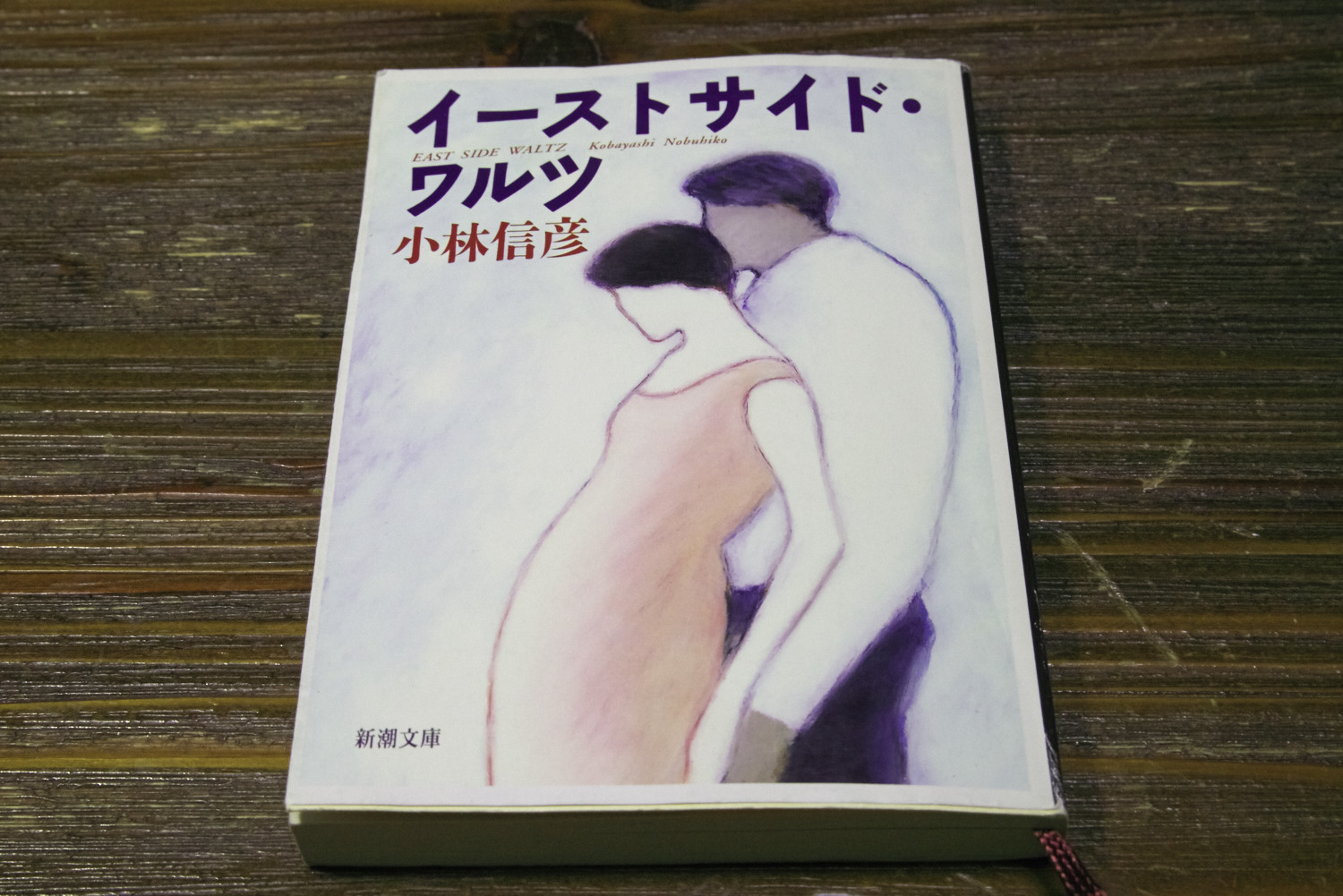 小林信彦の「イーストサイド・ワルツ」再読完了。
小林信彦の「イーストサイド・ワルツ」再読完了。
1993年4月27日~10月3日 毎日新聞朝刊に連載されたもの。朝日新聞に連載された「極東セレナーデ」は一応成功作だと思いますが、この作品は毎日新聞の読者に歓迎されたか疑問です。特に終わり方の暗さと来たら…
作者は後書きで、「初めての恋愛小説」だと説明していますが、それはないと思います。1988年の「背中合わせのハート・ブレイク」(原題は「世間知らず」)はどうなるのでしょうか。その「ハート・ブレイク」と結構共通点が多いです。主人公がどちらも「世間知らず」であること、主人公の若い時の恋愛が自分は振られたと思っていて、相手は逆に主人公に振られたと思っていること、そしてどちらもハッピーエンドではないこと、等々。また、1992年の「ドリーム・ハウス」とも、一緒に住んでいる女性が結婚した後自分を殺して家と土地を自分のものにする、という心配をする所がかぶっています。
後、山の手の男性と下町の女性の恋愛ということで、「東京の街」論がたっぷり出てきますが、恋愛小説には不必要な詳細さであるのと、小林信彦をずっと読んできている読者にはある意味うんざりするような感じです。
この作品は、知らなかったのですが、「イーストサイド・ワルツ 悦楽の園」としてVシネマになっているみたいです。ここで予告編が見られますが、意外と忠実な映像化をしているように見えます。
小林信彦の「ハートブレイク・キッズ」
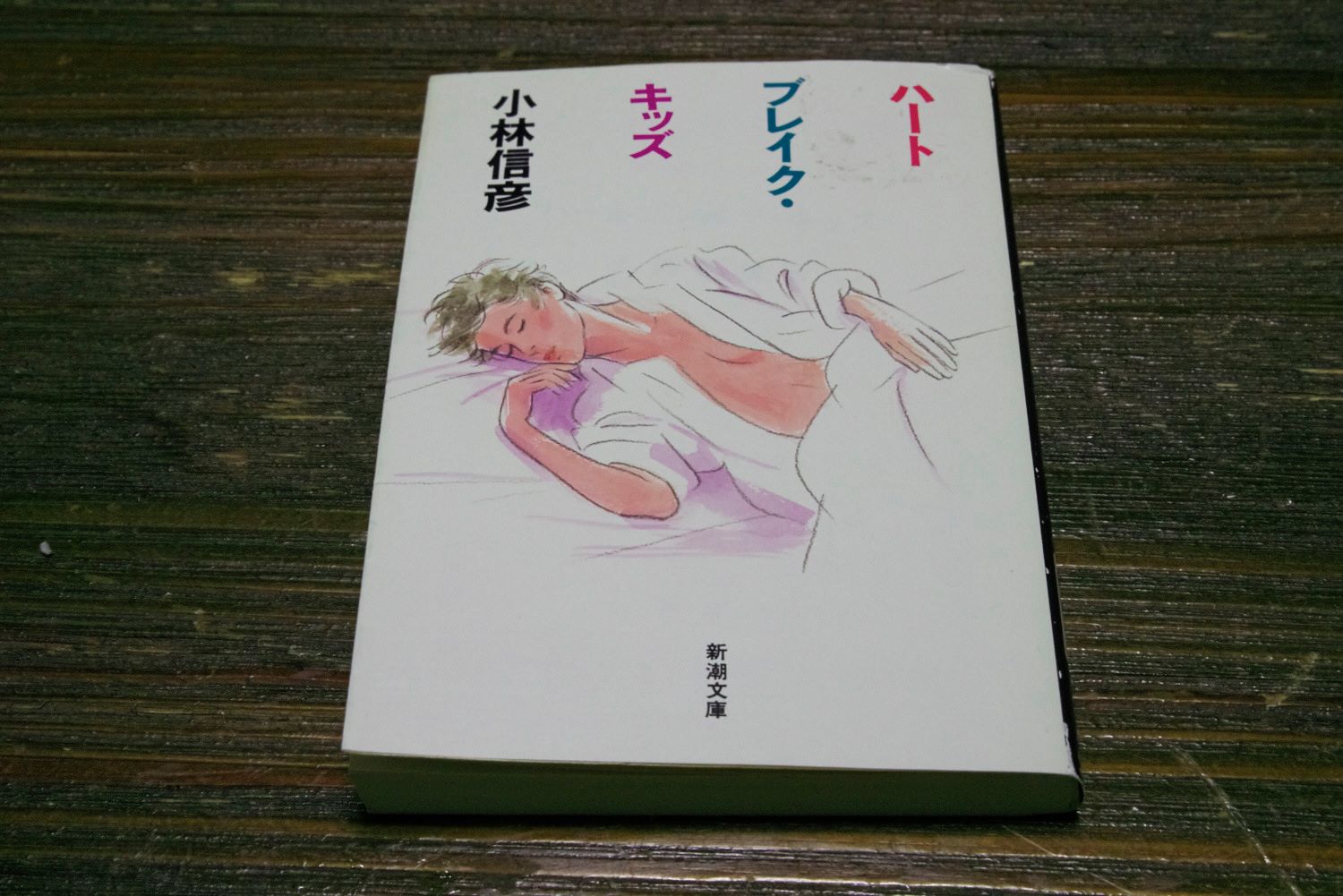 小林信彦の「ハートブレイク・キッズ」を読了。再読かと思いましたが、たぶんまだ読んでなかったようです。1991年に出版されたもので、雑誌JJに1年間連載されたものです。掲載誌が掲載誌だけに、小林信彦作品としては珍しく女性の読者を強く意識したものです。女性に好評だった作品の「極東セレナーデ」の時に身につけた、若い女性のしゃべり言葉がこの作品でも使われています。文庫版の解説の小森収が書いているように、この作品は「小林信彦の小説の様々な定跡のパッチワーク」だと思います。具体的にはその解説にも書いてありますが、前述の「極東セレナーデ」「夢の砦」「紳士同盟」などです。他にも、主人公の恋人になる男の職業が放送作家、また出身が下町で、あることがきっかけで没落している、など、小林信彦によくある設定のオンパレードです。ただ、どれもこれも中途半端にごちゃまぜ、という感じで、決してよく出来た作品ではないと思います。
小林信彦の「ハートブレイク・キッズ」を読了。再読かと思いましたが、たぶんまだ読んでなかったようです。1991年に出版されたもので、雑誌JJに1年間連載されたものです。掲載誌が掲載誌だけに、小林信彦作品としては珍しく女性の読者を強く意識したものです。女性に好評だった作品の「極東セレナーデ」の時に身につけた、若い女性のしゃべり言葉がこの作品でも使われています。文庫版の解説の小森収が書いているように、この作品は「小林信彦の小説の様々な定跡のパッチワーク」だと思います。具体的にはその解説にも書いてありますが、前述の「極東セレナーデ」「夢の砦」「紳士同盟」などです。他にも、主人公の恋人になる男の職業が放送作家、また出身が下町で、あることがきっかけで没落している、など、小林信彦によくある設定のオンパレードです。ただ、どれもこれも中途半端にごちゃまぜ、という感じで、決してよく出来た作品ではないと思います。
池井戸潤の「陸王」
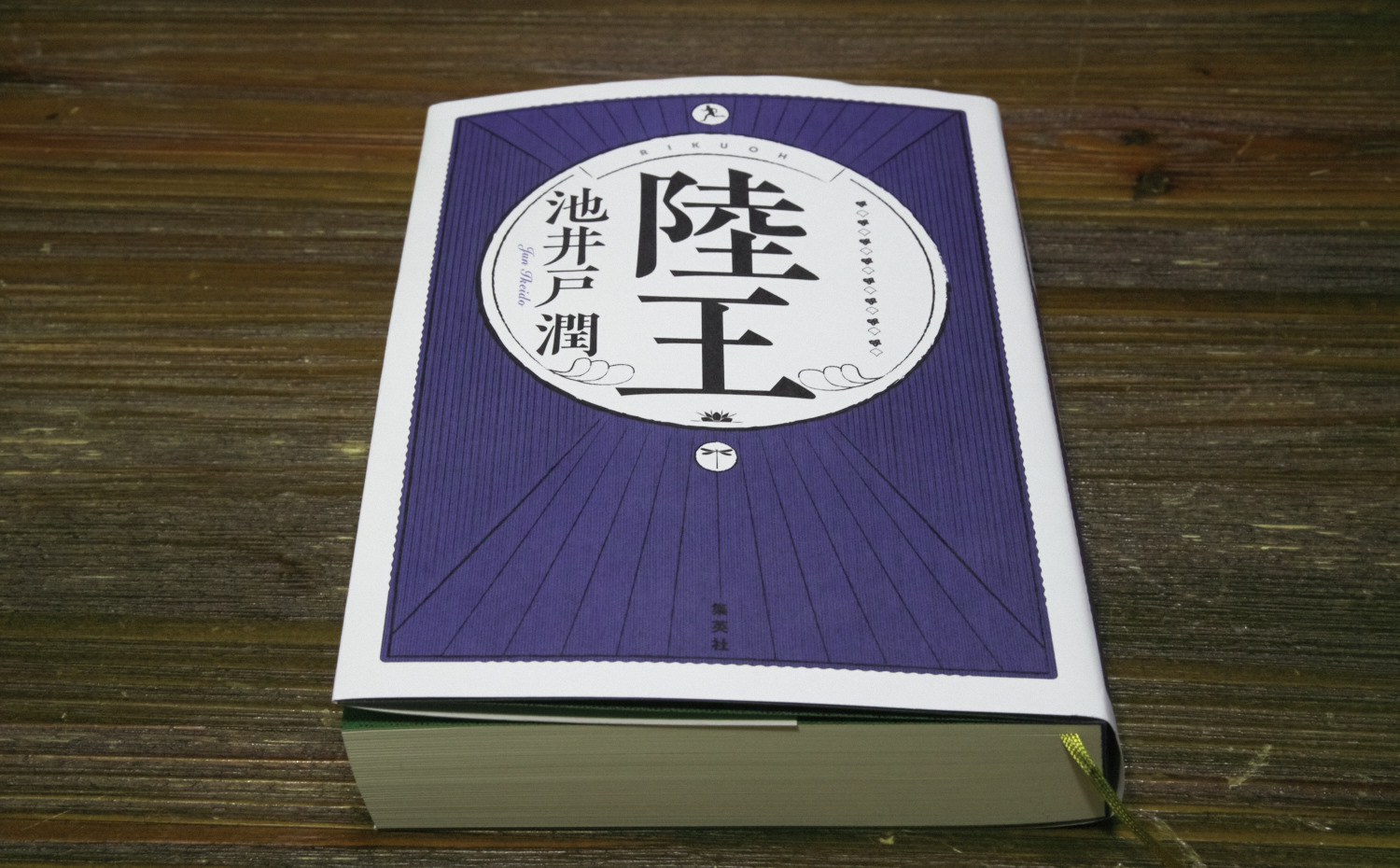 池井戸潤の最新作「陸王」を読了。埼玉県行田市にある創業100年の足袋メーカーこはぜ屋が、新規事業として足袋を応用したスポーツシューズの開発に着手し…とくれば、最近の池井戸潤得意の「下町ロケット」パターンです。ですが、新作としてそれなりにはワンパターンを逃れる工夫はしてあって、一つは茂木という怪我をしてどん底に落ちた長距離ランナーが復活する話をからめたことです。二つ目は、この手の池井戸作品のパターンとして、こはぜ屋には次から次に危機が訪れますが、最後に訪れた最大の危機を脱するためにこはぜ屋が採った手段がちょっと今までのパターンにはなく新しいと思います。三つ目は社長の息子の大地が、就職面接にことごとく失敗して、仕方なくいやいやこはぜ屋で仕事をしていたのが、新製品の開発に関わる内に成長していく、ビルドゥングスロマンとしての一面です。全体的に傑作とは思いませんが、まあまあ楽しめる作品でした。少なくとも今読売新聞に連載している「花咲舞が黙ってない」よりはずっとまし。
池井戸潤の最新作「陸王」を読了。埼玉県行田市にある創業100年の足袋メーカーこはぜ屋が、新規事業として足袋を応用したスポーツシューズの開発に着手し…とくれば、最近の池井戸潤得意の「下町ロケット」パターンです。ですが、新作としてそれなりにはワンパターンを逃れる工夫はしてあって、一つは茂木という怪我をしてどん底に落ちた長距離ランナーが復活する話をからめたことです。二つ目は、この手の池井戸作品のパターンとして、こはぜ屋には次から次に危機が訪れますが、最後に訪れた最大の危機を脱するためにこはぜ屋が採った手段がちょっと今までのパターンにはなく新しいと思います。三つ目は社長の息子の大地が、就職面接にことごとく失敗して、仕方なくいやいやこはぜ屋で仕事をしていたのが、新製品の開発に関わる内に成長していく、ビルドゥングスロマンとしての一面です。全体的に傑作とは思いませんが、まあまあ楽しめる作品でした。少なくとも今読売新聞に連載している「花咲舞が黙ってない」よりはずっとまし。
白井喬二の「富士に立つ影」(総評)
白井喬二の「富士に立つ影」を読了しましたが、以前10巻まで読んだ「大菩薩峠」と比べると、小説としてのまとまりは「富士に立つ影」の方がずっと上だと思います。「大菩薩峠」は最初の方こそ話がとんとんと進みますが、途中で停滞して、時間の進み方も極度に遅くなります。それに比べると「富士に立つ影」は三代七十年の時間的経過がはっきりしていて、話の進行では時が十年くらい飛んだりします。
ですが「富士に立つ影」が完璧な作品かというとそうは思いません。解決されていない謎とかつじつまの合わない箇所がいくつもあります。例えば、第一巻で、怪我をして行方不明になった佐藤菊太郎の行方を追い求めて、喜連川門下の侍二人が登場しますが、この二人は熊木伯典が赤針流の跡継ぎになるにあたって何か不正を行ったのを突き止めて、その証拠を持って伯典を問い詰めるのですが、結局二人とも伯典に殺されて、その不正がなんだったのかは明らかにされないままです。また、小里が蛇蝎のように嫌っていた伯典の妻になるのも、お染の身代わりになったとしてもかなり不自然です。また、熊木伯典と佐藤菊太郎の年齢も、第一巻では伯典が中年から初老の男として描かれるのに対し、佐藤菊太郎は二十代前半として描かれていて、明らかに年齢差がありますが、第二巻以降はこの年齢差が曖昧になります。
まあそうは言っても、「富士に立つ影」はやはり大衆文芸の傑作と思います。
白井喬二の「富士に立つ影」[10](明治篇)
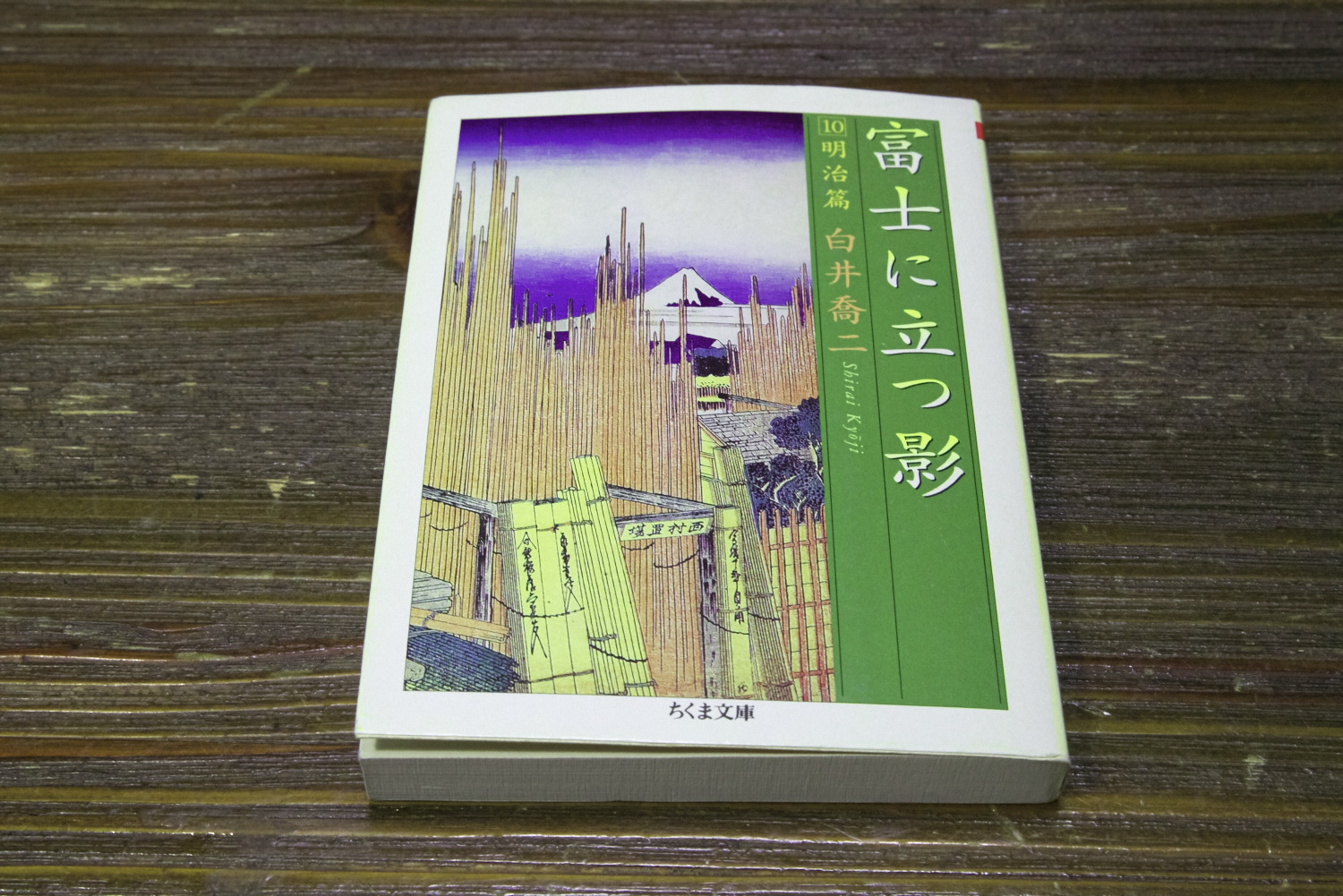 白井喬二の「富士に立つ影」第十巻、明治篇読了。ついにこの長い物語の最後に到達しました。
白井喬二の「富士に立つ影」第十巻、明治篇読了。ついにこの長い物語の最後に到達しました。
明治の御代になりましたが、佐藤光之助は、時勢に合わせることができず、貧窮の生活を送っています。師の杉浦星巌の娘、美佐緒のコネで開成学校のグラスという外人教師に口を利いてもらったお陰で、開成学校の教職につきますが、そのグラスが生徒であった松村介次郎を怒らせ、切りつけられました。松村は逮捕されますが、それで開成学校の生徒達は憤激し、グラスの手引きで学校に入った光之助をも排斥します。
光之助は、いまや押しも押されもせぬ侠客となっている黒船兵吾(お園と佐藤兵之助の息子)が新門辰五郎に紹介してくれたことにより、日本全国の忠臣の事績をまとめるという事業の調査役として採用されます。そうしている内に、杉浦美佐緒から、古い西洋の楽譜を手渡されましたが、それは昔、錦将晩霞が使っていたもので、欄外に、佐藤兵之助が調練隊の隊長に決まった時に、熊木公太郎が錦将晩霞に祝いの曲を所望したという驚くべきことが書いてあることを発見します。
光之助は東北地方を旅し、各地の忠臣の事績を調査しますが、調べていくと、忠臣と褒め称えられる人物が、実際には無実の人間を殺めていたりして、必ずしも立派な人間ではないのを知ります。そうしている内に、仇敵である熊木公太郎こそ理想的な人物であったのではないかと思うようになり、公太郎の足跡を訪ねて歩き、公太郎が那須にいた時の知り合いである笛の名人の森義に出会って公太郎の話を聞くことができました。
光之助は東京に戻り、新橋の陸蒸気の駅で、熊木城太郎に出会います。城太郎はある人の助手として外国に出かけることになっていましたが、光之助は城太郎にもはや仇としては付け狙わないという和解を持ちかけ、ここについに熊木家、佐藤家の三代に渡る対立は終わりを告げます。
物語の最後に、作者は光之助に、「ただこの世はおおらかなる心を持つ者のみが勝利者ではあるまいか。」と語らせています。これがこの小説を貫くテーマであると思います。
白井喬二の「富士に立つ影」[9](幕末篇)
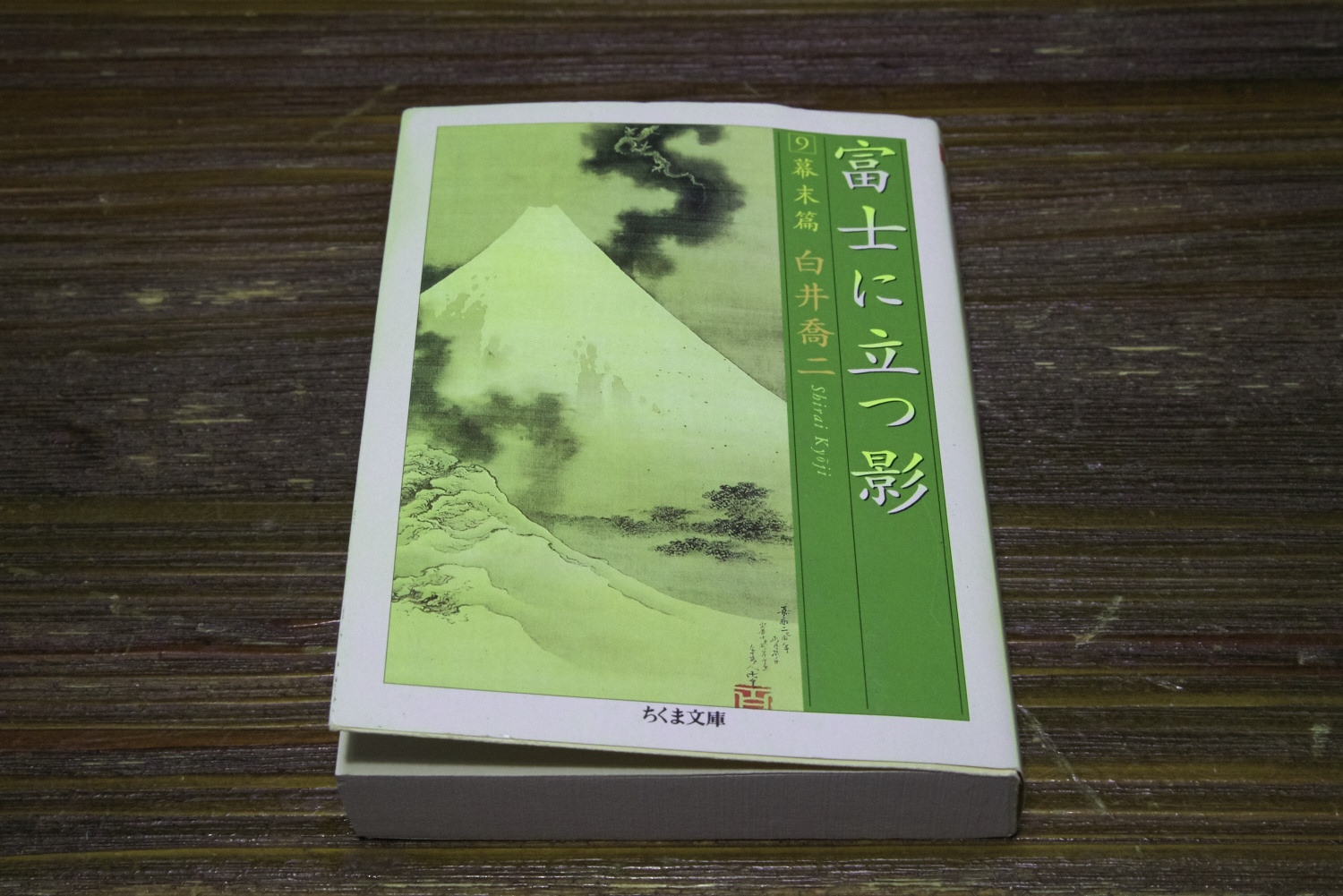 白井喬二の「富士に立つ影」第九巻、幕末篇読了。
白井喬二の「富士に立つ影」第九巻、幕末篇読了。
熊木城太郎は、糊口をしのぐために、赤松浪人団に参加します。そこの副隊長がこともあろうに、佐藤光之助でした。城太郎は光之助から、公私の区別をつけることを条件に入団を許されます。城太郎は、佐藤兵之助を一旦は討ち取ったと思っていましたが、死んだのを確認しなかったため、時が経つにつれて、実は兵之助は生きているのではないかと思うようになります。そのことを、城太郎は光之助に何度も問いただし、光之助を辟易させます。そうこうしている内に、光之助は隊長である赤松総太夫と、お八重という女性を巡って険悪になり、ついには袂を分かつことになりました。その時に団員に、光之助か総太夫のどちらについていくか問うた所、光之助に付き従うものは一人もおらず、ただ公太郎だけが歩みでます。このことを光之助は感謝し、とうとう城太郎に、兵之助が生きていることを告げます。
お八重と光之助は夫婦になりますが、城太郎は兵之助を探して江戸中を彷徨うことになります。兵之助は、音羽に潜んでいましたが、そこで火事があったのをきっかけに、城太郎に居場所を突き止められてしまいます。ですが、すぐにお八重と光之助の新居に移り、無事に城太郎をまくことができました。
兵之助はしばらく平穏に暮らしますが、老残の身になって、今は昔のお園とのことだけが懐かしくなり、お園に会いたくてたまらなくなり、ついには一人でお園に会いにいきます。お園に会って、今こそ愛していることを告げたのですが、老いたお園は今さらと、兵之助の告白を一笑に付します。失意の兵之助は帰りに懐かしい湯島天神に参りますが、そこで熊木城太郎に遭遇し、今度こそ仇を討たれてしまいます。
白井喬二の「富士に立つ影」[8](孫代篇)
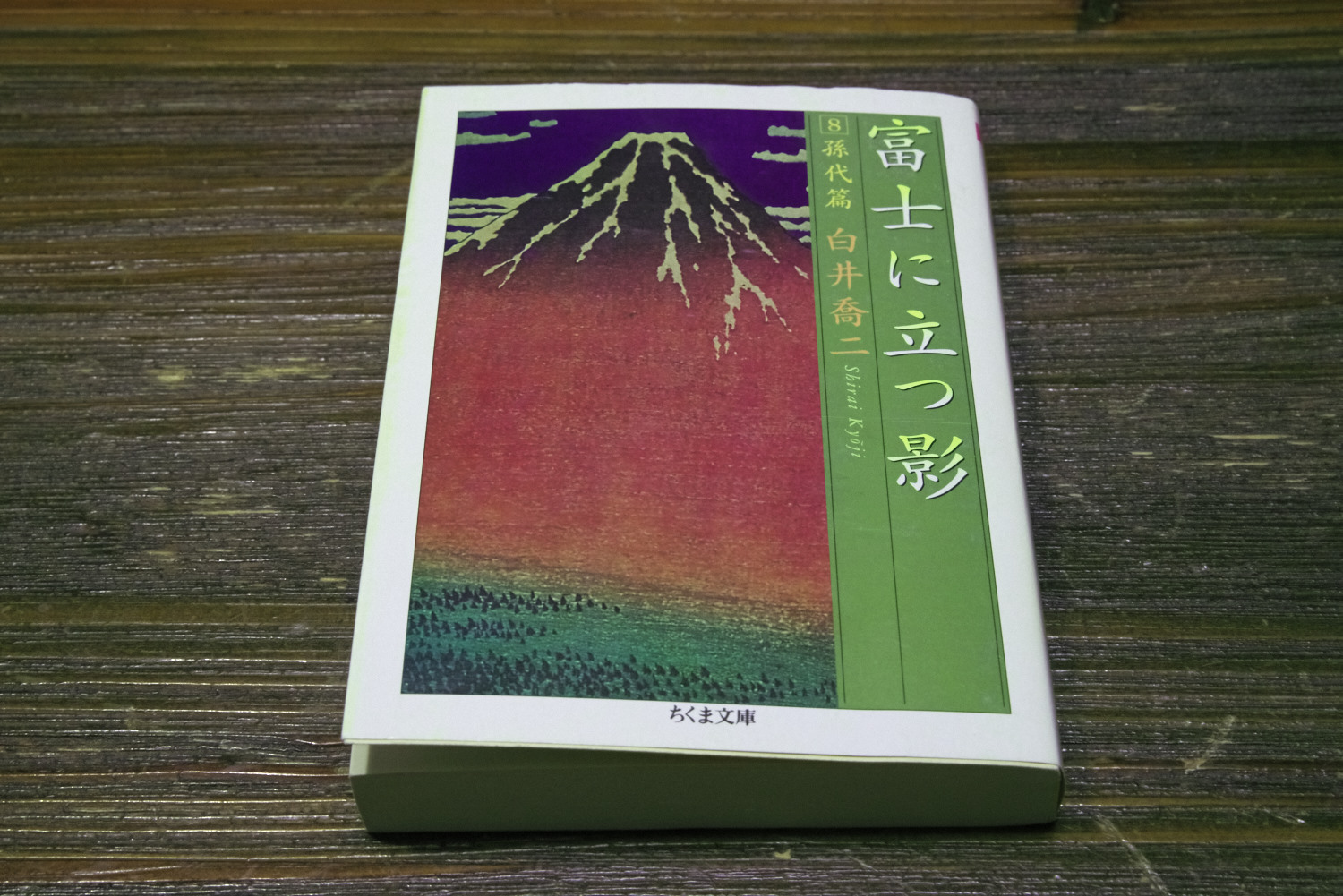 白井喬二の「富士に立つ影」第八巻、孫代篇を読了。佐藤兵之助とお園の子、兵吾は武士を憎み、職人とし生きるため、船大工の鳥ノ居頼吉の元で修行に励んでいます。しかし、頼吉がふとしたことで、黒船建造についての論争で敗れてしまい、船大工を辞めることになったため、結局侠客の上冊吉兵衛の元に身を寄せることになります。その吉兵衛が、ある足が不具である侍が敵討ちに襲われるのを守ることになり、兵吾もその役目を果たしますが、その侍は実は兵吾の実の父親である佐藤兵之助でした。兵之助は熊木公太郎を鉄砲で撃って殺害した時に、自身も公太郎の知り合いの猟師の銃の弾を膝に受けて、不具者になってしまっていました。兵吾はふとした弾みから、守っている侍が実の父であることを知り、ようやく親子の対面を果たします。
白井喬二の「富士に立つ影」第八巻、孫代篇を読了。佐藤兵之助とお園の子、兵吾は武士を憎み、職人とし生きるため、船大工の鳥ノ居頼吉の元で修行に励んでいます。しかし、頼吉がふとしたことで、黒船建造についての論争で敗れてしまい、船大工を辞めることになったため、結局侠客の上冊吉兵衛の元に身を寄せることになります。その吉兵衛が、ある足が不具である侍が敵討ちに襲われるのを守ることになり、兵吾もその役目を果たしますが、その侍は実は兵吾の実の父親である佐藤兵之助でした。兵之助は熊木公太郎を鉄砲で撃って殺害した時に、自身も公太郎の知り合いの猟師の銃の弾を膝に受けて、不具者になってしまっていました。兵吾はふとした弾みから、守っている侍が実の父であることを知り、ようやく親子の対面を果たします。
一方、佐藤兵之助の正妻の子である光之助は幕府の品川への砲台建設の現場に採用されて、工事資材の監督をしています。光之助は、元々城太郎というのですが、熊木公太郎の息子も城太郎というのを知って光之助に改名しようとします。そうこうしている内に、佐藤菊太郎は老齢のためついに命を落とします。
また、熊木公太郎の息子である熊木城太郎ですが、公太郎に似た鷹揚な性格に見えて父親とは異なっており、特に二重人格というか躁鬱病みたいな所があって、「勝番」と呼んでいる調子の良い時は、武術で師範を負かしてしまう程の腕になるのですが、「負番」と呼ぶ調子の悪い時には、素人にさえ負けてしまいます。この熊木城太郎が、公太郎の親友であった大竹源五郎の助けを借りて、佐藤兵之助を親の仇としてつけねらいますが、「負番」の時が多くて、なかなかうまくいきません。そうこうしている内に、大竹源五郎は、公太郎の妻であった貢に惚れてしまった自分を恥じて、とうとう自殺してしまいます。それを知らずに、熊木城太郎はある日「勝番」になった勢いをもって、ついに佐藤兵之助と佐藤光之助の親子が会談している場所に踏みこんで仇を討とうとします…
