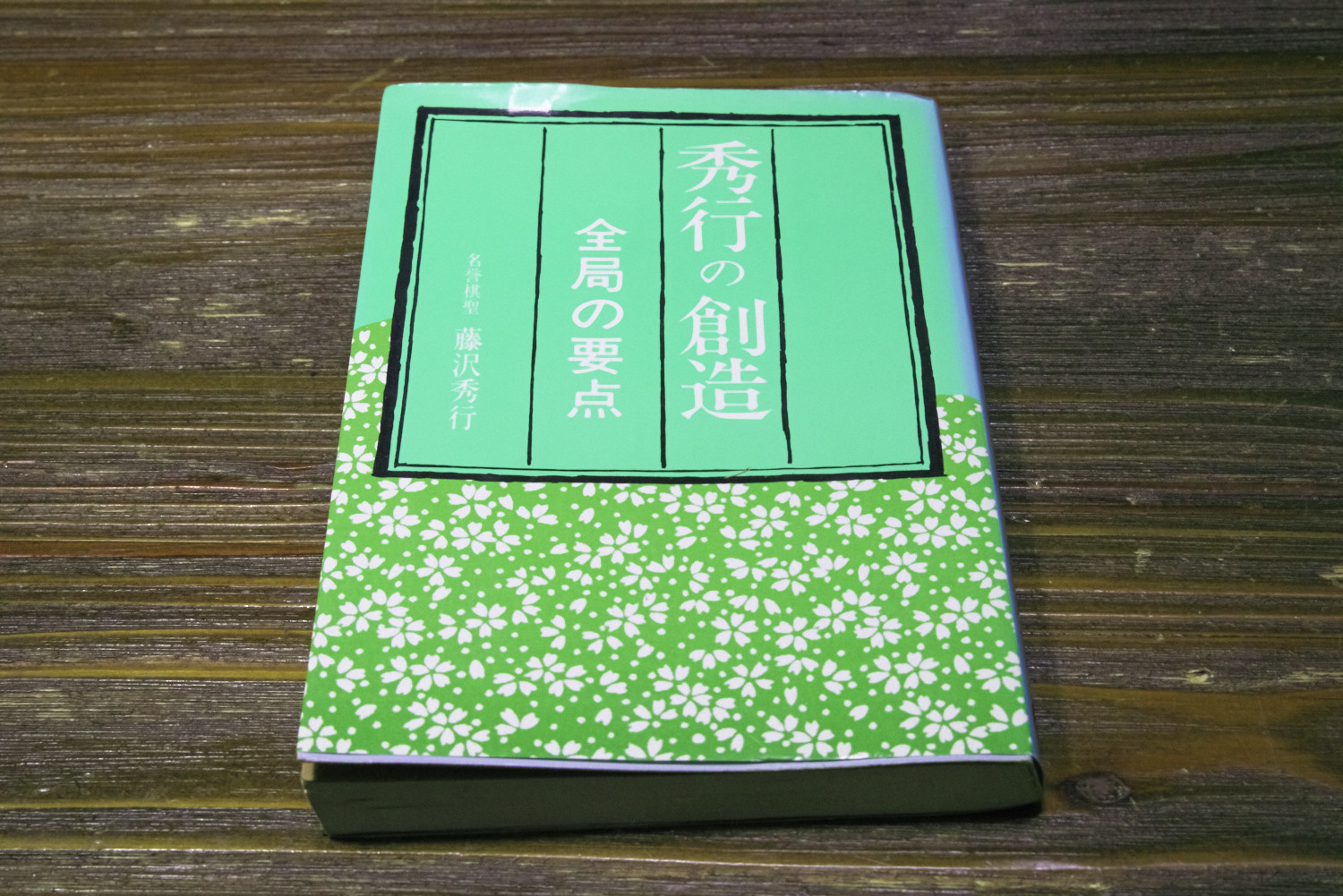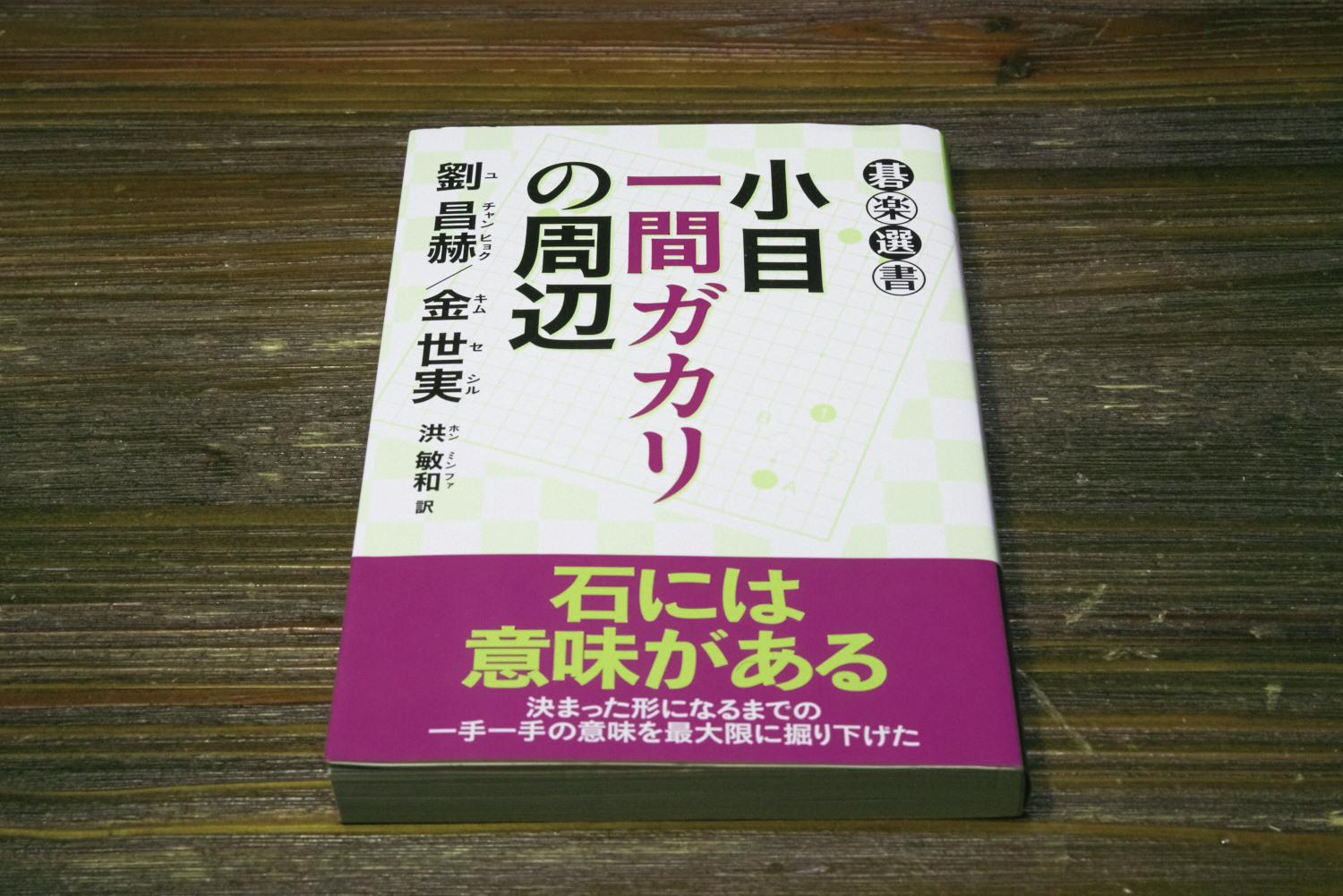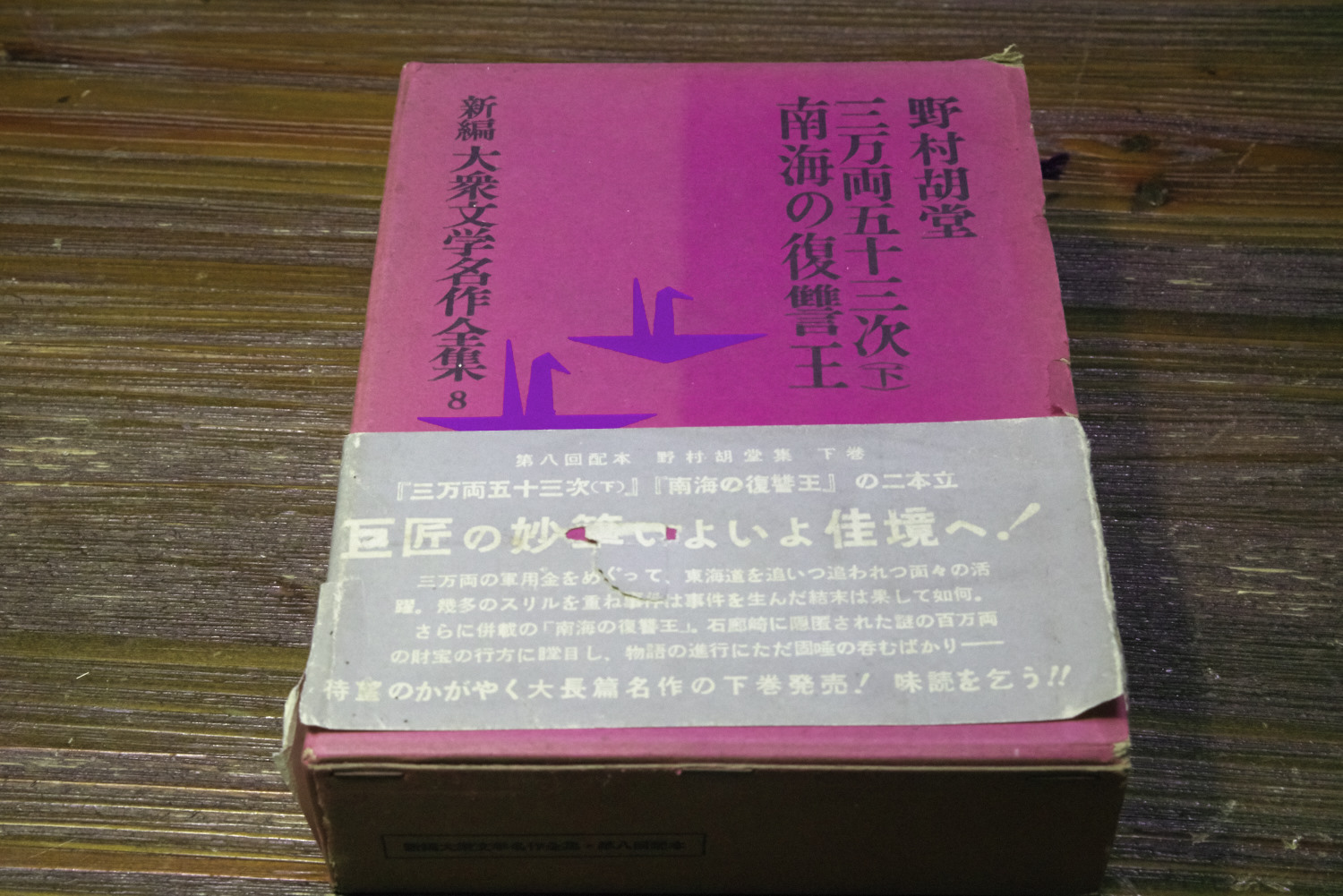 野村胡堂の「南海の復讐王」を読了。これはもう、野村版の「巌窟王」(モンテ・クリスト伯)です。悪者のため、実の父は食を自ら断って餓死、育ての養父は追い詰められ自害、母親は捕らわれの身になって自害、実の兄は拷問を受け死亡、許嫁は育ての養父の命を救うため、敵の息子の妻になってしまい、という中々すさまじい設定。それで主人公は捕まって孤島の岩牢に入れられ、とこれまた巌窟王と同じ。その岩牢から脱牢し、顔を長崎のオランダ人に変えさせ、琉球に渡り、その後琉球の王かつ琉球の商人に化けて江戸にやってきて、復讐をする話です。米相場で儲けようとする敵に、米を安く江戸に持ち込んで損をさせる、というのは「雪之丞変化」でも出てきました。なかなか読ませる話で、野村胡堂は「銭形平次」だけではないということです。
野村胡堂の「南海の復讐王」を読了。これはもう、野村版の「巌窟王」(モンテ・クリスト伯)です。悪者のため、実の父は食を自ら断って餓死、育ての養父は追い詰められ自害、母親は捕らわれの身になって自害、実の兄は拷問を受け死亡、許嫁は育ての養父の命を救うため、敵の息子の妻になってしまい、という中々すさまじい設定。それで主人公は捕まって孤島の岩牢に入れられ、とこれまた巌窟王と同じ。その岩牢から脱牢し、顔を長崎のオランダ人に変えさせ、琉球に渡り、その後琉球の王かつ琉球の商人に化けて江戸にやってきて、復讐をする話です。米相場で儲けようとする敵に、米を安く江戸に持ち込んで損をさせる、というのは「雪之丞変化」でも出てきました。なかなか読ませる話で、野村胡堂は「銭形平次」だけではないということです。
カテゴリー: Book
野村胡堂の「三万両五十三次」(下)
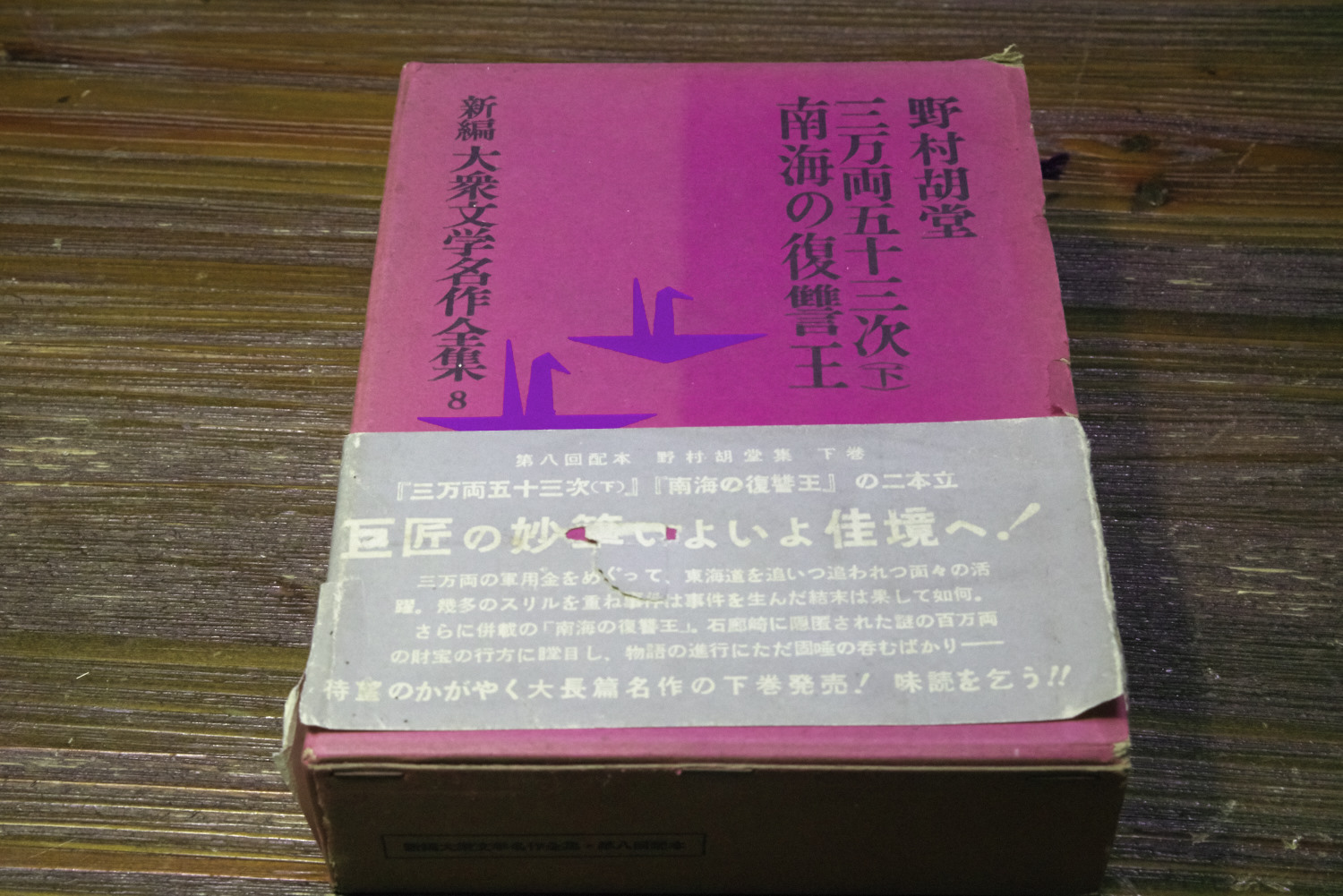 野村胡堂の「三万両五十三次」(下)を読了。東海道を京へと上っていく三万両を運ぶ旅は、その三万両がどこにあるのか、和泉屋のお蝶の花嫁行列の長持ちの中か、それとも馬場蔵人が運ぶ仏像の中か、この謎が解き明かされないまま、話はついに京を目前にした琵琶湖の瀬田まで引っ張られます。このお話に登場する美女4人の内、上巻では影が薄かった小百合は、この巻では比較的多く語られています。そして4人の中で作者が一番思い入れがありそうだった真琴は何と意外な展開が…(1952年にこの作品が映画化されていますが、その配役にこの「真琴」が出てこないのをいぶかしく思っていましたが、下巻を読んである程度納得しました。)
野村胡堂の「三万両五十三次」(下)を読了。東海道を京へと上っていく三万両を運ぶ旅は、その三万両がどこにあるのか、和泉屋のお蝶の花嫁行列の長持ちの中か、それとも馬場蔵人が運ぶ仏像の中か、この謎が解き明かされないまま、話はついに京を目前にした琵琶湖の瀬田まで引っ張られます。このお話に登場する美女4人の内、上巻では影が薄かった小百合は、この巻では比較的多く語られています。そして4人の中で作者が一番思い入れがありそうだった真琴は何と意外な展開が…(1952年にこの作品が映画化されていますが、その配役にこの「真琴」が出てこないのをいぶかしく思っていましたが、下巻を読んである程度納得しました。)
三万両を運ぶ馬場蔵人と、勤王の志士の矢柄城之介、最後はこの二人の知恵比べになりますが、最後に笑ったのは果たしてどちらか…
読み終わってみると、なかなかの快作だったように思います。作者は東海道を自動車で旅して取材するなど、かなりこの作品に対して準備して臨んでいます。
なお、大泥棒の牛若の金五が出てくるのは、なんとクルト・ワイルの「三文オペラ」の影響だそうです。この作者らしいです。
野村胡堂の「三万両五十三次」(上)
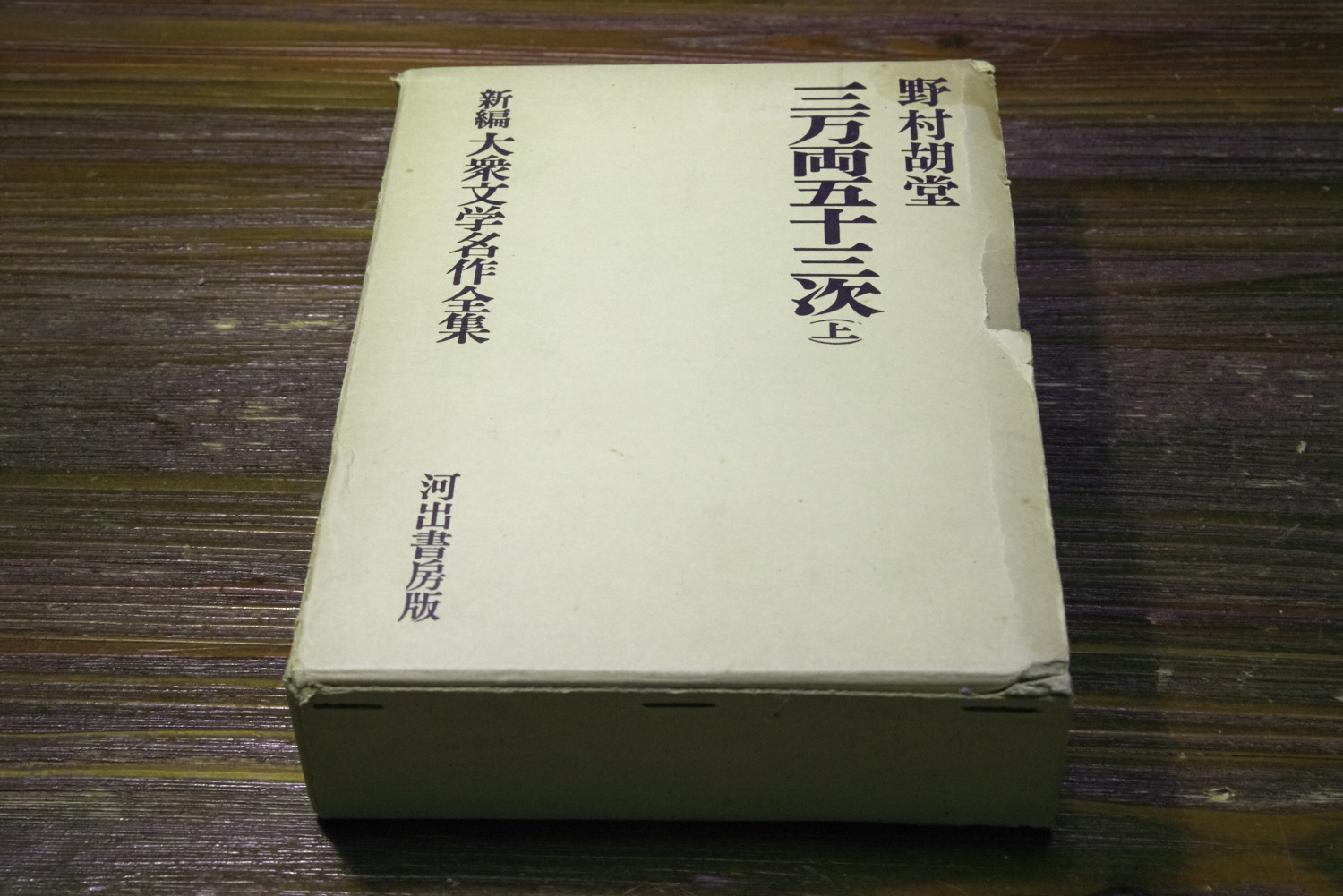 野村胡堂の「三万両五十三次」(上)を読了。この本を買ったのは、Amazonで「白井喬二」で検索したら出てきたので、てっきり白井喬二作品だと思って間違って買ったもの。現物が届いてみたら、白井喬二はこの全集の監修をしているだけでした。お話は、幕末に幕府の武士が京都の勤王の公家達を懐柔しようと、三万両という大金を持って東海道を旅して京都まで行こうとするのを、その三万両を途中で奪い取ろうとする勤王の志士達と、お蓮という女盗賊、元は盗賊だったが親父から頼まれて三万両の守護をすることになった牛若の金五、三万両の護送をカモフラージュするために、京都まで嫁入りの行列をするお蝶、そのお蝶を慕う千代松などが絡み合う話です。いわゆる「お宝の移動」物です。美女がたくさん出てきて、その盗賊のお蓮に加え、勤王の志士の妹の真琴、花嫁のお蝶、三万両を運んでいく馬場蔵人を父の仇とつけねらう小百合などです。上巻では小百合はかなり影が薄いです。箱根の関所の破り方が、作者が実際に現地検分してかなり詳しく記載されています。また、「名曲決定盤」の作者として知られるクラシック音楽好きだけあって、「最高音(ソプラノ)」、「交響曲(シンフォニィ)」といった単語がよく出てきます。ただ、話の進め方はちょっと冗長で、長すぎると感じます。下巻でどうなるか。
野村胡堂の「三万両五十三次」(上)を読了。この本を買ったのは、Amazonで「白井喬二」で検索したら出てきたので、てっきり白井喬二作品だと思って間違って買ったもの。現物が届いてみたら、白井喬二はこの全集の監修をしているだけでした。お話は、幕末に幕府の武士が京都の勤王の公家達を懐柔しようと、三万両という大金を持って東海道を旅して京都まで行こうとするのを、その三万両を途中で奪い取ろうとする勤王の志士達と、お蓮という女盗賊、元は盗賊だったが親父から頼まれて三万両の守護をすることになった牛若の金五、三万両の護送をカモフラージュするために、京都まで嫁入りの行列をするお蝶、そのお蝶を慕う千代松などが絡み合う話です。いわゆる「お宝の移動」物です。美女がたくさん出てきて、その盗賊のお蓮に加え、勤王の志士の妹の真琴、花嫁のお蝶、三万両を運んでいく馬場蔵人を父の仇とつけねらう小百合などです。上巻では小百合はかなり影が薄いです。箱根の関所の破り方が、作者が実際に現地検分してかなり詳しく記載されています。また、「名曲決定盤」の作者として知られるクラシック音楽好きだけあって、「最高音(ソプラノ)」、「交響曲(シンフォニィ)」といった単語がよく出てきます。ただ、話の進め方はちょっと冗長で、長すぎると感じます。下巻でどうなるか。
藤沢秀行名誉棋聖の「秀行の創造 全局の要点」
趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国 治勲の爆笑人生相談室 3」
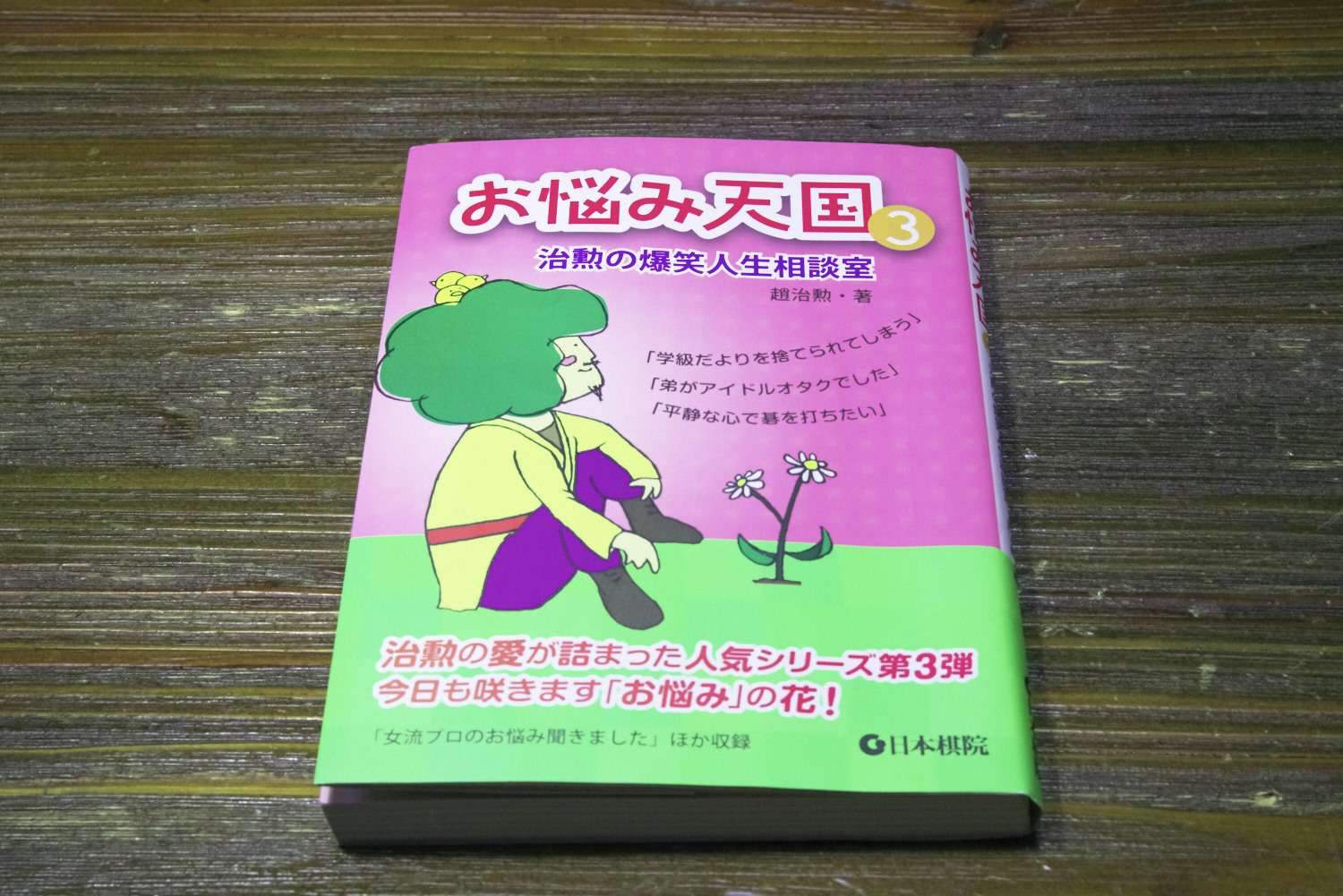 趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国 治勲の爆笑人生相談室 3」を読了。結局三冊全部読んでしまいました。この巻には、いつも趙治勲さんがいじりのネタにしている石田芳夫二十四世本因坊が登場。治勲さんの悪口を全部許した上で、治勲さんが石田芳夫二十四世本因坊をいじるは、木谷一門での治勲さんの先輩の中で甘えられるのがもう石田さんだけだから、ということです。ちょっと感動的です。木谷一門というのは木谷実9段の弟子のことで、「木谷道場」と呼ばれる内弟子生活を送った棋士の総称です。一時は7大タイトルを一門で独占し、一門で取った7大タイトルの数は全部で146にもなります。そうやって若い時を一緒に囲碁修行をした先輩後輩の仲をずっと保ち続けるというのも素晴らしくうらやましいことだと思います。
趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国 治勲の爆笑人生相談室 3」を読了。結局三冊全部読んでしまいました。この巻には、いつも趙治勲さんがいじりのネタにしている石田芳夫二十四世本因坊が登場。治勲さんの悪口を全部許した上で、治勲さんが石田芳夫二十四世本因坊をいじるは、木谷一門での治勲さんの先輩の中で甘えられるのがもう石田さんだけだから、ということです。ちょっと感動的です。木谷一門というのは木谷実9段の弟子のことで、「木谷道場」と呼ばれる内弟子生活を送った棋士の総称です。一時は7大タイトルを一門で独占し、一門で取った7大タイトルの数は全部で146にもなります。そうやって若い時を一緒に囲碁修行をした先輩後輩の仲をずっと保ち続けるというのも素晴らしくうらやましいことだと思います。
南條範夫の「月影兵庫 上段霞切り」
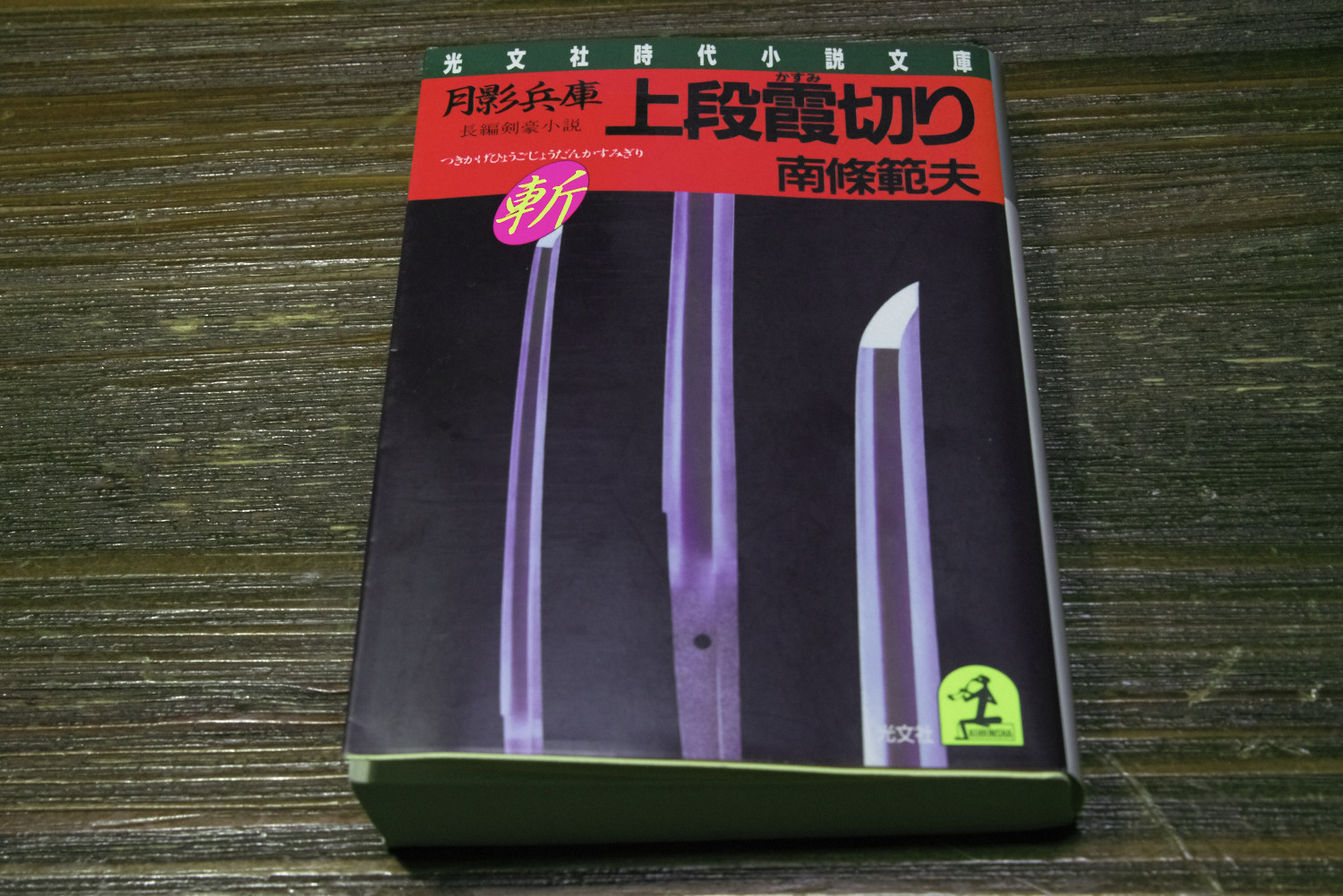 南條範夫の「月影兵庫 上段霞切り」を読了。南條範夫は1956年に直木賞を取った作家です。この月影兵庫はシリーズ化されており、これが第一作です。後にTVにもなっています。何となく「月影兵庫」という名前に聞き覚えがあるような気がするのはそのせいでしょうか。老中松平伊豆守信明の甥の月影兵庫は、次男坊で部屋住みの身ですが、十剣無統流という武芸の使い手で、剣だけでなく、薙刀も槍も柔術も剣法も何でもほぼ無敵というスーパー剣士です。この兵庫が、叔父の松平伊豆守が自己の保身のため将軍に献上しようとしていた、綾姫というお姫様が連れ去られてしまったのを、東海道を京まで旅して取り返そうとするお話です。明朗闊達な主人公、何故強いかよくわからないのに強い主人公の腕など、白井喬二の作品とも共通するものがあります。といっても、私はこのシリーズを続けて読もうと思うほどは魅力的には感じませんでしたけど。南條範夫にはこの間読んだ、「駿河城御前試合」のような武士道残酷物と呼ばれる一連の作品もありますが、そちらの方は益々私の趣味ではありません。
南條範夫の「月影兵庫 上段霞切り」を読了。南條範夫は1956年に直木賞を取った作家です。この月影兵庫はシリーズ化されており、これが第一作です。後にTVにもなっています。何となく「月影兵庫」という名前に聞き覚えがあるような気がするのはそのせいでしょうか。老中松平伊豆守信明の甥の月影兵庫は、次男坊で部屋住みの身ですが、十剣無統流という武芸の使い手で、剣だけでなく、薙刀も槍も柔術も剣法も何でもほぼ無敵というスーパー剣士です。この兵庫が、叔父の松平伊豆守が自己の保身のため将軍に献上しようとしていた、綾姫というお姫様が連れ去られてしまったのを、東海道を京まで旅して取り返そうとするお話です。明朗闊達な主人公、何故強いかよくわからないのに強い主人公の腕など、白井喬二の作品とも共通するものがあります。といっても、私はこのシリーズを続けて読もうと思うほどは魅力的には感じませんでしたけど。南條範夫にはこの間読んだ、「駿河城御前試合」のような武士道残酷物と呼ばれる一連の作品もありますが、そちらの方は益々私の趣味ではありません。
劉昌赫/金世実の「小目一間ガカリの周辺」
趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国 治勲の爆笑人生相談室」
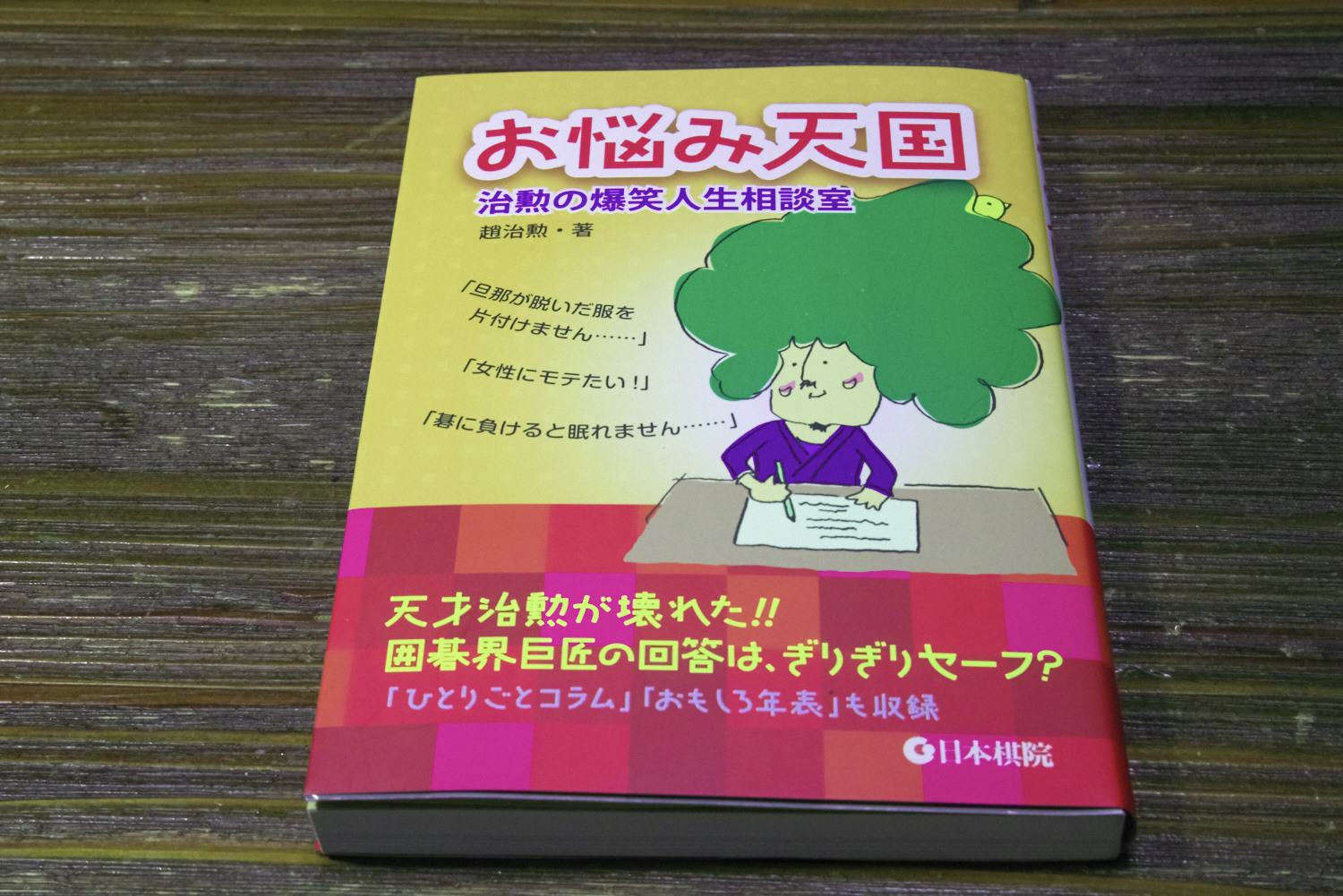 趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国 治勲の爆笑人生相談室」を読了。第2巻を試しに読んだらとても面白かったので、1巻と3巻もポチりました。この1巻も面白いです。「小林光一とは本当に仲が悪かったのですか」という質問に対して、色々書いた後で、「最後になりましたが、光一さん、名誉棋聖、名誉名人、名誉碁聖おめでとう。名誉本因坊もあれば最高だったね。なんで名誉本因坊がないんだろうねえ……」なんて書いています。小林光一名誉名人は、本因坊に4回挑戦しましたが、その相手が全部趙治勲さんで、その全てに負けたんです…
趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国 治勲の爆笑人生相談室」を読了。第2巻を試しに読んだらとても面白かったので、1巻と3巻もポチりました。この1巻も面白いです。「小林光一とは本当に仲が悪かったのですか」という質問に対して、色々書いた後で、「最後になりましたが、光一さん、名誉棋聖、名誉名人、名誉碁聖おめでとう。名誉本因坊もあれば最高だったね。なんで名誉本因坊がないんだろうねえ……」なんて書いています。小林光一名誉名人は、本因坊に4回挑戦しましたが、その相手が全部趙治勲さんで、その全てに負けたんです…
また、囲碁入門として紹介している張栩9段の「黒猫のヨンロ」、私もiPodで購入して(380円)、やってみましたが、なかなかいいですよ。囲碁を始めたい方にお勧め。
国枝史郎の「八ヶ嶽の魔神」
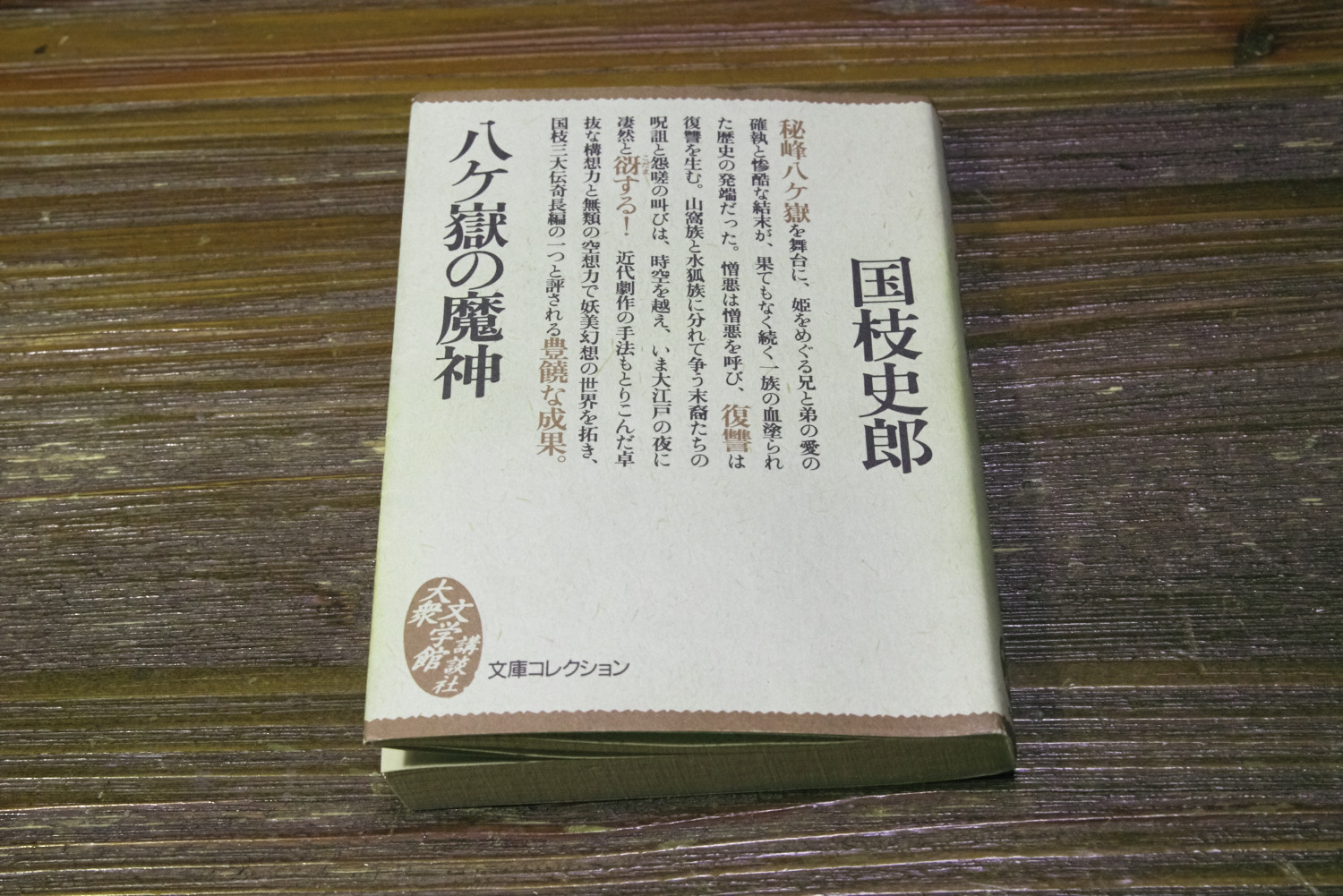 国枝史郎の「八ヶ嶽の魔神」を再読。前に読んだのは6年ぐらい前ですが、内容はほとんど忘れてしまっていました。国枝の三大傑作は「神州纐纈城」、「蔦葛木曽桟」とこの「八ヶ嶽の魔神」と言われています。その三作の中で、この作品だけが唯一完結しています。但し、完結しているといっても、一人の姫を巡って争った兄弟の兄の方の末裔が山窩族となり、弟と姫の間に出来た久田姫の末裔が水狐族となって双方が代々争っています。山窩族の血を引く主人公の鏡葉之助が、水狐族の長を倒した時に呪いを受け、永遠に不安を感じながら生き続けることになり、物語が書かれた大正時代の今も生きている、というのが果たして普通に言う結末と言えるかどうか。この作品も平凡社の現代大衆文学全集に収められています。というか国枝史郎だけで、三巻も割り当てられおり、国枝史郎が当時いかに人気が高かったかが窺えます。物語の印象としては、最後の方で葉之助と、淫祠邪教化した水狐族の、血で血を争う腥い戦い(葉之助の味方となった熊や狼や豹の猛獣が人間を食い殺すシーンもたくさんあります)の描写が実に国枝らしいです。
国枝史郎の「八ヶ嶽の魔神」を再読。前に読んだのは6年ぐらい前ですが、内容はほとんど忘れてしまっていました。国枝の三大傑作は「神州纐纈城」、「蔦葛木曽桟」とこの「八ヶ嶽の魔神」と言われています。その三作の中で、この作品だけが唯一完結しています。但し、完結しているといっても、一人の姫を巡って争った兄弟の兄の方の末裔が山窩族となり、弟と姫の間に出来た久田姫の末裔が水狐族となって双方が代々争っています。山窩族の血を引く主人公の鏡葉之助が、水狐族の長を倒した時に呪いを受け、永遠に不安を感じながら生き続けることになり、物語が書かれた大正時代の今も生きている、というのが果たして普通に言う結末と言えるかどうか。この作品も平凡社の現代大衆文学全集に収められています。というか国枝史郎だけで、三巻も割り当てられおり、国枝史郎が当時いかに人気が高かったかが窺えます。物語の印象としては、最後の方で葉之助と、淫祠邪教化した水狐族の、血で血を争う腥い戦い(葉之助の味方となった熊や狼や豹の猛獣が人間を食い殺すシーンもたくさんあります)の描写が実に国枝らしいです。
趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国② 治勲の爆笑人生相談室」
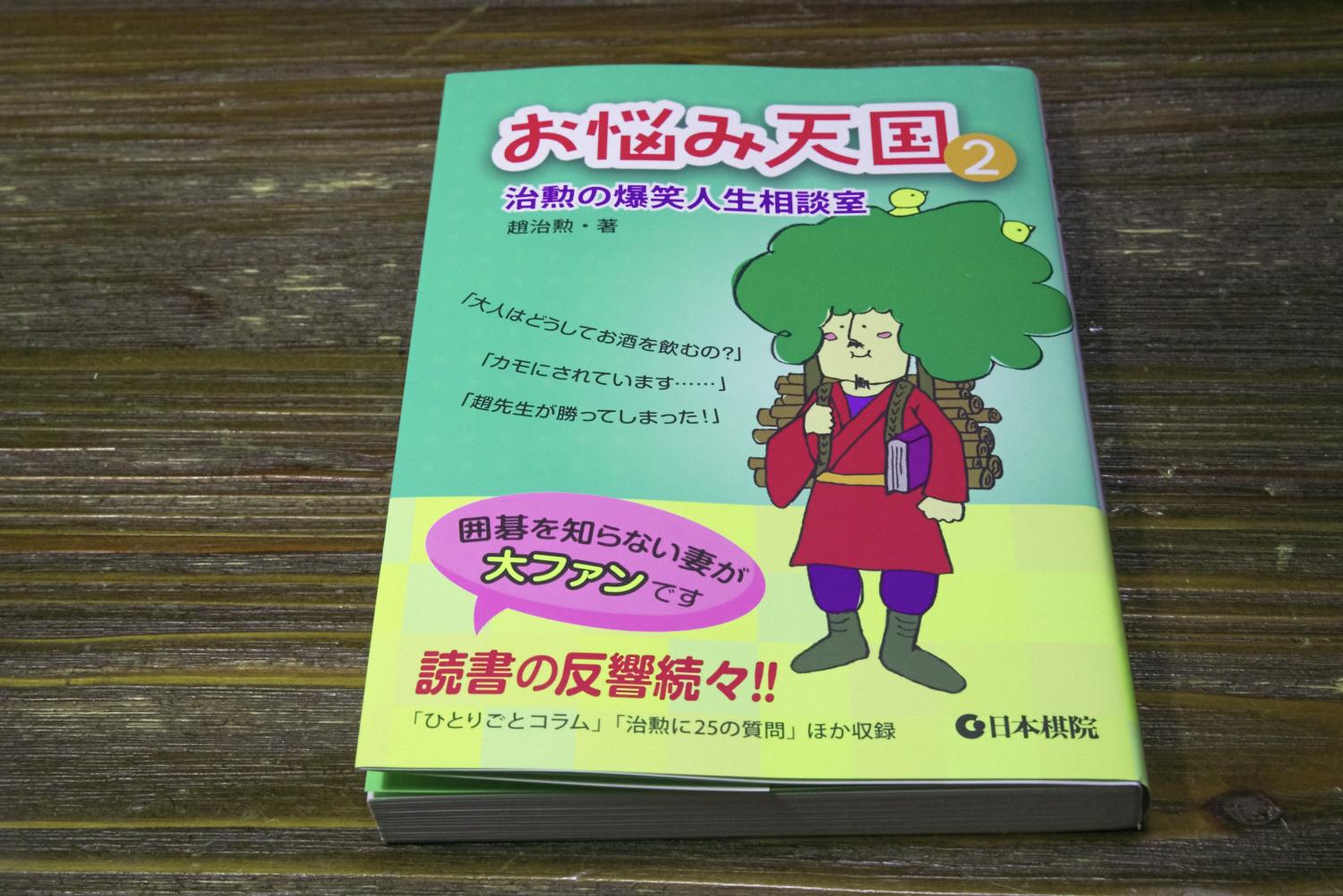 趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国② 治勲の爆笑人生相談室」を読了。週刊碁に連載されていたもの。(囲碁を知らない人はびっくりされるかもしれませんが、囲碁の週刊新聞があるんです。私も学生時代は毎週買っていました。碁の雑誌がほとんど無くなる一方で、週刊碁は今も出ています。)趙治勲さんのTVの碁での解説とか、各タイトル戦での挨拶とかとても面白いので有名ですが、文章の方でも爆笑ものです。あまり期待しないで買ってみましたが、とても面白いです。囲碁をまったく知らなくても問題なく楽しめます。囲碁を知っている人にはもっと面白く、小林光一とか張栩の悪口とか、山城宏日本棋院副理事が登場したりします。趙治勲さんは、現時点で棋士の中でもっとも多数のタイトルを獲得した人で、もう還暦を迎えられていますが、現在でも第一線の棋士として活躍中です。
趙治勲名誉名人・二十五世本因坊の「お悩み天国② 治勲の爆笑人生相談室」を読了。週刊碁に連載されていたもの。(囲碁を知らない人はびっくりされるかもしれませんが、囲碁の週刊新聞があるんです。私も学生時代は毎週買っていました。碁の雑誌がほとんど無くなる一方で、週刊碁は今も出ています。)趙治勲さんのTVの碁での解説とか、各タイトル戦での挨拶とかとても面白いので有名ですが、文章の方でも爆笑ものです。あまり期待しないで買ってみましたが、とても面白いです。囲碁をまったく知らなくても問題なく楽しめます。囲碁を知っている人にはもっと面白く、小林光一とか張栩の悪口とか、山城宏日本棋院副理事が登場したりします。趙治勲さんは、現時点で棋士の中でもっとも多数のタイトルを獲得した人で、もう還暦を迎えられていますが、現在でも第一線の棋士として活躍中です。