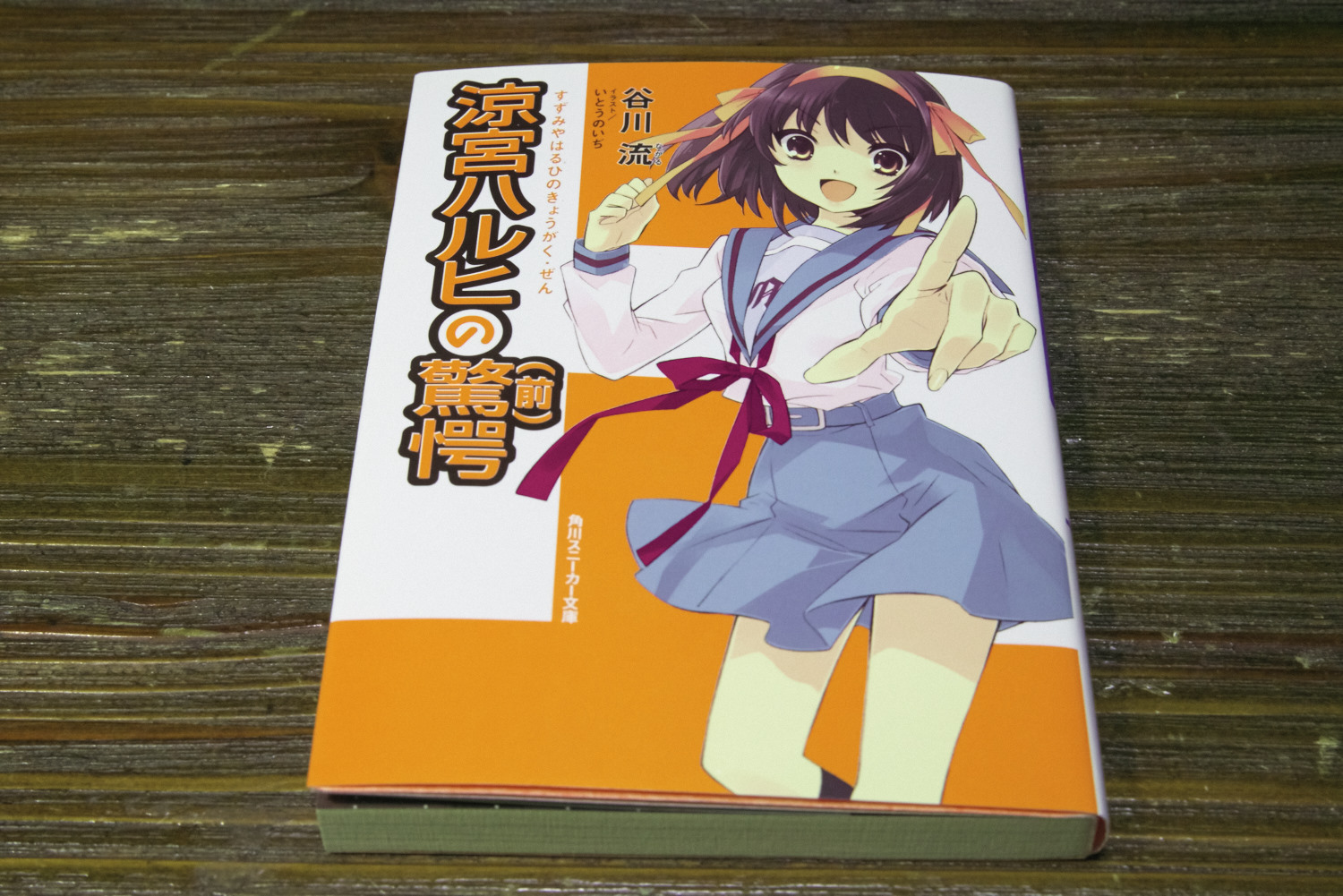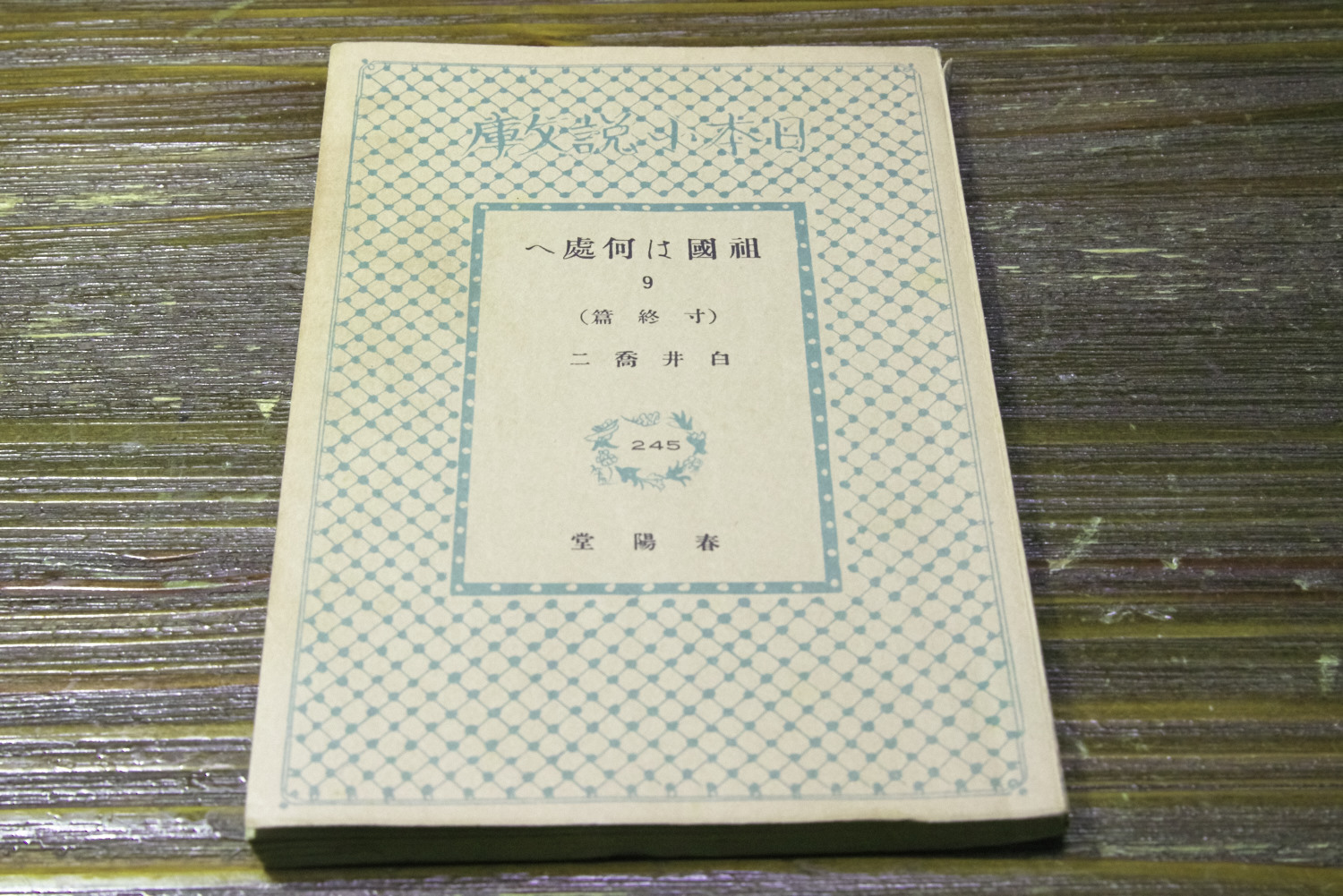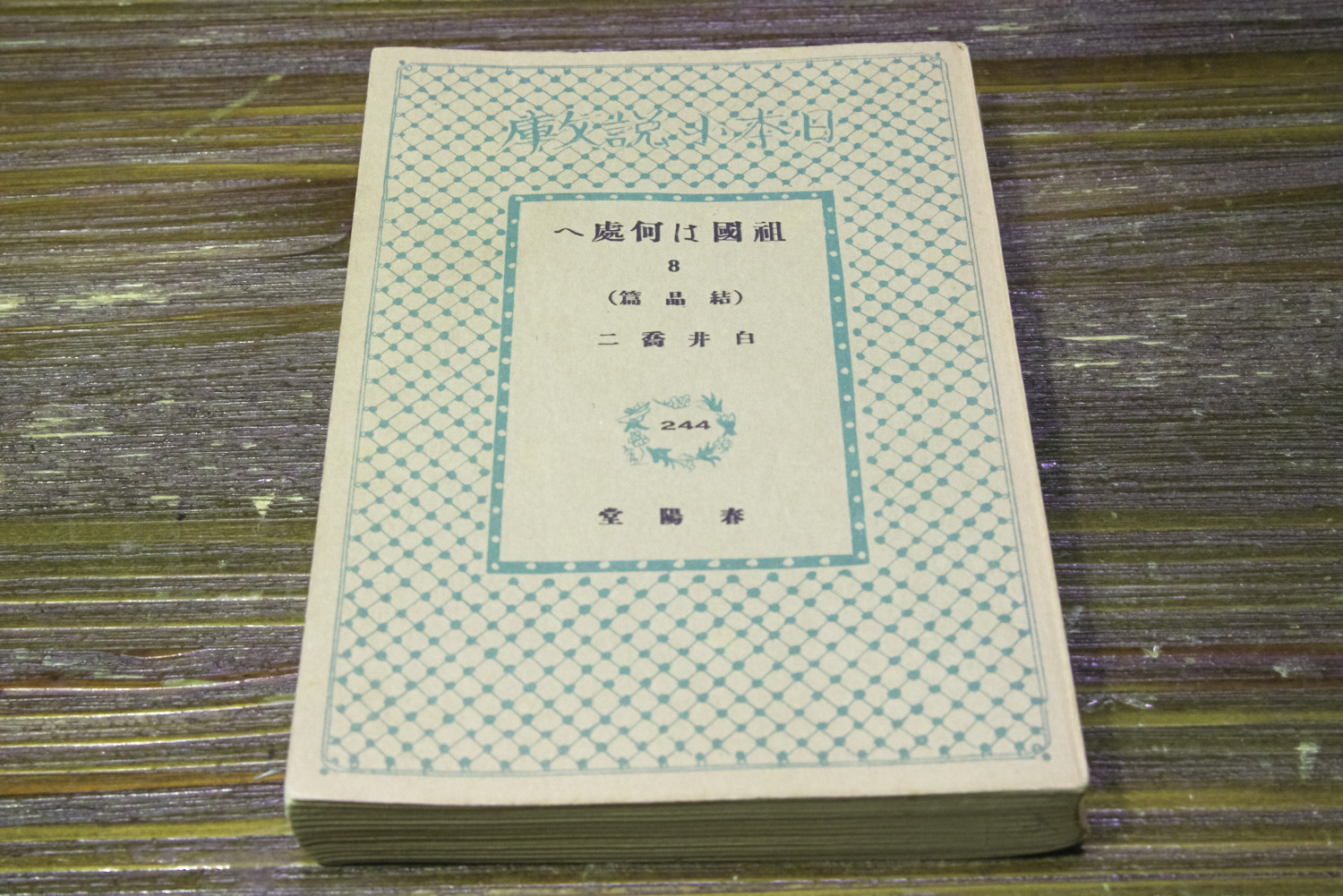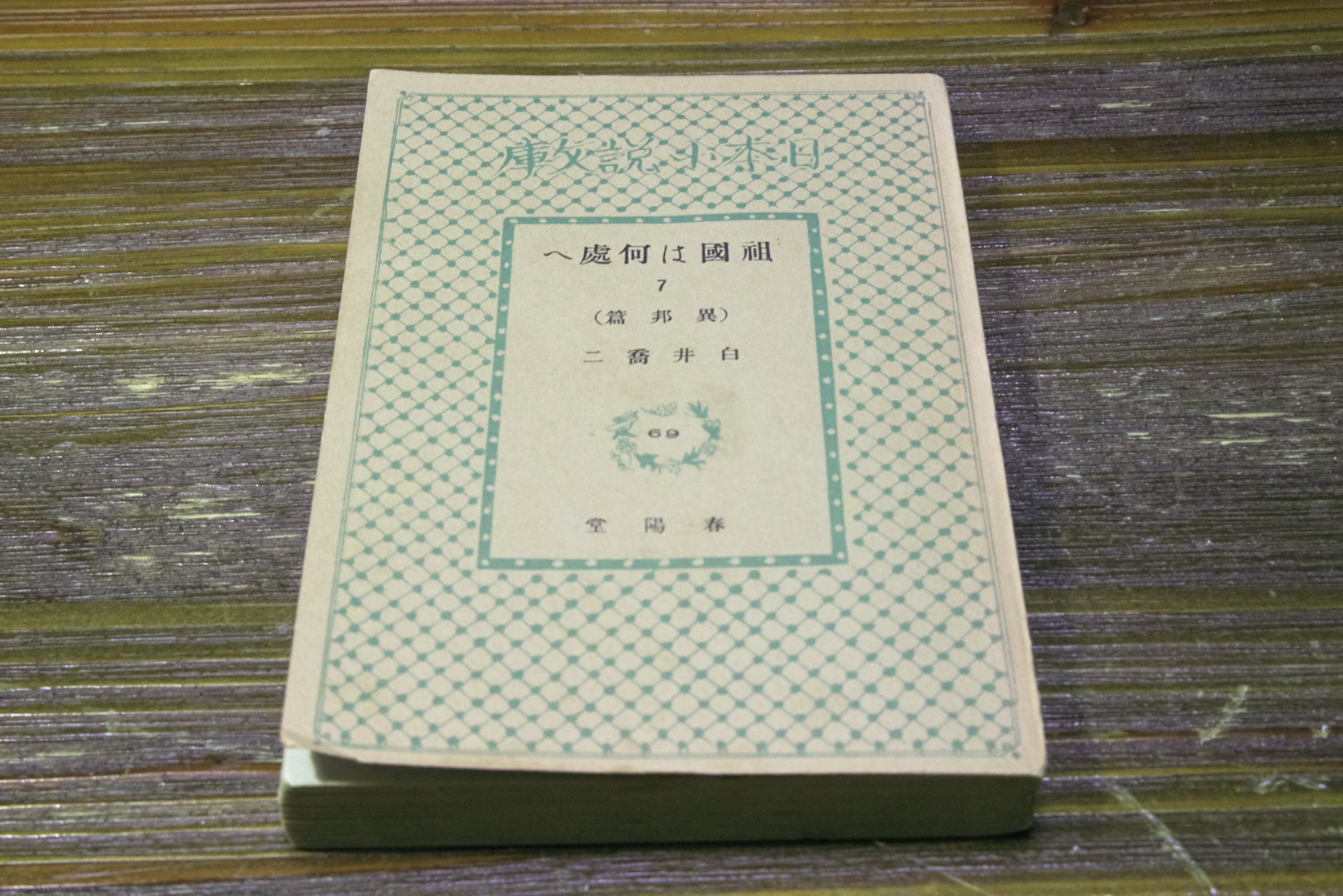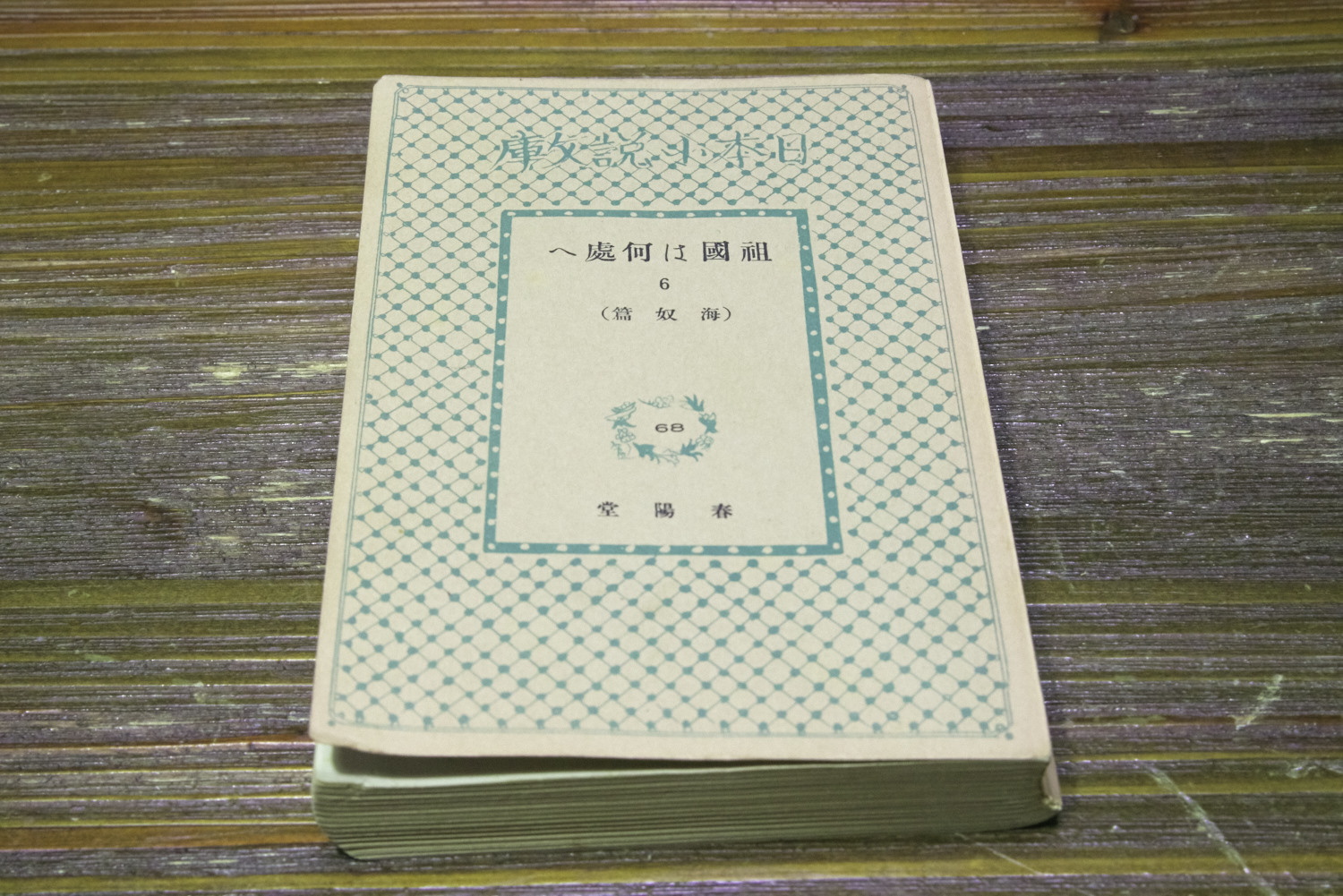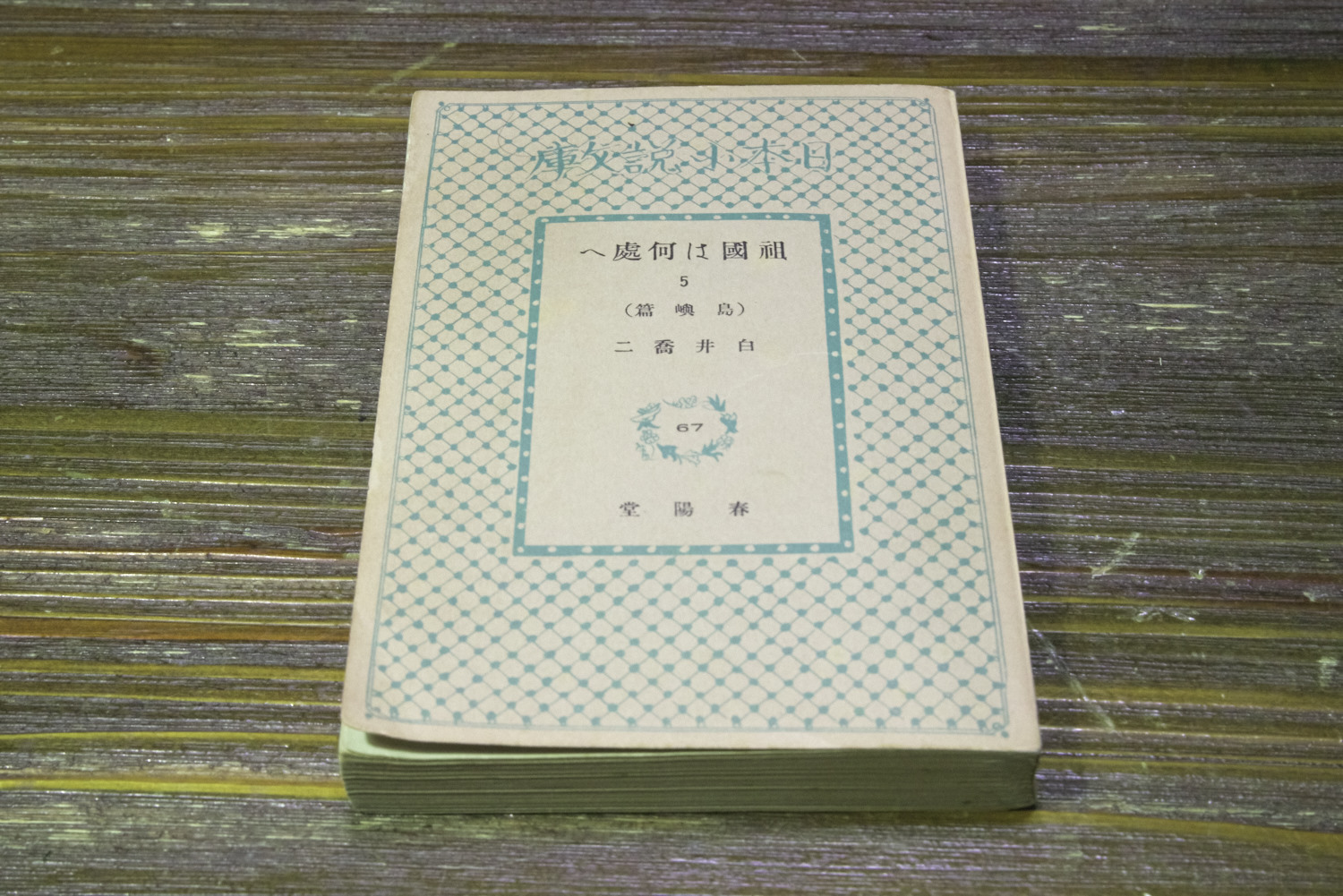このブログにおける小林信彦作品へのエントリーのリンク集です。
袋小路の休日
虚栄の市(1)
虚栄の市(2)
虚栄の市(3)
冬の神話
監禁
日本橋バビロン
汚れた土地-我がぴかれすく
大統領の晩餐
丘の一族
夢の砦
衰亡記
極東セレナーデ
ドジリーヌ姫の優雅な冒険
唐獅子株式会社、唐獅子源氏物語
コラムの冒険 -エンタテインメント時評 1992~95
消えた動機
小説世界のロビンソン
パパは神様じゃない
素晴らしい日本野球
地獄の読書録
神野推理氏の華麗な冒険
ぼくたちの好きな戦争
地獄の映画館
超人探偵
変人十二面相
地獄の観光船
オヨヨ大統領の悪夢
一少年の観た<聖戦>
オヨヨ島の冒険
時代観察者の冒険
ビートルズの優しい夜
怪人オヨヨ大統領
オヨヨ城の秘密
名人 志ん生、そして志ん朝
セプテンバー・ソングのように 1946-1989
大統領の密使
合言葉はオヨヨ
秘密指令オヨヨ
怪物がめざめる夜
背中合わせのハート・ブレイク
紳士同盟、紳士同盟ふたたび
イエスタデイ・ワンス・モア
イエスタデイ・ワンス・モアPart2 ミート・ザ・ビートルズ
世界でいちばん熱い島
サモアン・サマーの悪夢
私説東京放浪記
ドリーム・ハウス
つむじ曲がりの世界地図
小説探検
ハートブレイク・キッズ
イーストサイド・ワルツ
ムーン・リヴァーの向こう側
新編 われわれはなぜ映画館にいるのか
裏表忠臣蔵
結婚恐怖
本は寝ころんで
東京少年
<超>読書法
私説東京繁昌記
流される
兩國橋(家の旗)
決壊
和菓子屋の息子 -ある自伝的試み-
四重奏 カルテット
横溝正史読本
決定版 日本の喜劇人