続けて、ヴェーバーの「ローマ農業史 国法と私法への意味付けにおいて」の日本語訳プロジェクトを開始します。
カテゴリー: Book
「中世合名・合資会社成立史」のKindle版販売開始
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳ですが、出来るだけ色々なフォーマットで読めた方がいいかと思い、AmazonでKindle版の提供も始めました。
別にお金を取るつもりはなかったのですが、設定として$0というのは出来ず、最低価格の$0.99(今時点のレートで105円)になっています。
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳PDF
ヴェーバー「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳PDF版を公開
ヴェーバー「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳PDF版を公開しました。まだ校正中ですが取り敢えずWordフォーマットにし、訳者注を本文から分離して脚注にしました。また人名をカタカナ表記にしました。
相倉久人著、松村洋編著の「相倉久人にきく昭和歌謡史」
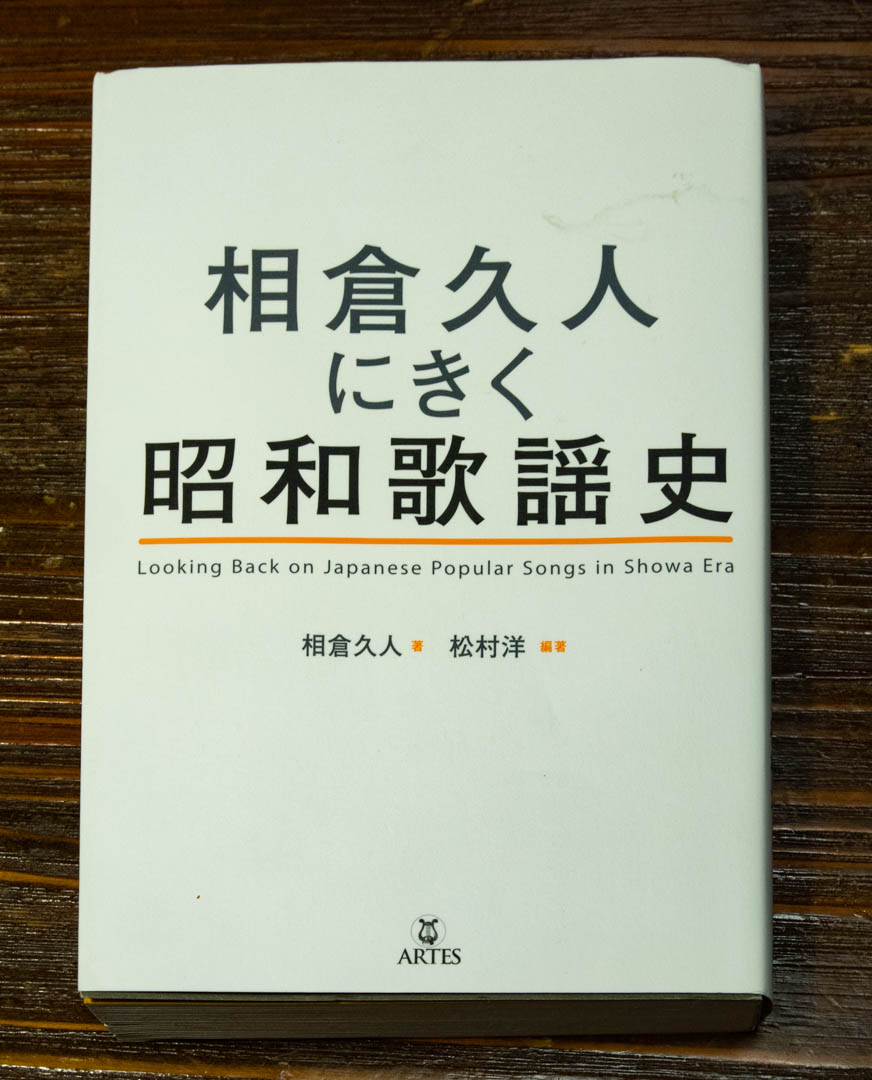 相倉久人著、松村洋編著の「相倉久人にきく昭和歌謡史」を読了。といっても読了したのはかなり前で、ここの所ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の翻訳に時間を取られて紹介する暇がありませんでした。
相倉久人著、松村洋編著の「相倉久人にきく昭和歌謡史」を読了。といっても読了したのはかなり前で、ここの所ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の翻訳に時間を取られて紹介する暇がありませんでした。
相倉久人さんは昭和6年生まれの昭和一桁なんで、戦前の音楽もよくご存知です。例によって古関裕而がきっかけになって古い昭和の音楽にはまり、青春歌年鑑というシリーズで昭和3年から私が生まれた1960年代初めまでを全部揃えてしまいました。
この本で良かったのはやはり戦前の所で、古関裕而の軍事歌謡も含めて当時どのように受け止められていたのか経験者の話が聴けたのは良かったです。またエノケンの歌の才能についてこの本で教えられてCDを買いました。それから戦後になって、美空ひばり、坂本九、クレージーキャッツくらいまでは楽しめました。山口百恵以降はもう同時代なんでそんなに新しい発見はないですが、ちあきなおみの「夜へ急ぐ人」のような隠れた名曲を教えてもらったのが良かったです。ずっとCDを色々聴きながら読んでいましたが、つくづく思うのが昔の歌手の歌の上手さ。昔はほとんどの歌手が音大か音楽専門学校で歌を学んだ人ばかりでした。それが1960年代にフォークソングが出てきて素人ばかりになりました。もちろん素人には素人の良さもありますが、私はやはりちあきなおみや弘田三枝子のような上手い歌手が好みです。
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳の第46回目公開(完結!)
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳の第45回目を公開
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳の第45回目を公開しました。
この箇所で注39に長いラテン語がありましたが、このラテン語は比較的分かりやすく、訳には苦労しませんでした。逆にドイツ語本文が結構分りにくかったです。ともかく後1回になりました。
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳の第44回目を公開
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳の第44回目を公開しました。ここでも合名会社における「連帯責任」を法的にどう取り扱って来たかという議論が延々と続きます。
後8ページで、取り敢えずの終了予定日は9月6~8日です。
我ながら良くここまでたどり着いたなあと思います。
ヴェーバーの日本語訳のタイトル変更「中世合名会社史」→「中世合名・合資会社成立史」
ヴェーバーの”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の邦訳のタイトルを「中世合名会社史」から「中世合名・合資会社成立史」に変更しました。詳しい理由はこちらをご覧ください。
菊地清麿の「評伝 古関裕而」
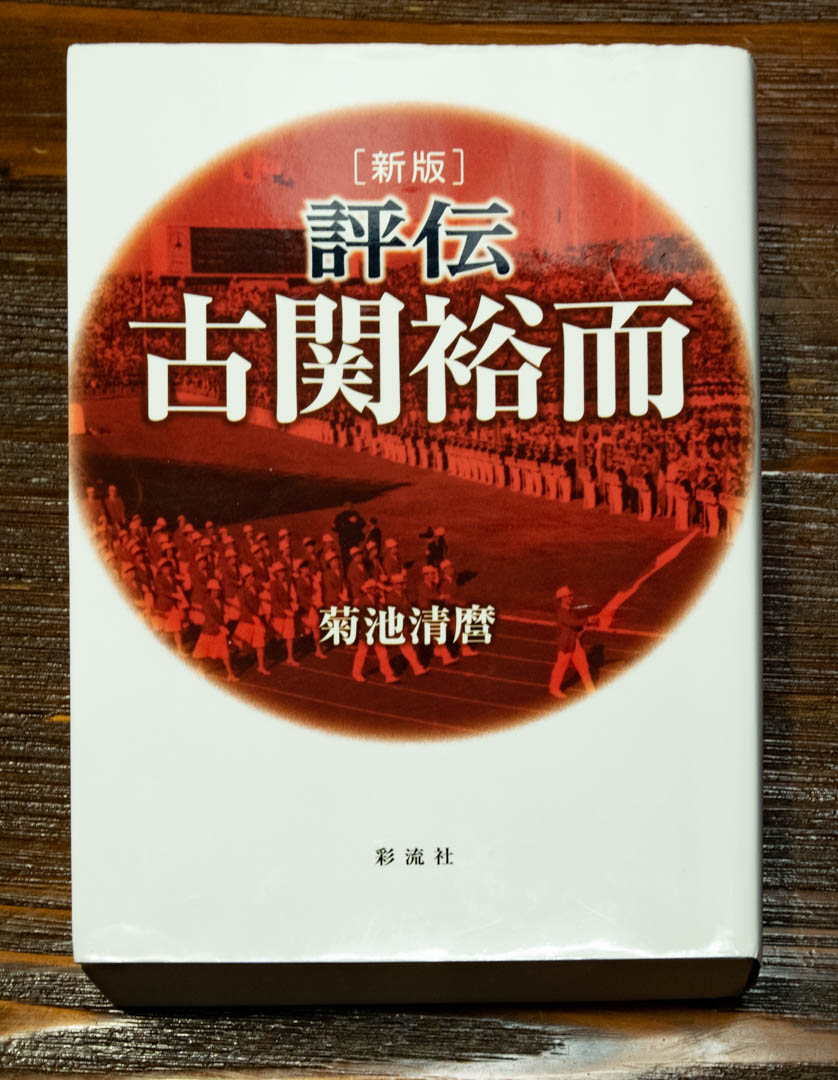 菊地清麿の「評伝 古関裕而」を読了。自伝とムック本を除いて、古関裕而に関する本はこれが5冊目です。これまで読んできた本で最大の不満点であった「古関裕而の音楽そのものへの分析がほとんどない」という点に関しては、この本はかなりの情報量を持っています。筆者は元々明治大学で古賀政男以来の伝統を持つマンドリンクラブにいた人のようで、昭和流行歌謡史が専門のようです。それはいいのですが、そういう長所を言う前にこの本の校正レベルの低さに辟易しました。ほとんど数ページに一箇所ぐらいの割合で校正ミスを発見します。また、とても信じられないような内容を書いている箇所も多数あり、例えば古関が奥さんの金子さんのために作曲したオペラ3作について「どの作品をとっても豊かな音楽性に溢れ、出演者の力量を十分に活かした作品だった」(P.233)と書いていますが、この人はそういうことを一体どうやって確認したのでしょうか。と言うのもこの3作のオペラについては録音テープがあったらしいのですが、アメリカに送られて行方不明と聞いており、これまでレコードもCDも出ておらず、おそらく放送もされていません。また1960年生まれということなので実演を聴いたということもあり得ません。つまりは聴いても(観ても)いない音楽で適当なことを書く人なのだということです。また、古賀政男がコロンビアから首にされたと書いている所もありますが、実際はテイチクに好条件で引き抜かれたのであって、コロンビアは古賀を訴えています。首にした者を訴える筈がありません。という具合で、ともかく色んな情報があるのはいいのですが、かなりの部分が記憶にだけ頼って書き飛ばしている感じで、一つ一つ他の資料で確認しないととてもそのまま信じる気にはなりません。筆者は大学で講師として教えているそうですが、その割りには日本語も変な箇所が沢山あります。ともかく残念な本でした。
菊地清麿の「評伝 古関裕而」を読了。自伝とムック本を除いて、古関裕而に関する本はこれが5冊目です。これまで読んできた本で最大の不満点であった「古関裕而の音楽そのものへの分析がほとんどない」という点に関しては、この本はかなりの情報量を持っています。筆者は元々明治大学で古賀政男以来の伝統を持つマンドリンクラブにいた人のようで、昭和流行歌謡史が専門のようです。それはいいのですが、そういう長所を言う前にこの本の校正レベルの低さに辟易しました。ほとんど数ページに一箇所ぐらいの割合で校正ミスを発見します。また、とても信じられないような内容を書いている箇所も多数あり、例えば古関が奥さんの金子さんのために作曲したオペラ3作について「どの作品をとっても豊かな音楽性に溢れ、出演者の力量を十分に活かした作品だった」(P.233)と書いていますが、この人はそういうことを一体どうやって確認したのでしょうか。と言うのもこの3作のオペラについては録音テープがあったらしいのですが、アメリカに送られて行方不明と聞いており、これまでレコードもCDも出ておらず、おそらく放送もされていません。また1960年生まれということなので実演を聴いたということもあり得ません。つまりは聴いても(観ても)いない音楽で適当なことを書く人なのだということです。また、古賀政男がコロンビアから首にされたと書いている所もありますが、実際はテイチクに好条件で引き抜かれたのであって、コロンビアは古賀を訴えています。首にした者を訴える筈がありません。という具合で、ともかく色んな情報があるのはいいのですが、かなりの部分が記憶にだけ頼って書き飛ばしている感じで、一つ一つ他の資料で確認しないととてもそのまま信じる気にはなりません。筆者は大学で講師として教えているそうですが、その割りには日本語も変な箇所が沢山あります。ともかく残念な本でした。
