 荒川敏彦の「殻の中に住むものは誰か 『鉄の檻』的ヴェーバー像からの解放」を読了。「現代思想」の2007年の11月増刊号の「総特集 マックス・ウェーバー」の中の一篇です。ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の最後に出てくる”ein stahlhartes Gehäuse”は、アメリカの有名な社会学者のタルコット・パーソンズがこの論文を英訳した時に、”iron cage”(鉄の檻)と訳し、この「鉄の檻」という言葉が一人歩きし、ヴェーバーが変質して(初期のプロテスタンティズムの倫理が忘れ去られて)人々を縛り付けるものとなった資本主義をペシミスティックに捉えた、と理解されるようになりました。実際、ミッツマンという人は、ヴェーバーの伝記を出す時にタイトルを「鉄の檻」にしています。また日本の大塚久雄も、この論文の日本語訳を改訳する時に、最初の翻訳者である梶山力が「外枠」と訳していたのを、わざわざ「鉄の檻」に変更しました。明らかにパーソンズの英訳に影響されています。
荒川敏彦の「殻の中に住むものは誰か 『鉄の檻』的ヴェーバー像からの解放」を読了。「現代思想」の2007年の11月増刊号の「総特集 マックス・ウェーバー」の中の一篇です。ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の最後に出てくる”ein stahlhartes Gehäuse”は、アメリカの有名な社会学者のタルコット・パーソンズがこの論文を英訳した時に、”iron cage”(鉄の檻)と訳し、この「鉄の檻」という言葉が一人歩きし、ヴェーバーが変質して(初期のプロテスタンティズムの倫理が忘れ去られて)人々を縛り付けるものとなった資本主義をペシミスティックに捉えた、と理解されるようになりました。実際、ミッツマンという人は、ヴェーバーの伝記を出す時にタイトルを「鉄の檻」にしています。また日本の大塚久雄も、この論文の日本語訳を改訳する時に、最初の翻訳者である梶山力が「外枠」と訳していたのを、わざわざ「鉄の檻」に変更しました。明らかにパーソンズの英訳に影響されています。
ところが、このパーソンズの英訳が「誤訳」で、Gehäuse(ゲホイゼ)は、一般的は「ケース」「外装」「貝殻」などの意味であり、「檻」のように中に無理矢理何かを閉じ込めるというニュアンスはなく、むしろ逆に中のものが傷つかないように守る、というニュアンスが正しいのだそうです。つまりヴェーバーはここで確立した資本主義のシステムを、(1)その中に守られて生きていくしかない(2)しかしそこから外に出て行くことは難しい(死んでしまう)という両方のニュアンスを込めている、とのことです。
これはなかなか目から鱗が落ちる感じでした。たった一語の翻訳ですが、それの誤訳でヴェーバーのイメージががらっと変わってしまいますから、怖いと思います。
カテゴリー: Book
折原浩先生の「ヴェーバー『経済と社会』の再構成 トルソの頭」
 折原浩先生の「ヴェーバー『経済と社会』の再構成 トルソの頭」を読了。1996年に出版されたもの。1984年の冬学期から始まった東大駒場の教養学科と相関社会科学の大学院の合同演習で延々10年間をかけて、「理解社会学のカテゴリー」と「経済と社会」の旧稿部分の精読を進めた結果として発表されたものです。(私はその開始から2年半その演習に参加しています。)
折原浩先生の「ヴェーバー『経済と社会』の再構成 トルソの頭」を読了。1996年に出版されたもの。1984年の冬学期から始まった東大駒場の教養学科と相関社会科学の大学院の合同演習で延々10年間をかけて、「理解社会学のカテゴリー」と「経済と社会」の旧稿部分の精読を進めた結果として発表されたものです。(私はその開始から2年半その演習に参加しています。)
「マックス・ウェーバー基礎研究序説」の時に紹介したように、「経済と社会」の従来二部とされてきた旧稿部分は、従来のように「社会学の基礎概念」をそのカテゴリー論として読むべきではなく、(直接的には「ロゴス」誌に発表され「経済と社会」とは一見無縁に見える)「理解社会学のカテゴリー」をカテゴリー論として、つまり「頭」として読むべきだという仮説を提示し、なおかつ最初の編纂者であるマリアンネ・ヴェーバーとメルヒオール・パリュイが恣意的に並べた順番を本来のあるべき順番に戻す、という作業を、「前後参照句」(「以前論じたように」とか「後で詳しく論じる」のように、テキストの他の箇所への参照を示す句)を手がかりに、その参照が「内容的に」どこにつながるのか、ということを精読を通じて地道に解明したものです。この「前後参照句」は実は最初の編纂の際に、その時の順番に合わせるために、編纂者によって書き換えられている可能性もあり、その手が加えられた箇所も同時に抜き出していかないといけません。その結果、全体で409の前後参照句の内、「旧稿の中のどこにも該当部分が無い」(が「理解社会学のカテゴリー」にその該当部分がある)、「前後の参照方向が間違っている」ものが41発見されました。その一つ一つを逐一詳細に論理的に検証し、(1)確かに「頭」として「理解社会学のカテゴリー」が必須であること(2)どうテキストを並べ替えれば順番の辻褄が合うか、という作業を徹底して行ったものです。
この作業の結果、旧稿に欠けていた「頭」が蘇り、また間違った配列も正される、「経済と社会」の再編纂問題における、画期的な進歩を達成したのが、この本に収められている論文になります。この本に入っている論文は独訳され、「ヴェーバー全集」を編集しているチームにも送られました。その中心メンバーであるシュルフター教授も、折原説には一度は賛成し、問題は解決したかと思われましたが、問題はさらにもつれます。これについてはまた次の機会に紹介します。
「汚名挽回」は誤用ではない!

 「汚名挽回」が間違った表現だと言い張る人達がいます。ATOKも昔、JUST MEDDLERというお節介機能で「汚名挽回」と変換させると、「誤用で『汚名返上』が正しい」なんて馬鹿なメッセージを出していました。しかしその当時ATOKの企画に携わっていた私がその後強く抗議して(監修の先生とも相談の上)止めさせました。「劣勢を挽回する」というのが「劣勢を取り戻す」という意味ではなく、「劣勢状態を良い状態に回復させる」という意味であることを考えれば、「汚名挽回」も汚名の不名誉を雪いで良い方に持っていく、という意味であることは間違いありません。ググって見つけたサイトによると、1976年頃に、「汚名挽回」を誤用とする本が出て、それで広まったみたいです。つい最近では2月くらいの読売新聞の朝刊のコラムで「汚名挽回」を誤用と書いていました。
「汚名挽回」が間違った表現だと言い張る人達がいます。ATOKも昔、JUST MEDDLERというお節介機能で「汚名挽回」と変換させると、「誤用で『汚名返上』が正しい」なんて馬鹿なメッセージを出していました。しかしその当時ATOKの企画に携わっていた私がその後強く抗議して(監修の先生とも相談の上)止めさせました。「劣勢を挽回する」というのが「劣勢を取り戻す」という意味ではなく、「劣勢状態を良い状態に回復させる」という意味であることを考えれば、「汚名挽回」も汚名の不名誉を雪いで良い方に持っていく、という意味であることは間違いありません。ググって見つけたサイトによると、1976年頃に、「汚名挽回」を誤用とする本が出て、それで広まったみたいです。つい最近では2月くらいの読売新聞の朝刊のコラムで「汚名挽回」を誤用と書いていました。
「汚名挽回」が間違っていないというのの証明として「青空文庫」で「挽回」を検索すると、
頽勢を挽回する(5例くらい)
名誉を挽回する
皇運を挽回する
敗戦挽回の策
勇気を挽回する
人気を挽回する
荒地挽回
家産を元通りに挽回する
旧勢力を挽回する
勢力を挽回する
頽(くづれ)を挽回する
蹉跌を挽回する
家運を挽回する
悪い体勢を挽回する
財産を挽回する
家運を挽回する
衰勢を挽回する
などで、かなり多く「マイナスの状態」を示す言葉にくっついています。ここから見ても「挽回」が「取り戻す」という意味でないことは明白です。
「名誉挽回」も「名誉を取り戻す」という意味ではなく、ニュアンスとしては「(失われた)名誉を復活させる」という意味だと思います。
その「汚名挽回」誤用説について、そのきっかけになったという「死にかけた日本語」という本を入手してみました。編者の中に福田恆存が入っているんで、まさか福田恆存ほどの人が何を馬鹿なことを言っているのかと思っていましたが、中を確認したら「誤用」としているのは単なる素人の投書です。それもある人が朝日新聞で「汚名ばん回」とあったのを間違いと投書して、それを「そうだそうだ」と引用して投書しているもの。間違いだという根拠は「挽回は取り戻すという意味で、汚名を取り戻すのはおかしい」という、俗説きわまりないものです。なんでこんな素人の屁理屈が堂々とまかり通るようになったのか、そちらの方が不思議です。
白井喬二の「信長と鉄火裁判」
 白井喬二の「信長と鉄火裁判」を読了。大日本雄弁会講談社の「キング」の昭和9年8月号掲載。小説やエッセイと言うより、信長にまつわる逸話紹介という感じです。しかしながら、白井の日本逸話大事典にはこの話は出ていませんでした。お話は、信長の頃、「火起證」という裁判のやり方があって、それは古代の「盟神探湯」にも似ていて、裁判の両者に真っ赤に焼いた鉄棒や鉄板を握らせて、無事な方を勝ちとする、という今から見ると何とも不思議な判定方法です。この話では庄屋の甚兵衛と左介という者が争って、左介が池田信輝の被官だったので、裁く者が依怙贔屓で左介を勝ちとしようとしていたのに、たまたま信長が通りかかり、甚兵衛の代わりに焼けた鉄棒を握って何事もなく、甚兵衛を勝ちに導くという話です。
白井喬二の「信長と鉄火裁判」を読了。大日本雄弁会講談社の「キング」の昭和9年8月号掲載。小説やエッセイと言うより、信長にまつわる逸話紹介という感じです。しかしながら、白井の日本逸話大事典にはこの話は出ていませんでした。お話は、信長の頃、「火起證」という裁判のやり方があって、それは古代の「盟神探湯」にも似ていて、裁判の両者に真っ赤に焼いた鉄棒や鉄板を握らせて、無事な方を勝ちとする、という今から見ると何とも不思議な判定方法です。この話では庄屋の甚兵衛と左介という者が争って、左介が池田信輝の被官だったので、裁く者が依怙贔屓で左介を勝ちとしようとしていたのに、たまたま信長が通りかかり、甚兵衛の代わりに焼けた鉄棒を握って何事もなく、甚兵衛を勝ちに導くという話です。
折原浩先生の「マックス・ウェーバー基礎研究序説」
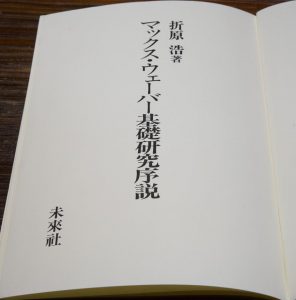 折原浩先生の「マックス・ウェーバー基礎研究序説」を読了。1986年に出た本です。この本が出た時私は既に就職していて、この本をその時に買っていて一度読んでいますが、その時はこの本の内容を十分に理解したとはとてもいえないものでした。今回、まずテンブルックの論文(ヴェーバーの「経済と社会」の編纂問題を初めて指摘した人)を読み、それからベンディクスの書いたヴェーバーの全体像に関する本を読み、更にシュルフターが書いたこの編纂問題に関するまとめを読んで、ときちんと順序を踏んで再度この本に挑み、ようやくその内容がちゃんと理解できるようになりました。
折原浩先生の「マックス・ウェーバー基礎研究序説」を読了。1986年に出た本です。この本が出た時私は既に就職していて、この本をその時に買っていて一度読んでいますが、その時はこの本の内容を十分に理解したとはとてもいえないものでした。今回、まずテンブルックの論文(ヴェーバーの「経済と社会」の編纂問題を初めて指摘した人)を読み、それからベンディクスの書いたヴェーバーの全体像に関する本を読み、更にシュルフターが書いたこの編纂問題に関するまとめを読んで、ときちんと順序を踏んで再度この本に挑み、ようやくその内容がちゃんと理解できるようになりました。
ヴェーバーの「経済と社会」はその妻マリアンネによって、1920年までにヴェーバー自身が校訂を済ませた部分と、第一次世界大戦前の1911年~1913年に渡って書かれ、戦争その他の理由で出版されることがなく草稿のままとなった「旧稿」(ヴェーバーはこの「旧稿」もきちんと改訂して用いる予定があったのだと思いますが、1920年に彼はスペイン風邪からによる肺炎で急死し、この作業を行うことはできず、またどのように全体を構成するかのメモも残されませんでした)の2つの部分に分かれています。マリアンネと、またこの「経済と社会」の再編纂を試みたヨハネス・ヴィンケルマンの両方が、1920年校訂版を第一部、旧稿を第二部とする二部構成を採用し、一部が理論や範疇論で、二部がその具体的な展開で、「宗教社会学」や「法社会学」といった「○○社会学」という個別的展開であるという構成を採用していました。また第一部の冒頭には「社会学の根本概念」が全体に対するカテゴリーを説明するとして置かれていました。
で、テンブルックはこの構成が嘘であり、ヴェーバーが意図したものではなく、「経済と社会」にもはやヴェーバーの主著としての価値はないとします。これに対し日本では折原浩先生、ドイツではヴォルフガング・シュルフターがテンブルックの二部構成批判に対しては賛成するものの、「経済と社会」の価値を否定せず、改めてあるべき構成を再構築しようとしてきました。
この折原浩先生の書は、その研究の初期に書かれたものです。先生は、東京大学で10年間の年月をかけて、「経済と社会」の旧稿の部分の精読を行って、その中に含まれる「参照指示」(「これまで我々が見てきたように」とか「後でもう一度議論することになるが」といった、別の箇所への参照を示す章句)を分析し、それを手がかりにあるべき全体構成を見出そうとします。また、マリアンネ版でカテゴリー論文として冒頭に置かれている「社会学の根本概念」の内容が、旧稿には適用できず、旧稿を読むためには1914年に書かれた「理解社会学のカテゴリー」の中の諸概念を使わなければならない、ということを検証しようとしました。
私は、この折原先生の10年間の検証作業の最初の2年半に一学生として参加しました。その時は最初に「理解社会学のカテゴリー」をきちんと読み直し、その後「法社会学」以下への解読へと進みました。そういう意味で私にとっても思い入れの深い内容です。
折原浩先生の研究はドイツ語で論文として何本か発表され、その後ドイツでヴェーバー全集の編集委員の一人として同じくこの問題に関わったヴォルフガング・シュルフター教授と論争していくことになりますが、今後それも追いかけていきます。
ドイツ科出身の新約聖書学者
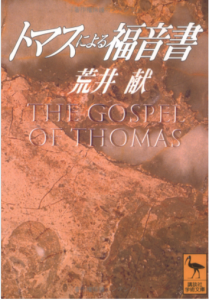 東大の駒場は日本の新約聖書研究では結構重要な役目を果たしています。内村鑑三の無教会派に属していた矢内原忠雄が1949年に教養学部長になり(今は無くなってしまったみたいですが、昔駒場キャンパスには矢内原門というのがありました)、後に東大総長になりますが、その時代に、私の出身学科である教養学科ドイツ科から3人の新約聖書学者が出ています。
東大の駒場は日本の新約聖書研究では結構重要な役目を果たしています。内村鑑三の無教会派に属していた矢内原忠雄が1949年に教養学部長になり(今は無くなってしまったみたいですが、昔駒場キャンパスには矢内原門というのがありました)、後に東大総長になりますが、その時代に、私の出身学科である教養学科ドイツ科から3人の新約聖書学者が出ています。
佐竹明 1953年卒
荒井献 1954年卒
八木誠一 1955年卒
この3人の内、荒井先生は私が学生の時に教養学科で教えられていて、私は半年だけですが、その授業を受けることが出来ました。その時の授業は「使徒行伝(使徒言行録)」が実際にはどのように成立したのかという内容でした。私の新約聖書に関する知識のかなりの部分はこの時に教えてもらったものです。その授業の中で、「死海文書」「クムラン教団」「エッセネ派」なんかも出てきました。(当時、イエス・キリストはエッセネ派の一員ではないかという説がありました。)後年、エヴァンゲリオンで死海文書が出てきた時はびっくりしましたが。
マイケル・ウォルフの「炎と怒り――トランプ政権の内幕」へのレビュー
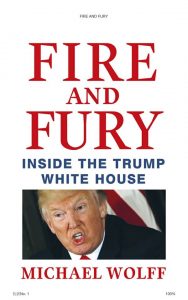 「炎と怒り」の日本語訳のAmazonレビューで、6件のカスタマーレビューの内、私の書いた以下のレビューが「役に立った」2018年3月23日現在71票で圧倒的トップ。
「炎と怒り」の日本語訳のAmazonレビューで、6件のカスタマーレビューの内、私の書いた以下のレビューが「役に立った」2018年3月23日現在71票で圧倒的トップ。
=====================================
まず、私はオリジナルの英語版を読みました。日本語訳の方は読んでいません。
また私はアンチ・トランプで、彼をサポートする気はありません。
しかし、一言申し上げたいのは、この本は「事実を淡々と描写し、その判断は読者に任せる」というスタイルではまるでなく、その正反対です。ほとんどの文章に過剰な程の形容詞や副詞、それもあまり聴いたことのないような奇妙なものが使われています。ここから分かるのは、作者は読者をある一定の印象に導こうとしている、ということです。もちろん、この本の中にあるように、トランプ陣営がお互いの対立から情報のリーク合戦を行ったのは多分事実でしょうから、それなりの事実は含まれていると思います。しかし、その事実をどう解釈するかという点で作者の誘導にそのまま引っかかるのはどうかと思います。
要は日本で言えば、週刊誌、それもあまり程度が高くないもののゴシップ記事だと思っていた方が間違いないと思います。
作者は「この本でトランプ政権は終わるだろう」と発言していますが、そもそもトランプ支持者がこの本を読むとは思えず、買っているのはほとんどアンチの人だと思います。そういう訳で、現在アメリカで起きているpolarization(2極化)の状況をよく考え、一方だけの情報に流されず、両方の情報を取るように努めた方がいいかと思います。アメリカのマスコミは保守陣営だけでなく、リベラル側もかなりおかしくなっています。
高森日佐志の「弔花を編む 歿後三十年、梶原一騎の周辺」
 高森日佐志の「弔花を編む 歿後三十年、梶原一騎の周辺」を読了。筆者は梶原一騎の実弟です。「ワル」の原作者の真樹日佐夫が梶原の実弟ということは知っていましたが、その下にさらに弟さんがいたことは知りませんでした。その三男の日佐志が実父高森龍夫や梶原一騎などについて思い出を書いたものです。
高森日佐志の「弔花を編む 歿後三十年、梶原一騎の周辺」を読了。筆者は梶原一騎の実弟です。「ワル」の原作者の真樹日佐夫が梶原の実弟ということは知っていましたが、その下にさらに弟さんがいたことは知りませんでした。その三男の日佐志が実父高森龍夫や梶原一騎などについて思い出を書いたものです。
まず梶原作品にイエス・キリストが登場する理由が分かりました。実父の高森龍夫は若い頃神学校で牧師を目指したほどのクリスチャンでした。しかし、周囲にはそれを隠し、葬儀の時にそれが明らかになって回りの者が驚いた、となっています。梶原一騎自身がクリスチャンだったとはどこにも書いてありませんが、一騎自身の葬式も最初仏式でやるかどうかもめて、結局父親と同じキリスト教式の葬儀になったそうです。
梶原の作品では、巨人の星の星一徹、柔道一直線の車周作のように、実力を持ちながら世に受け入れられない人物がかなりの迫真性をもって登場しますが、それは実父の龍夫の人生がそういうものだったからのようです。
また、梶原の自伝的漫画「男の星座」は、梶原が「巨人の星」で有名になる前に梶原の死により終わっていますが、この本ではその始まりの様子が書かれていました。講談社は漫画に吉川英治の「宮本武蔵」のような人間ドラマを持ち込もうとしていたとのことで、私は梶原作品に大衆文学のストーリーテリングの影響を感じるのはやはり間違っていなかったと思います。
またこれは遺族サイドからの証言なので割り引いて考えるべきでしょうが、梶原の晩年の裁判沙汰は、ショーケン(萩原健一)が覚醒剤で逮捕され、その黒幕が梶原一騎だと警察が思い込んで、無理矢理に案件を作り出して起訴した、とされています。元々梶原一騎自身は中学生の頃から掻っ払いや万引きを繰り返していて(梶原の中学生時代は戦後の混乱期で、大人も皆闇取引をやっていたり、風紀の乱れていた時代でした)、ずっと道徳家を装っていてそれが世間にばれたということではなく、以前も書きましたが、梶原自身は常に善と悪との間で揺れ動いていて悩み苦しんでいたのだと思います。最初の奥さんであった篤子さんも、梶原をそういう「複雑な人間」と描写しています。
ラインハルト・ベンディクス著、折原浩訳の「マックス・ウェーバー その学問の包括的一肖像」(上・下)
 ラインハルト・ベンディクス著、折原浩訳の「マックス・ウェーバー その学問の包括的一肖像」(上・下)を読了。原題は、”Max Weber: An Intellectual Portrait”で1960年が初出。日本語訳は同じく折原浩訳で1966年に中央公論社から一冊本で出ています。今回読んだのは、それを三一書房が上下二冊本として1987年に再版したものです。訳者の折原浩氏は私の大学の恩師です。著者のベンディクスは、1916年にドイツに生まれたユダヤ人の社会学者で、若い頃ナチスに対抗するユダヤ人組織に所属していましたが、1938年にアメリカに移住しています。1969年にアメリカの社会学会の会長に選ばれています。
ラインハルト・ベンディクス著、折原浩訳の「マックス・ウェーバー その学問の包括的一肖像」(上・下)を読了。原題は、”Max Weber: An Intellectual Portrait”で1960年が初出。日本語訳は同じく折原浩訳で1966年に中央公論社から一冊本で出ています。今回読んだのは、それを三一書房が上下二冊本として1987年に再版したものです。訳者の折原浩氏は私の大学の恩師です。著者のベンディクスは、1916年にドイツに生まれたユダヤ人の社会学者で、若い頃ナチスに対抗するユダヤ人組織に所属していましたが、1938年にアメリカに移住しています。1969年にアメリカの社会学会の会長に選ばれています。
この本は、マックス・ヴェーバーが1920年に亡くなって40年間、その学問については断片的な利用ばかりで、全体像をきちんと振り返る人が誰もいなかったのを、初めてまとめた労作です。そういう研究は本来ならヴェーバーの祖国の学者が行うべきものと思いますが、ヴェーバーの死後のドイツは社会学がマルクス系と国家社会主義系に分裂し、そのどちらもヴェーバーを重視しませんでした。戦後においても、ドイツではヴェーバーの全体像を探ろうとする動きは見られず、一方で以前紹介したモムゼンのヴェーバー批判のような、ヴェーバーの政治的な面のみが注目されたりしました。そういう中でこのベンディクスの著作が出てきた訳で、大きく分けて「宗教社会学論集」と「経済と社会」という2つの大きな研究の流れに加え、ヴェーバーの初期の研究まで視野に入れたものです。ただ、「理解社会学」「理念型」「価値自由」といった、ヴェーバーの社会科学の方法論については、おそらく著者はそれらが時代遅れだと評価していたのかまったく取り上げられていません。
ヴェーバーの著作というのは、「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」「職業としての学問」「職業としての政治」くらいはまだ何とか読めるのですが、この本で紹介されている「儒教と道教」や「ヒンドゥー教と仏教」、「古代ユダヤ教」の宗教社会学三部作は、繙かれた方はおわかりと思いますが、とても難解というか、はっきり言って知らないことばかり出てきて途方に暮れる、という状態に誰もが陥ります。(「儒教と道教」は東アジアの事を扱っているのでまだましかも知れませんが、ヴェーバー特有の用語で分析される中国社会はこれはこれでまた難解です。)特に「古代ユダヤ教」については、日本人で旧約聖書に出てくるユダヤ人の歴史に詳しい人などまずほとんどいないと思います。その結果、これを読むと、ヴェーバーを通じて旧約聖書を学ぶというある意味倒錯を起こすことになります。
また、もう一方の「経済と社会」については、こちらは有名な編集問題があり、この著作はヴェーバーの生前に一冊にまとまった著作として世に出たものでなく、ヴェーバーの妻のマリアンネがヴェーバーの死後残された遺稿を彼女なりに整理してある意味無理矢理に一冊の著作として出したものです。そういう訳で、各論考のつながりがどうなっているのかという問題に加え、「旧稿」と呼ばれる第一次世界大戦前に書かれた部分に出てくる概念について、本来は「理解社会学のカテゴリー」という論文に準拠すべきなのに、旧稿の後から書かれた「社会学の根本概念」が「間違った頭」として「経済と社会」の冒頭に長い間置かれて来た、という問題があります。また「法社会学」とか「支配の社会学」、「宗教社会学」といった部分部分の論考を一つ一つ取っても、ある意味膨大な比較文明史的な題材が扱われて、どれ一つを取っても簡単に読めるものはありません。
以上のような状況なので、ヴェーバーに関しては、適切な入門書の必要性は非常に高いのですが、残念ながら日本で「○○新書」の類いで出ている「ヴェーバー入門」の諸冊は、きちんとヴェーバーの学問全体をまとめたものは一冊も無いといってよく、それぞれの著者が自分の関心のある所だけをつまんで断片的に論じているものがほとんどです。
そういう意味で、このベンディクスの本は、唯一のきちんと読む価値のあるヴェーバー入門書であり、ある程度ヴェーバーを知っている人にとっても十分読む価値のある本だと思います。
ただ欠点はあって、テンブルックにも訳者である折原浩先生からも同じく批判されていますが、後に執筆された「古代ユダヤ教」を「経済と社会」での主要研究テーマを設定するキーになっている、という解釈はヴェーバーの研究の順番と一致しないため成立しません。ただそうは言っても、私も「経済と社会」の底に流れるテーマは、宗教社会学のメインテーマである「合理化の進展」が様々な文明・社会でどのように発達してきたか、ということだと思い、そのテーマは「古代ユダヤ教」が書かれる前に既にヴェーバーの中ではっきり確立していたと思います。
個人的にこの本で啓発されたのは、私は学生時代ヴェーバーの論考を読みながら、その中に取り上げられている文化人類学的な素材が極めて限定されていることが残念でした。ヴェーバーの時代にもフレイザーの「金枝篇」とか、グリァスンの「沈黙交易」(The silent trade)などの人類学的知見があり、ヴェーバーの論考の中にも出てきます。しかし、近代的な文化人類学の始まりはブロニスワフ・マリノフスキーの「西太平洋の遠洋航海者」とラドクリフ・ブラウンの「アンダマン島民」が出てきた1922年とされており、ヴェーバーの死後2年後です。その後、いわゆるフィールドワークによって、色々な西欧以外の社会の分析が進み事例が集まる訳ですが、ヴェーバーがそうしたものを見ることが出来ていたら、と思わざるを得ません。この本に、私と同じようなことを考えている人が多い、と指摘されていました。(余談になりますが、そういう文化人類学から出てきた素材を用いて、ヴェーバー的な分析を行った人は、私はカール・ポランニーだと思います。)
柊・オ・コジョの「文化の逆転 ―幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)―」
 (以下はAmazonへのレビューで書いたものです。)
(以下はAmazonへのレビューで書いたものです。)
柊・オ・コジョの「文化の逆転 ―幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)―」という本を読了。Amazonで偶然見つけたもの。Kindle版だけの本で、元はブログの記事をまとめたもののようです。以前「北斎とジャポニズム」という展覧会を見て、北斎の浮世絵に影響された西洋の画家達が、北斎の構図とか人物のポーズとかを真似しつつも、決して浮世絵そのままではなく、線も色も浮世絵よりはるかに複雑微妙だったという違いを感じ、その理由を知るヒントになるかな、と思って読んでみたものです。
作者の方についてはどういう方かまったく知りません。ですが、博引旁証ぶりはかなりのもので、私がほとんど知らない人名がいっぱい出てきて、文献参照は実に800以上にも及びます。
それはいいんですけど、ある意味やり過ぎというか、そこまで文献参照しないと自分の意見を書けないのかな、という所が気になりました。そうやってたくさん引用して出てきた結論が、「日本人は自然と一体化しているという考えを好み、西洋人は自然を人間が支配していると考える」といった、ある意味誰でも知っているようなことだったりします。
それでもまあ参考になったのは、日本の絵画が気韻生動、徹底した観察、線を一気呵成に描くことの重視といった指摘で、それは北斎と西洋画家の違いを知る上で参考になりました。この線を一気に描くという伝統は、たとえば手塚治虫の漫画とかにも受け継がれていると思いますけど、そういう指摘はなかったです。
後、Kindle版で300円という書籍に文句を言っても仕方がないのですが、この人「縦中横」を知らないようです。そのため、アルファベットや数字が横に寝てしまっていて、縦書きとしては読みにくいです。また、Malerei(絵画)というドイツ語が何故かWalereiとMとWがひっくり返っていたり、明らかな誤記があったりして、もうちょっと校正をしっかりやって欲しいです。さらには本文中で参照されている図(絵)が巻末に置かれているだけで、リンクにもなっていないので、一々見に行くのが非常に面倒です。またその絵自体もサイズが小さくて見にくいです。
表紙は萌え風ですが、中身はそれなりにちゃんとしています。たぶん作者はどこかのアカデミズムの世界の人じゃないかと思います。ちゃんと校正すれば普通の紙の本として出して問題ないレベルだと思います。
