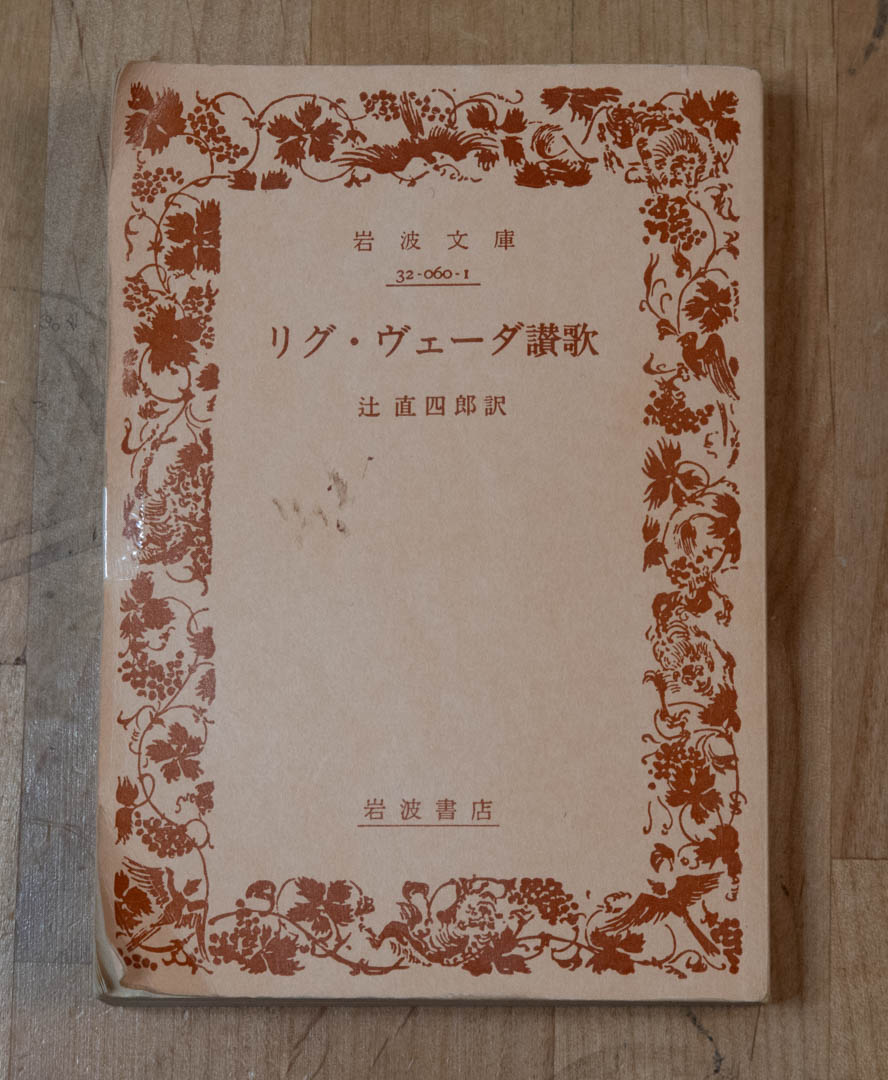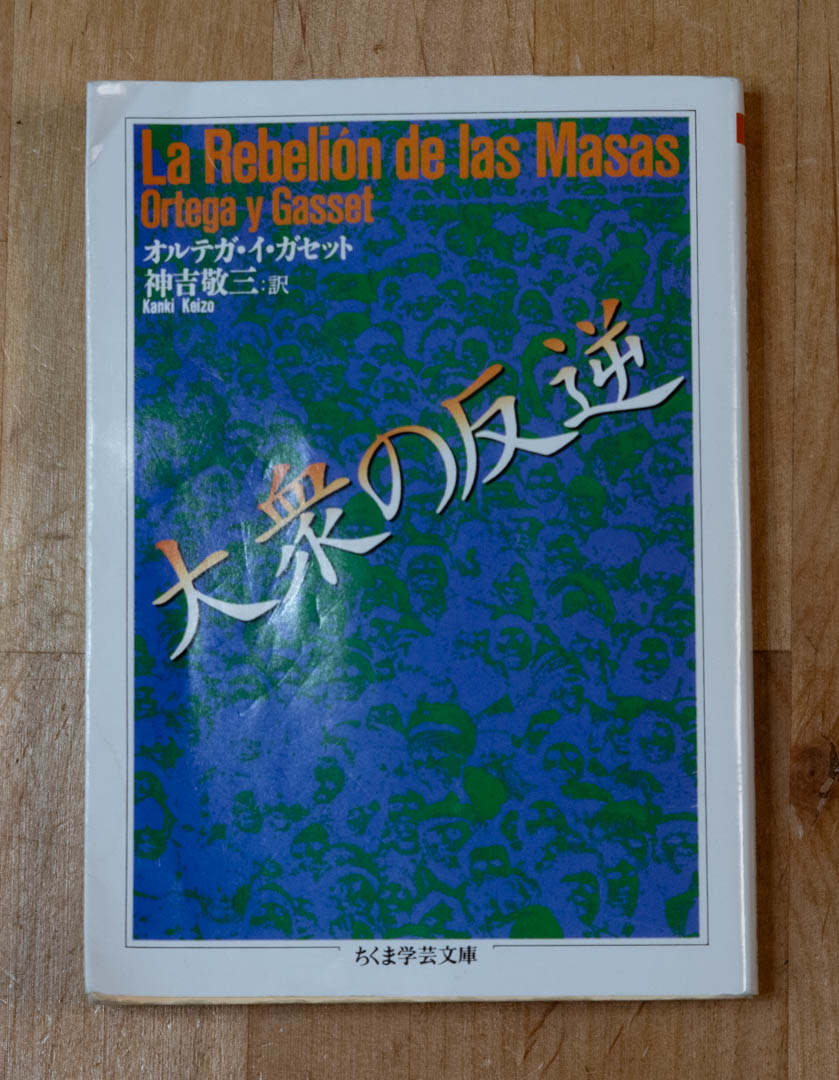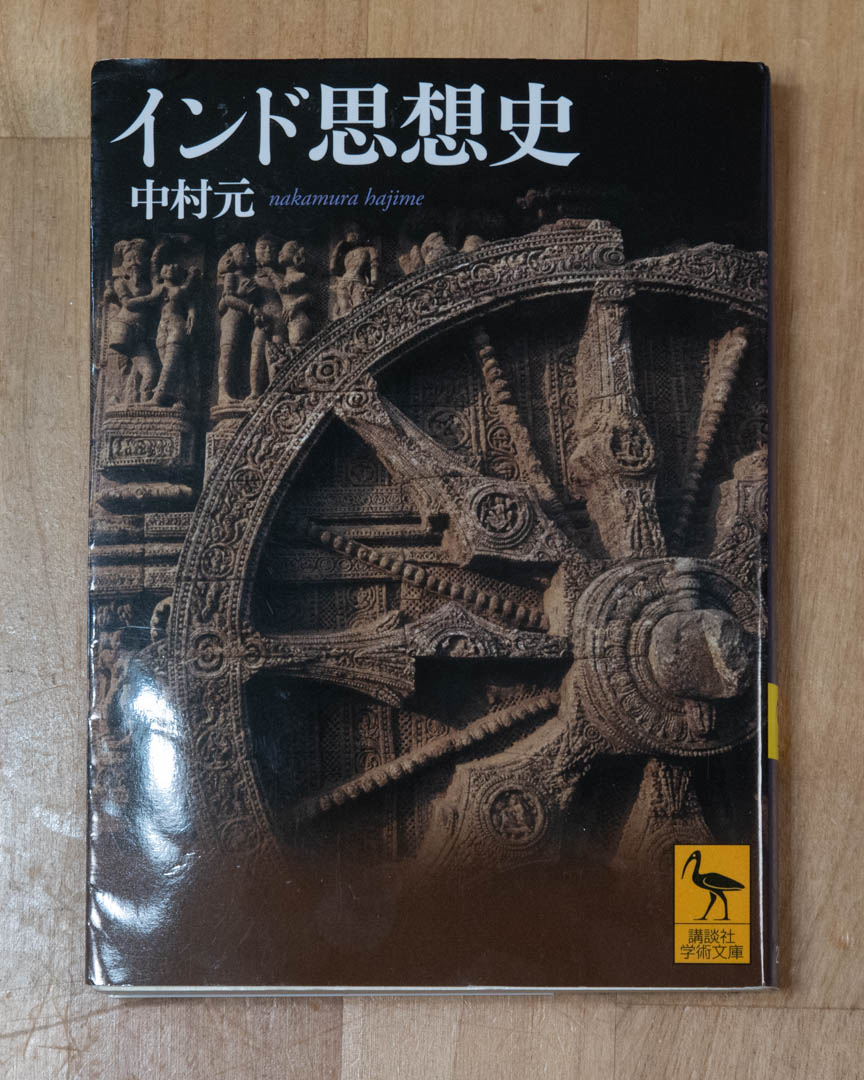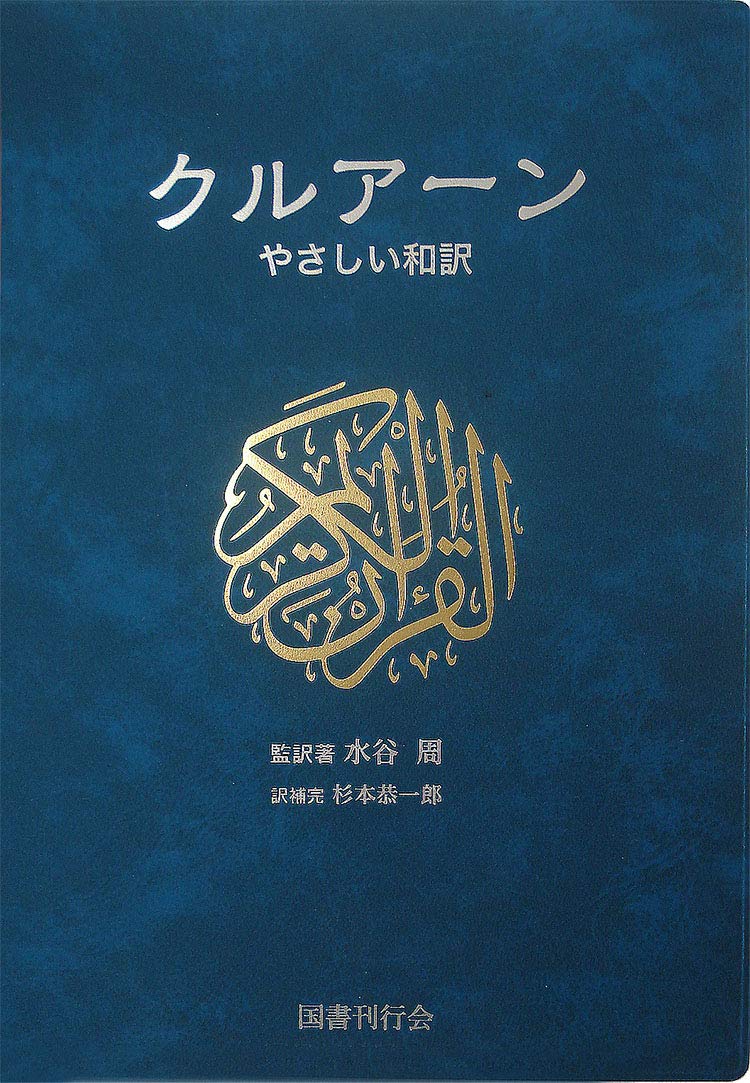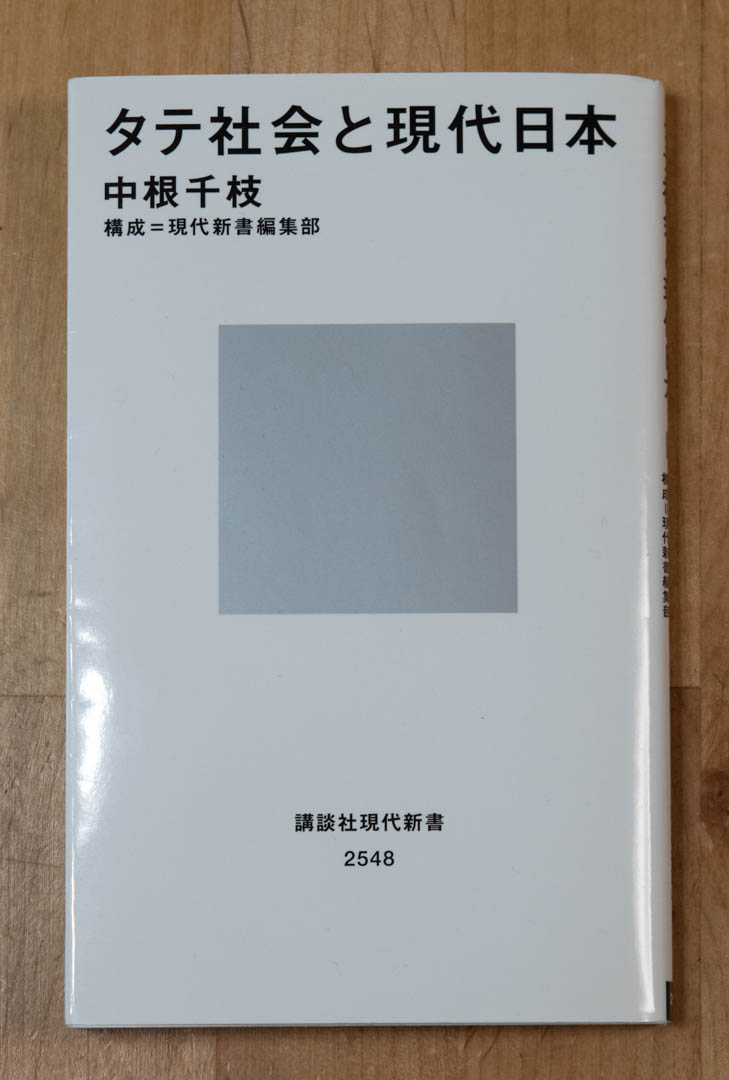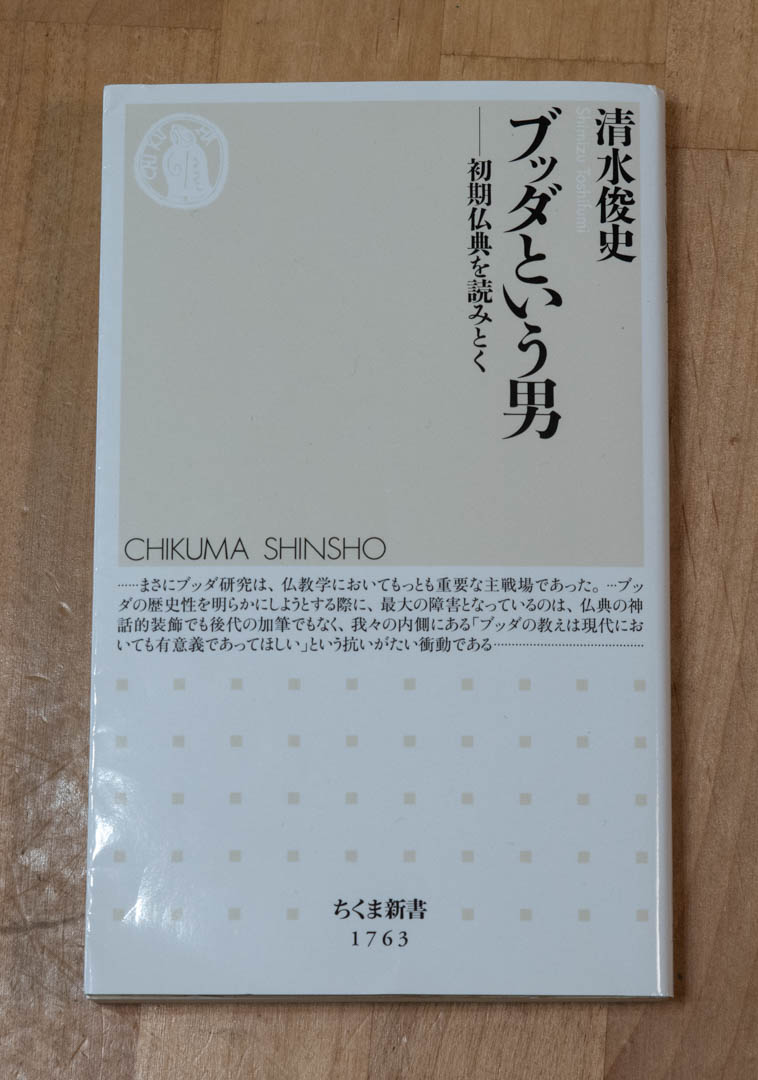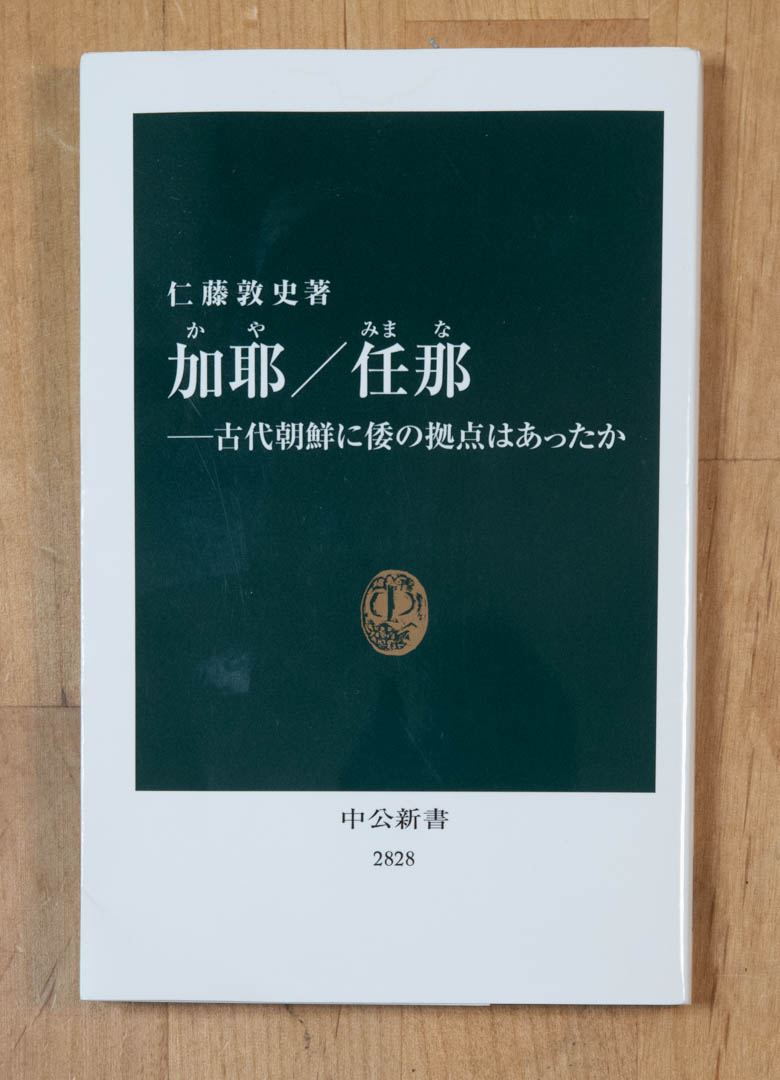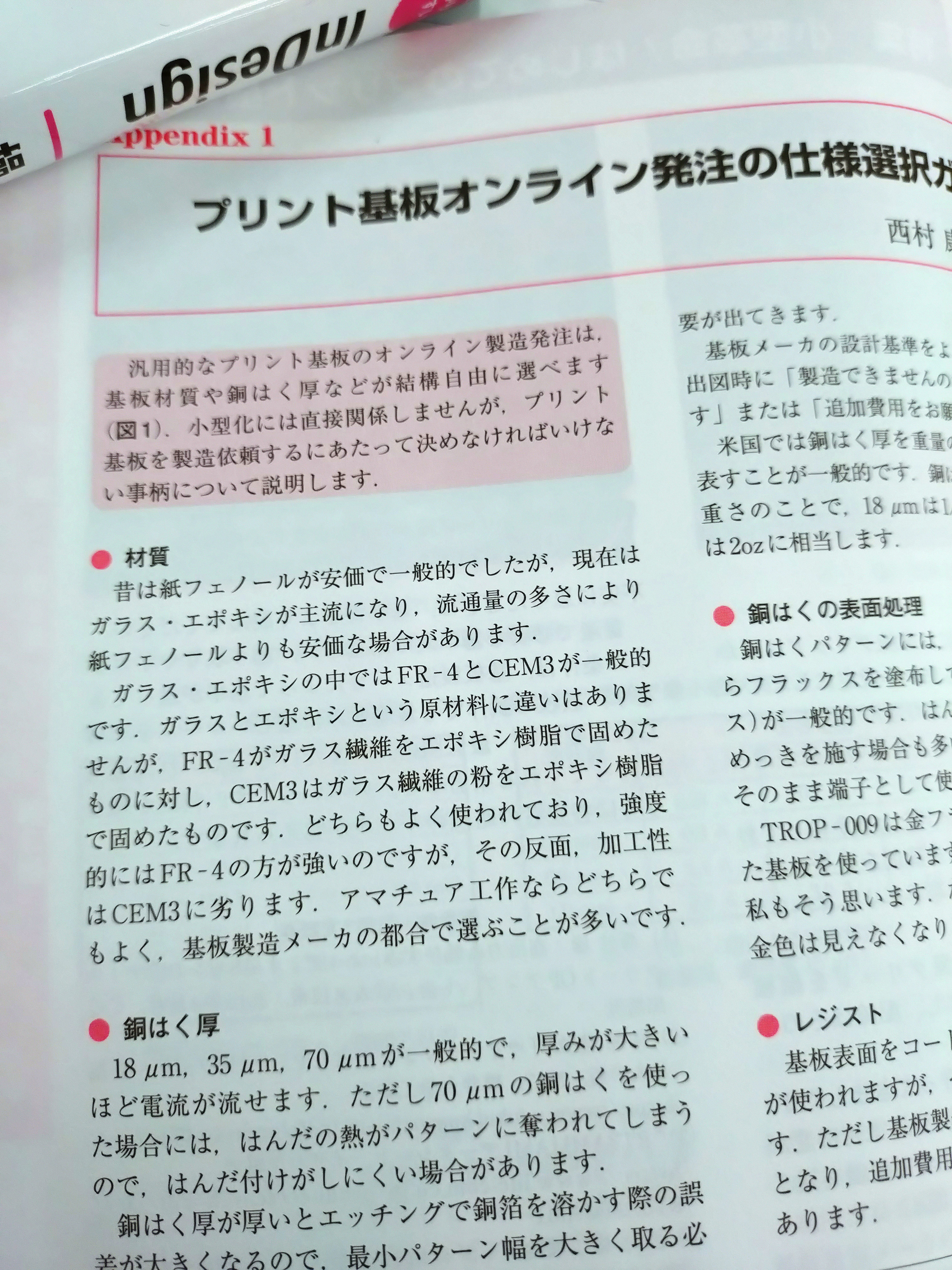 トランジスター技術の2025年2月号は、プリント配線板特集ですが、この記事が間違いだらけ。2点だけ指摘しておきますが、きちんとチェックしたらおそらく20箇所くらい不適切な内容がありそうです。
トランジスター技術の2025年2月号は、プリント配線板特集ですが、この記事が間違いだらけ。2点だけ指摘しておきますが、きちんとチェックしたらおそらく20箇所くらい不適切な内容がありそうです。
(1) プリント配線板の材料で、FR-4がガラス繊維をエポキシで固めたもの、CEM-3はガラスの粉をエポキシで固めたもの
馬鹿か、という説明です。FR-4はガラス布(にエポキシ樹脂を含浸させたプリプレグ)を使ったもの、CEM-3はガラス布とガラス不織布を組み合わせたものです。(樹脂はどちらもエポキシ樹脂)
(2) プリント配線板の穴開けは今はレーザー加工が主流になった
これも馬鹿か、です。プリント配線板の穴開けの主流は今でもドリルビットを使ったN/Cドリルマシンです。レーザー加工はビルドアップ基板などの特殊基板で多く使われますが、生産性の点でもコストの点でも主流にはなっていません。
私が日立化成で銅張り積層板を売っていた頃は、配線板の生産量は日本がトップだったと思いますが、今はおそらく上位10位にも入らないと思います。当然の結果として正しい知識を持たない人が増えてきている訳です。
これを書いている「西村康」というライターは同じ号で突入電流軽減回路についても書いていますが、こちらもそもそも「突入電流」という単語を知らず「アンプの回路が不安定になる」とか意味不明なことを書いています。更には電源スイッチの2極品について入手性が悪いとか高いとか書いています。2極のスイッチはごく普通に販売されていますし、トグルスイッチではむしろ単極より2極の方が多いです。また価格もせいぜい数十円アップぐらいです。またここで何回が紹介したように電源スイッチは安全のための「両切り」にするために2極のスイッチを使うのが正道です。