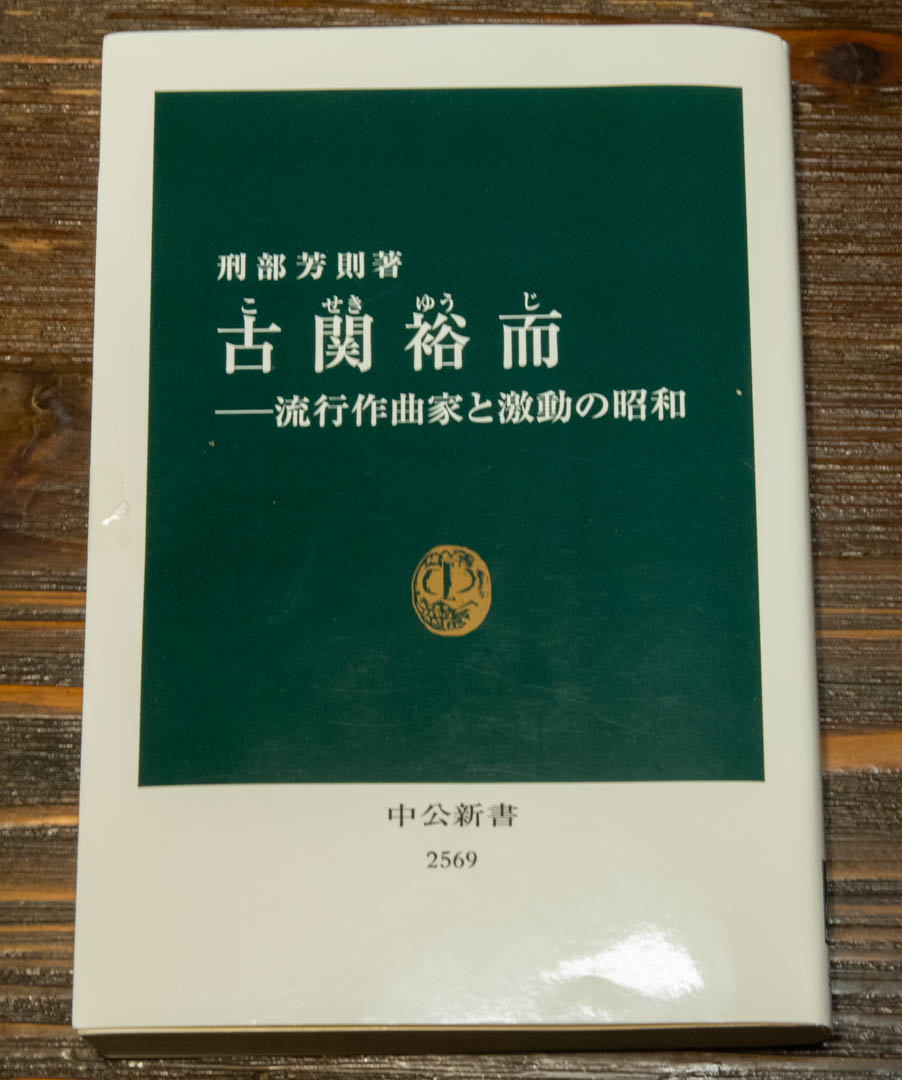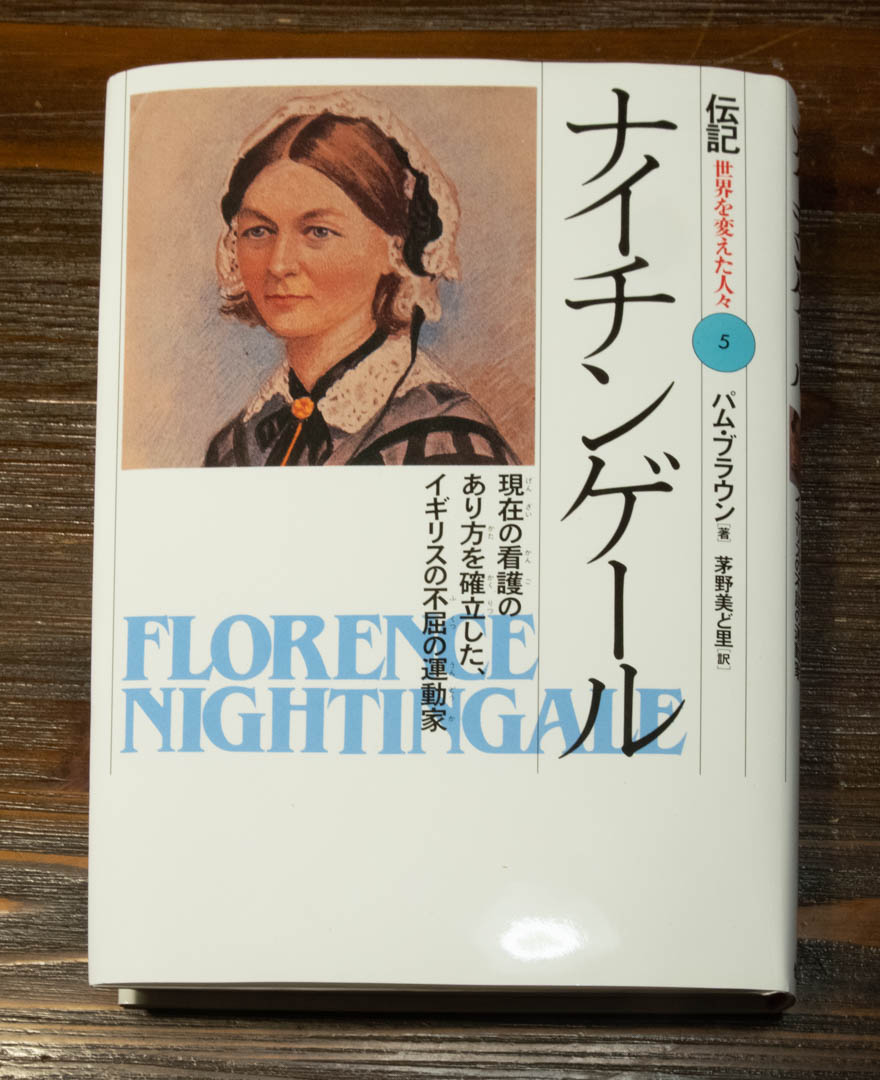7日間ブックカバーチャレンジの起源についての調査続報。
「7日間」という縛りは無いですが”Book Cover Challenge”という言葉の使用では今の所見つかったサイトではこれが一番古いようです。2014年7月12日にポストされたもの。
(引用開始)
Levels:
Level One: Read books for three requirements.
レベル1:下記の内3つの条件を満たす本をそれぞれ読みなさい。
Level Two: Read books for seven requirements.
レベル2:下記の内7つの条件を満たす本をそれぞれ読みなさい。
Level Three: Read books for all requirements.
レベル3:下記の内全ての条件を満たす本をそれぞれ読みなさい。
REQUIREMENTS:
1. Read a book with a dress on the cover.
本の表紙にドレスが載っている本を読みなさい。
2. Read a book that has no people on the cover.
本の表紙に人物が使われていない本を読みなさい。
3. Read a book with a cover you love.
あなたが好きなカバーの本を読みなさい。
4. Read a book with a cover you hate.
あなたが嫌いなカバーの本を読みなさい。
5. Read a book with a face-less person on the cover.
表紙に人が使われているけど顔が写っていない本を読みなさい。
6. Read a book where the title takes up most of the cover.
表紙がほとん書名だけの本を読みなさい。
7. Read a book with an animal on the cover.
表紙に動物が使われている本を読みなさい。
8. Read a cover that is your favorite color.
表紙の色があなたが好きな色である本を読みなさい。
9. Read a book with a bright colored cover.
表紙の色が明るい色の本を読みなさい。
10. Read a book with a darker-colored cover.
表紙の色が暗い(濃い)色の本を読みなさい。
Rules:
Post your books here.
ルール:
このブログのコメントとして投稿してください。
(引用終了)
所感:
(1)目的が本を紹介することではなく、条件を満たした「本を読め」なのでこれなら読書文化に貢献するでしょう。
というかこのサイトそのものが読書を奨励するサイトのようなので当然ですが。
(2)投稿例を見るとすべて写真ではなく販売サイトへのリンクなので、著作権侵害はまったくありません。
(3)このブログと2017年頃からのチャレンジとの関連は不明。

 七日間ブックカバーチャレンジについて色々と調べていて、チェーン投稿が何故いけないのか、昔と比べてネットワークの容量は格段に上がっているという意見の人がいました。
七日間ブックカバーチャレンジについて色々と調べていて、チェーン投稿が何故いけないのか、昔と比べてネットワークの容量は格段に上がっているという意見の人がいました。